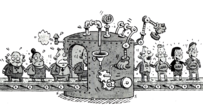弱いつながりが、縁故採用を復活させる
したがって人は弱いつながりの人脈を豊かに持っていれば、「遠くにある幅広い情報を、効率的に手に入れる」という面で有利になる。結果として、ビジネスの様々な局面で優位に立ちうるのだ。実際、多くの実証研究がその主張を支持している。図表4は、その代表的な研究の一部をまとめたものだ。
就職・採用など、労働市場での情報入手はその代表例だ。図表3-aで示したように、強いつながりにいる人はネットワークの範囲が狭く、同じような企業・業界情報しか手に入れられない。
逆に弱いつながりを持てば、図表3-bのように、ブリッジの多い希薄なネットワークに入り込むことができる。このネットワーク上では、様々な業界・企業についての多様な就職情報が遠くから、速く、効率的に流れてくる。
この点を初めて検証したのは、先のグラノヴェッターの1973年論文である。彼は、当時のボストン郊外で就職先を見つけたばかりの若者54人への質問調査を行った。そして彼らが就職の決め手になった情報をどのような人から得たかを聞いたところ、「頻繁に会う」相手から情報を得た人はわずか9人(17%)で、残りの45人(83%)は、「たまにしか会わない、あるいはほとんど会わない」弱いつながりの相手から得ていたのである。
近年も同様の結果が得られている。シカゴ大学のヴァレリー・ヤクボヴィッチが2005年に『アメリカン・ソシオロジカル・レビュー』に発表した論文では、ロシアの1143人を対象とした統計解析から、やはり人は強いつながりよりも弱いつながりを通じて就職先を見つける傾向を明らかにしている※3。
弱いつながりの効能は、採用する企業側にもある。例えば、いま日本のスタートアップ業界で注目されているのが、リファラル採用だ。これは「人材紹介会社や求人サイトなど既存の採用チャネルに頼らず、人と人との個人的なつながりを活用する」ことだ。平たく言えば「縁故採用」のことであり、むしろ古びた習慣のように聞こえるかもしれない。しかし、リファラル採用を徹底して成果を上げていることで知られるのが、日本発のユニコーン企業として注目を集め、2018年に上場したメルカリだと聞けば、その印象も変わるのではないか。
メルカリでは人事担当者が、社員に友人や知り合いで同社に向いていそうな人、関心のありそうな人を紹介してもらう仕組みが定着している。同社HR担当の石黒卓弥氏は、「経営陣をはじめ全員(がリファラル採用を担っている)」と述べる※4。
さらに興味深いのが、同社が行うミートアップ(同社に関心のある人と人事担当が会うイベント)に対する考え方だ。石黒氏は、以下のように語っている※5。
(メルカリが)定期的に開催しているミートアップもそうです。わたしはのべ500人くらいに会っていますが、仮に1人に20人友達がいれば、彼らを起点として1万人がメルカリに興味を持っていただき、応募してくれる可能性もあるわけで。そうやって「ゆるやかに応援してくれる人」を増やしていこうと考えています。
このように、メルカリにとってミートアップとは、純粋な採用そのものだけが目的ではない。同社と同社に関心がありそうな有望人材を「ゆるやかにつなぐ」ための仕掛けでもあるのだ。まさにSWT理論にかなった発想といえる。
【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】
「弱いつながりの強さ」理論
戦略という研究領域の構造と理論の関係
伊佐山元、高岡浩三両氏の名言に学ぶ、イノベーションの極意
【著作紹介】
世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。
その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。
本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。
お買い求めはこちら
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※3 Yakubovich, V. 2005. “Weak Ties, Information, and Influence: How Workers Find Jobs in a Local Russian Labor Market,” American Sociological Review, Vol.70, pp.408-421.
※4 「メルカリのぶれない採用基準とは」サイボウズ式、2016年3月28日。
※5 ※4を参照。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)