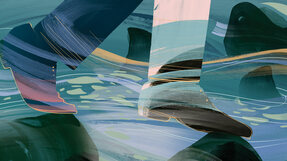-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
「共感」は職場で大きな力を発揮するが、
マネジャーの精神的疲労を招く
20年近く前に私が「共感」の研究を始めた頃、職場でのその価値についてさまざまな議論がなされていた。多くの見方は、生き馬の目を抜く競争の激しいビジネス界にとって、共感型リーダーシップ、すなわち他者の感情を理解し、気遣い、追体験する能力を利用したリーダーシップは「ソフト」すぎるというものであった。
しかしいまや、少なからぬ研究でまったく逆のことが実証されている。共感は弱みではなく、職場で大きな力を発揮するものなのだ。共感的な組織で働く従業員のほうが仕事への満足度が高く、創造的なリスクを取りやすく、同僚を手助けするようだ。深刻なバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥ったり、ストレスによる身体症状が出たりする確率がはるかに低く、逆境に直面しても立ち直りやすい。離職率も低い。
2022年に米国の1万5000人以上の従業員を対象にしたギャラップの調査によると、気遣いや思いやりがある組織に勤務する従業員のほうが、積極的に新しい職探しをする率がはるかに低い。アーンスト・アンド・ヤングが、大退職時代に離職した1000人以上を2021年に調査したところ、58%が離職の大きな原因として上司の共感不足を挙げた。さらにミレニアル世代やZ世代を中心に、従業員はリーダーからの共感をただ望むのではなく、要求するようになっている。