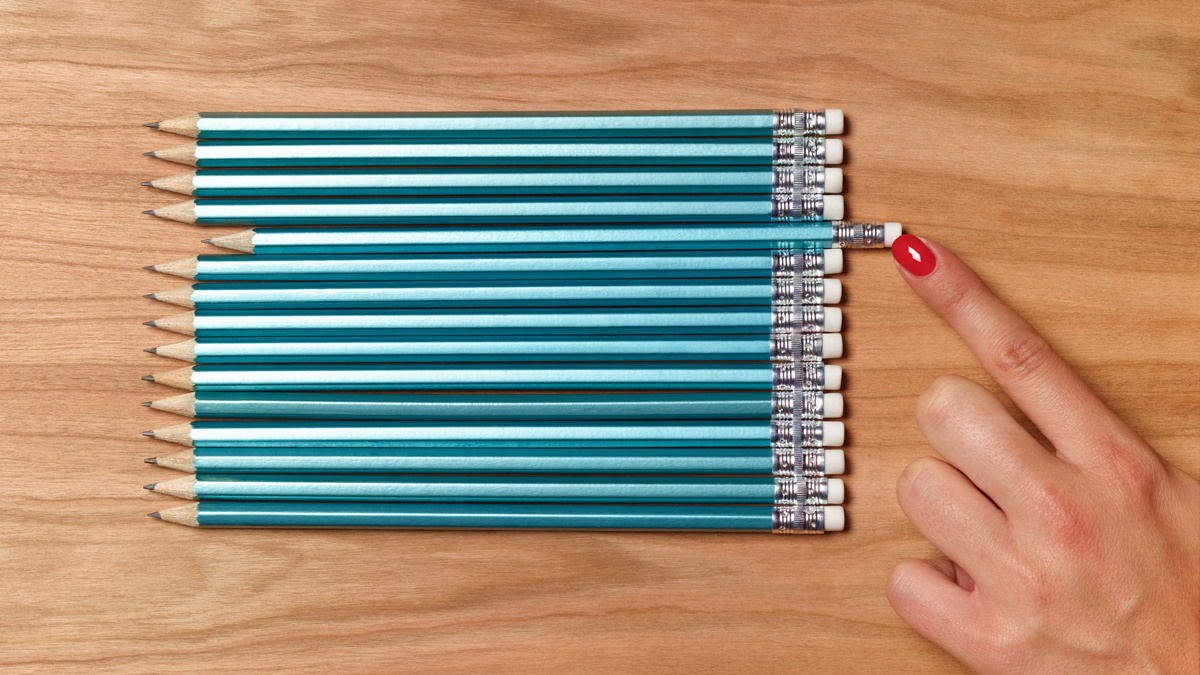
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
PMIの過程で非効率なことがM&A後に効果的になる
フェイスブックによる対話アプリ「ワッツアップ」(WhatsApp)の買収、IBMによるクラウド向けソフトウェア「レッドハット」(Redhat)の買収、半導体大手ブロードコムによるクラウド関連大手ヴイエムウェアの買収など、テクノロジー業界ではM&A(企業の合併・買収)がいちだんと増えており、成長を強力に後押ししている。テクノロジー業界におけるM&Aは、M&A全体の約20%を占め、既存企業が新興市場を支配し、戦略的な刷新を図り、新しい領域の知識を獲得し、技術力を高める役に立っている。
筆者らは10年以上にわたり、成功するM&Aと失敗するM&Aの違いを研究してきた。そのために3大陸の数百の企業のデータを集め、数十人のエグゼクティブの話を聞いてきた。特に重点を置いたのは、M&A成立後の当事者企業の統合(PMI)だ。その結果(『ストラテジー・サイエンス』誌に掲載予定)、PMIの過程では非効率に思えたことが、M&A後の企業が成長しようとする時、有効になることが多いという驚くべきインサイトが明らかになった。このインサイトは、会社の成長を効果的に管理したいリーダーにとって何を意味するのか。
非効率1:ミラーチーム
ミラーチームとは、買収企業と被買収企業が、機能的に同じチームをそれぞれ持ち、それぞれマネジャーと従業員を配置することをいう。ミラーリングは、2つの会社を有効に統合するための一つの手法だ。あるケースでは、統合企業が買収企業と被買収企業から1人ずつリーダーを選び、事業統合のためのミラーチームを組織した。2人のリーダーは「シナジー実現オーナー」と呼ばれ、同じ機能を持ち、それぞれの出身企業のリーダーから成るチームの指揮を執った。このアプローチは、2つの異なる組織がうまく融合することを可能にし、どちらかが相手の言いなりになるのではなく、両社が統合を積極的にリードすることを可能にした。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









