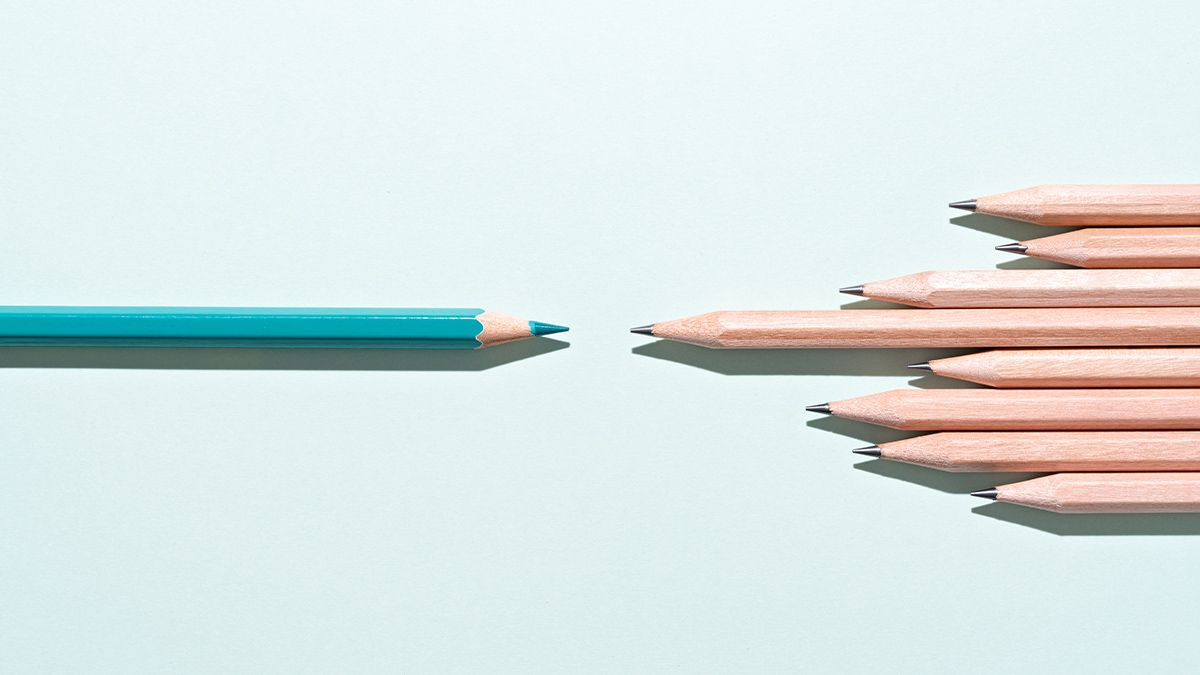
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業で困難な「暗黙知」の管理
仕事のやり方に関する知識を社内で共有する組織能力は、企業が事業活動を行うために不可欠だ。競合企業との競争でたえず重圧にさらされる中で、品質と安定性を確保しようと思えば、それは必須のケイパビリティといえる。
スタートアップ企業の場合は、チームのメンバーが互いの仕事ぶりを観察して学習することも可能だが、中規模企業や大企業ではそうはいかない。社内組織の縦割りの壁や地理的な断絶、業務や職能の種類の多さ、従業員の頻繁な入れ替わりと人事異動などの要因により、社内の知識移転は常に難しい課題であり続けている。
業務マニュアルや研修など、知識を明文化するための手立てとして、これまで一般に用いられてきたツールやメカニズムの類いには、いくつかの大きなトレードオフの関係がついて回る。
・指示が網羅的であればあるほど、指示を実行する役割を担う現場の人たちに、指示の内容が吸収、理解、記憶されにくくなる。しかも、あまりに網羅的な指示である場合、現場の人たちが抱く責任感が希薄化するリスクがある。
・指示が緻密であればあるほど、個々の顧客に合わせたカスタマイゼーションや従業員の創意工夫が行われる余地が小さくなる。
・指示が硬直的であればあるほど、環境の変化に合わせて変化を遂げる能力が弱まる。
人間による判断や、個別のニーズに合わせたカスタマイゼーション、そして環境の変化への適応などが要求される業務プロセスは、ひときわ明文化しにくい。その種の業務では、暗黙知を明らかにして把握すること、情報を絶えず更新すること、必要な時にしかるべき知識を取り出すことが難しいためだ。
その難しさは、現在のビジネス環境における変化の速さと予測不可能性の大きさによりさらに増幅されている。この2つの要素は、テクノロジーの進化と地政学的な不確実性により生まれている。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









