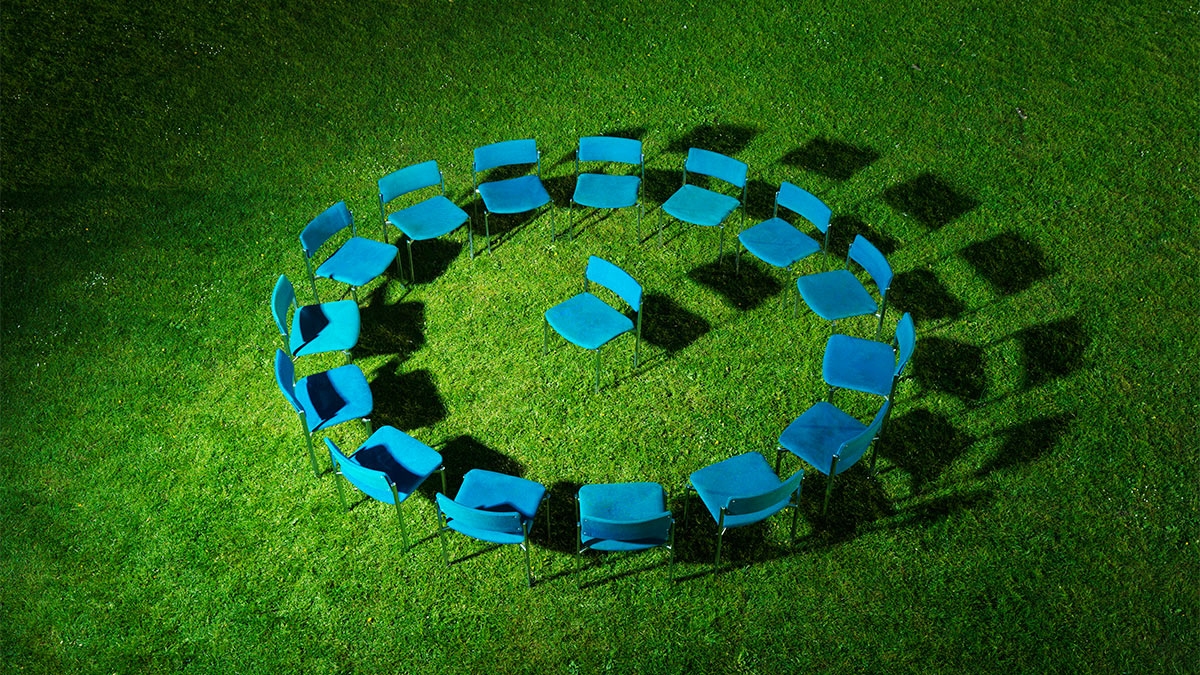
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
社外取締役が増加した背景
第2次世界大戦後の10年間、平均的な米国の上場企業では、取締役の75%がその会社に雇用されているか、何らかの形で会社と関係していた。いわゆる「社内」取締役または「非独立」取締役だ。
社内取締役は、1970年代までは、取締役会において大多数を占めていた。だが、ベトナム戦争とウォーターゲート事件の後、政府から企業まであらゆる機関に対する不信感が高まったことを受けて、コーポレートガバナンス(企業統治)という新しい概念が生まれた。
カリフォルニア大学バークレー校教授のメルビン・アイゼンバーグは、コーポレートガバナンスに大きな影響を与えた1976年の著書The Structure of the Corporation(未訳)で、取締役会の本質的な機能は経営幹部の監視であると主張した。
1977年には、取締役会における独立取締役と独立委員会の重要性を高めるニューヨーク証券取引所(NYSE)のルール改正が、米証券取引委員会(SEC)によって承認された。それまでNYSEは、上場企業の社外取締役を2人以上とすることしか定めていなかった。
ルールや規範が変わるにつれて、非独立取締役は次第に減少し、独立取締役が取締役会における少数派から多数派へ、そして圧倒的多数を占めるまでに拡大していった。2005年までに、米国の大手上場企業の取締役の75%が独立取締役になっていた。エグゼクティブ紹介大手のスペンサースチュアートの調査によると、この割合は2023年には85%に上昇した。一般的な企業の場合、これは社内取締役がCEOだけであることを意味する。
しかし実証研究によれば、一握りの例外をのぞき、取締役会の独立性と企業の業績の間に関連性はない。
取締役会の独立性と業績に関連性はない
1998年に行われた初のメタ分析(54件の研究を対象とし、40年以上にわたるデータを分析)によると、取締役会の独立性と企業の業績との間につながりは見られなかった。複数の文献レビューとさらなる研究でも、同じような結果となった。ある最近の文献レビューは、取締役の独立性に関する研究を次のように要約している。「コーポレートガバナンス(あるいはそれ以外の領域)の分野で、これほどまでに一貫して関連性がゼロだと結論づける文献ばかりなのは初めてだ」






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









