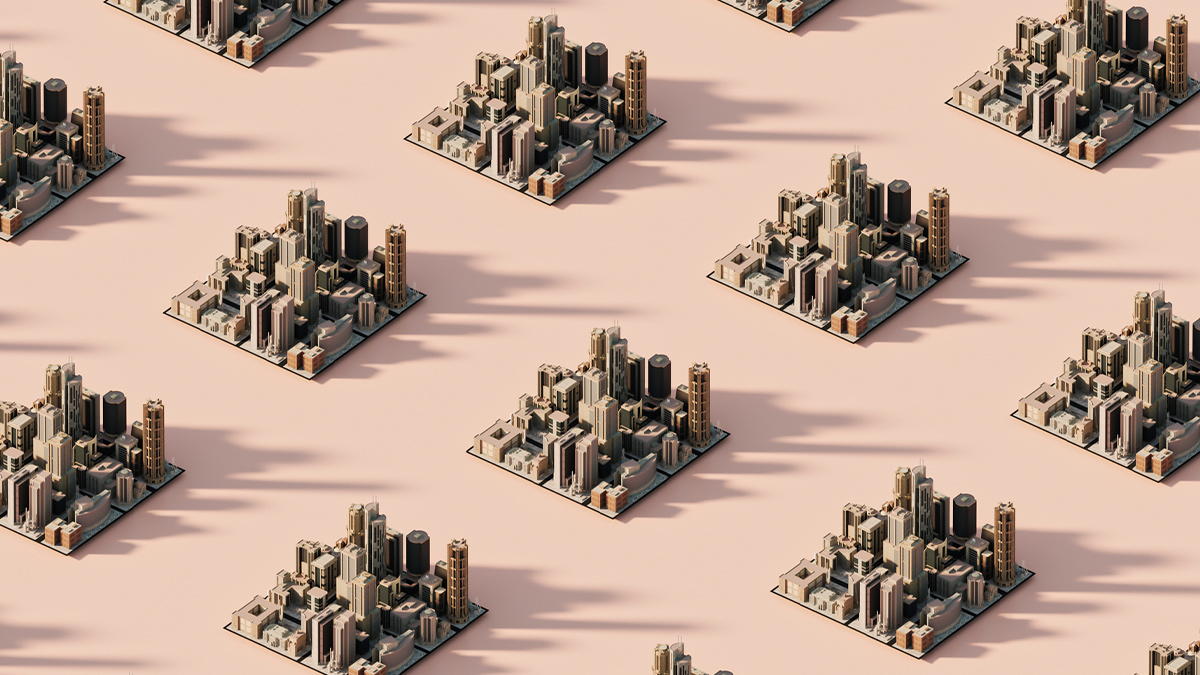
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AIドリブン企業はどのような点で他社と異なるか
AI時代において、企業は「持つ者」と「持たざる者」に分かれており、大多数は後者に属している。最近のボストン コンサルティング グループ(BCG)の調査によると、生成AIを使いこなしている企業はわずか1割にすぎない。しかし、これは従業員の責任ではない。実際、BCGの消費者意識調査では、7割の労働者が職場での生成AIの活用に熱心であることがわかっている。労働者は、学習を加速させるだけでなく、日常業務の労力を軽減する能力を評価しているのだ。その一方で、個々の労働者が仕事にAIを適用するボトムアップ型の利用から、企業がAI向けにプロセス全体を再設計するようになると、懸念が高まり、特に雇用が奪われるのではないかという不安がますます大きくなる。
とは言え、必ずしもそうなるわけではない。リーダーは、従業員を巻き込み、従業員の成長にAIを活用することで、AIのインパクトを拡大させることができる。筆者らの調査と、共著Personalized: Customer Strategy in the Age of AI(未訳)では、AIドリブンの企業は、以下の3つの点で他社と運営方法が異なっていることがわかった。
1. 戦略的優先事項にAIを組み込む。AIドリブンの企業は、ポートフォリオアプローチを採用し、責任あるAIへの投資によって競争優位を得る分野を優先する。彼らは解決すべき現実的な顧客の問題に着目し、より大きな投資を新たな価値の創造に向ける。
2. 部門間のサイロを取り払い、従業員をソリューションの形成に積極的に関与させる。こうした企業は、AIをスケールさせるためには営業、財務、アナリティクス、オペレーション、規制の各チームが協力しなければならないことを認識している。また、仕事を遂行し、官僚主義を排除するには、小規模で機敏なチームが必要であることも理解している。
3. 効率の向上だけでなく、体験の向上のためにAIを活用する。AIドリブンの企業は、顧客の満足度が高まり、従業員体験も向上するのであれば、あらゆるレベルの従業員がAIを積極的に受け入れることを理解している。
顧客の問題を解決するためAI活用の優先順位を上げる
取締役会、経営幹部、リーダーシップは、こうした取り組みにおいて大きな役割を担っている。たとえば、ある大手消費財メーカーは、戦略立案プロセスの各段階にAIの視点を組み込み、顧客価値創造と効率性のどちらを優先してAIをスケールさせるかについて、厳しい議論とトレードオフを迫られた。どちらも非常に重要であるため、同社は資金をすべて利益に組み込むのではなく、効率化を加速させて顧客価値向上のための投資に充てることにした。それにより、AIが削減のためだけではなく、成長のための手段になることを従業員にも理解してもらうことができた。迅速な対応が急務であることが明らかになるにつれ、同社は、クラウドコンピューティングプロバイダーやその他のテクノロジーベンダーとのパートナーシップを活用し、導入ペースを高め、必要な投資をより迅速に行うべきであることを認識した。
法務顧問や最高データ責任者(CDO)、最高セキュリティ責任者(CISO)も、企業の運命を左右する。しかし、将来を見据えた企業は、より微妙な政策を導入し、労働力のスキルアップの必要性を認識しつつ、責任あるAIに関する正当な懸念にも対処している。ある小売企業のCIOは、7種類の生成AIツールを使用している従業員の割合を積極的に測定する一方、責任あるAI設計のための全社的なフレームワークを展開し、AIを適用する準備ができていない3つの「禁止」ゾーンを明示している。
異なる働き方
最終的に、AIを大規模に展開するためには、部門横断的な作業チームが必要となる。筆者らの行ったCMO(最高マーケティング責任者)調査とパーソナライゼーション・インデックス調査によると、生成AI分野を牽引する上位10%の企業は、予測AIソリューションの拡張において最も進んでいる企業でもあることは偶然ではない。それらの企業はすでに運用基盤を整備しており、データとテクノロジーの成熟度においてさらに先を行っている。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









