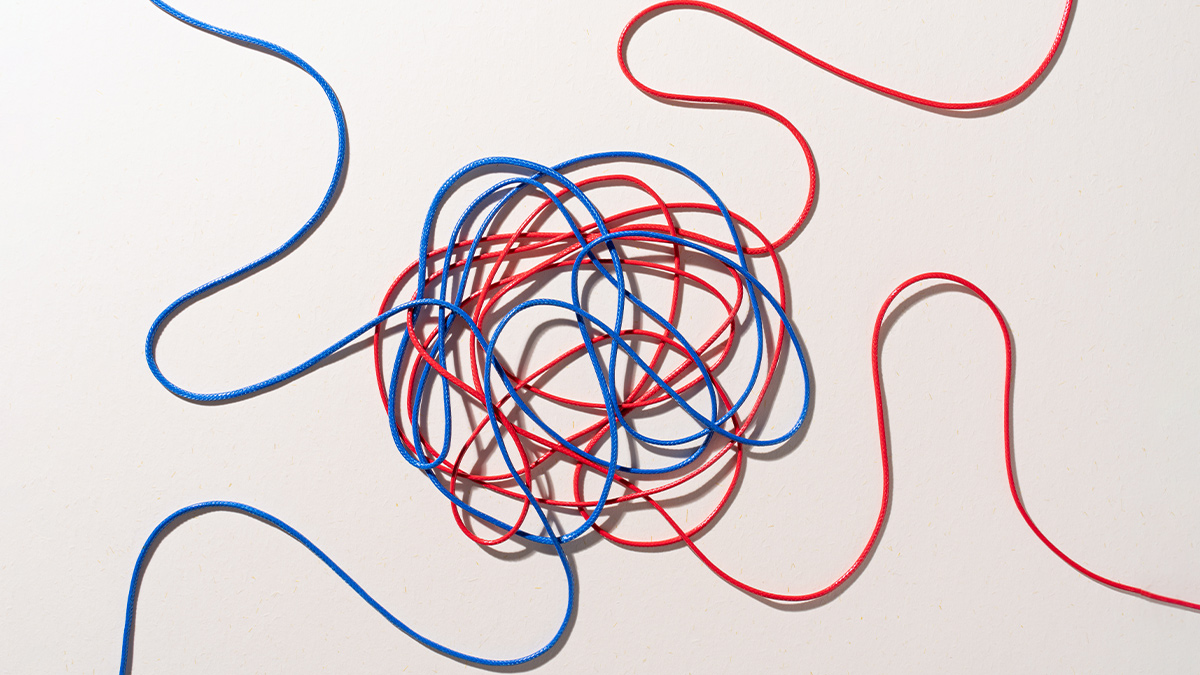
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
不確実な状況下での意思決定
2020年1月、家電量販店大手ベストバイのCEOコリー・バリーは、就任からわずか8カ月で、中国で新型コロナウイルスが広がっていることを知った。3月初旬には、バリーのもとに、ウイルスが米国の沿岸部で急速に広がっているという報告が届いた。その時、バリーは世界的なパンデミックへの対応マニュアルがなく、またコロナ禍の性質や範囲、および期間がまったく不明であることに気がついた。
そこでバリーは、理解できない問題を無理に解決しようとするのではなく、チームを集めて、不確実な状況下での意思決定の原則を確立した。その原則は3つあった。(1)従業員と顧客の安全を最優先すること、(2)レイオフの恒久化を可能な限り避けること、(3)長期的な価値創造を基準として意思決定を行うこと、である。何より注目すべきなのは、目先の収益維持にはいっさい言及していないことだろう。
新型コロナのような複雑な(complex)問題は、ベストバイがそれまで扱ってきたような複雑な(complicated)問題への従来の問題解決手法では解決できないことを、バリーは理解していた。従来の問題解決手法とは、問題を論理的な構成要素に分解して、それぞれを解決するためのアプローチを練り、それを論理的な一つの解決策にまとめるというもので、価格決定やプロダクトに関する決定を下す時に取るアプローチだった。
経営陣が対処法を検討する以前に、コロナ禍の複雑さとその不確実性を受け入れる必要があった。こうして3つの原則は、経営陣がコロナ禍の進化する状況に適応するための指針となった。たとえば、ベストバイは当初、全米1025店すべてを閉鎖せざるをえなかったが、数カ月後には最初に安全に営業を再開した大手小売業者の一つとなった。店舗の閉鎖に伴い、ベストバイは5万1300人の従業員を一時帰休させたが、その多くが営業再開とともに職場に戻った。この過程を通じて、バリーは現場のチームを強く信頼し、彼らは最初に合意した原則に基づき、最善の決定を下した。どの決定も暫定的なものであり、危機の展開に応じて見直しや変更が必要になることを、バリーと彼女のチームは理解していた。
2種類の「複雑な問題」
コロナ禍により生じた問題は、複雑な(complicated)問題と複雑な(complex)問題の違いを浮き彫りにしている。これらの用語はしばしば混同される。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









