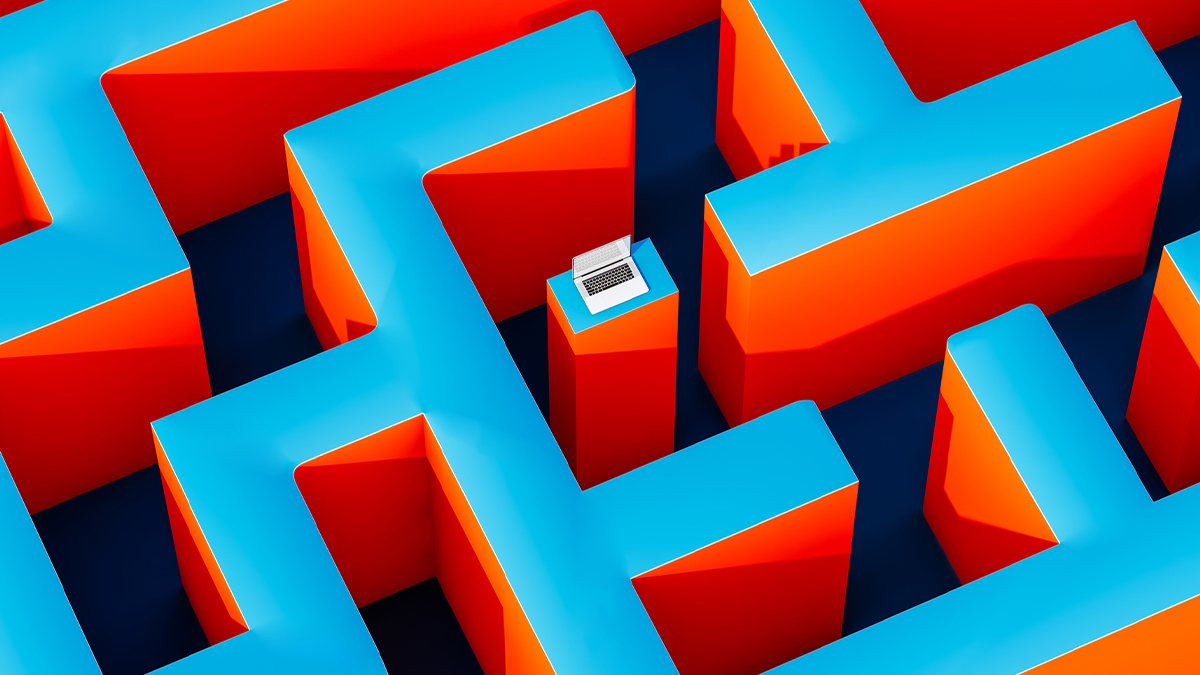
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
人間の判断が大きな違いにつながる
AIの急速な進歩は、コストが高く誤りを犯しやすい人間の代わりになることで、企業の意思決定に革命をもたらす可能性を生み出した。しかし、これまで以上に多くのデータを収集し、これまで以上に強力なアルゴリズムに供給するだけで、企業が真実を解明し、正しい意思決定を行い、価値を創造できると考えるのは短絡的だ。この誤った考えは、「データイズム」(データ至上主義)と呼ばれる。
意思決定は、単なるデータ集計とアルゴリズム分析といった行為ではない。信頼できるデータソースを選択し、想像力を働かせて事実を超えた可能性を思い描き、解決策の実現可能性を判断するといった、多くの微妙な要素が必要になる。これらは、人間が機械よりも生得的に有利な分野といえる。重要なのは、それらには暗黙的で、訓練されていない人間の能力が関わっているということだ。
コダックと富士フイルムのケースを考えてみよう。両社とも、デジタル写真の台頭を示す同じデータにアクセスし、成長と収益性の最大化という同じ目的に従ってそれを評価した。それでも、両社は異なる決断を下した。コダックはアナログ製品を倍増させた一方で、富士フイルムは多角化し、デジタル技術に投資し、化粧品など他の選択肢を追求し、生き残った。同じデータが、ソニーグループには別の決断を促した。ソニーは市場のチャレンジャーとして、デジタル写真の台頭を参入価値のあるチャンスと捉えた。
この違いは、意思決定が解釈、コンテキスト、戦略的枠組みという、いまだ人間の判断が重要な分野によって左右されることを浮き彫りにしている。
意思決定の全体像
筆者らは、企業の意思決定に関するみずからの経験や、意思決定科学に関する文献(軍事、医療、R&Dなど)に基づき、暗黙的であることが多いものの、ほとんどの意思決定に関与する、データやアルゴリズムには及ばない8つの側面を特定した。これらは、自動車の購入というシンプルな例を通して理解することができる。
1. 最終的な目標を定義する
すべての意思決定は、最終的に人間の目的にかなうものだ。それを明確にすることは、成功がどのようなものかを理解する上で極めて重要である。自動車を買う人にとっての目的は、高級車で自分のステータスを示すことかもしれないし、子どもたちが安全に通学できるようにすることかもしれない。
企業にもまた、経済的繁栄から社会貢献、環境保護に至るまで、最終的な目標があり、それは各社で著しく異なる。人間の価値観が主観的であることを考えると、人間の最終目標を定義することをAIに委ねることはできない。
2. 当面の目的を設定する
最終的な目標を達成するためには、その過程でより小さく、直接的で、具体的な決断を下さなければならない。自動車の購入の例で言えば、最終目標は一定の安全基準を満たした車を購入することかもしれないが、その車が所定の予算内に収まるようにもしたい。企業の場合、最終目標は前年比10%の売上増かもしれないが、短期的な売上成長の最適化が長期的なブランド評価を損なわないようにする必要もある。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









