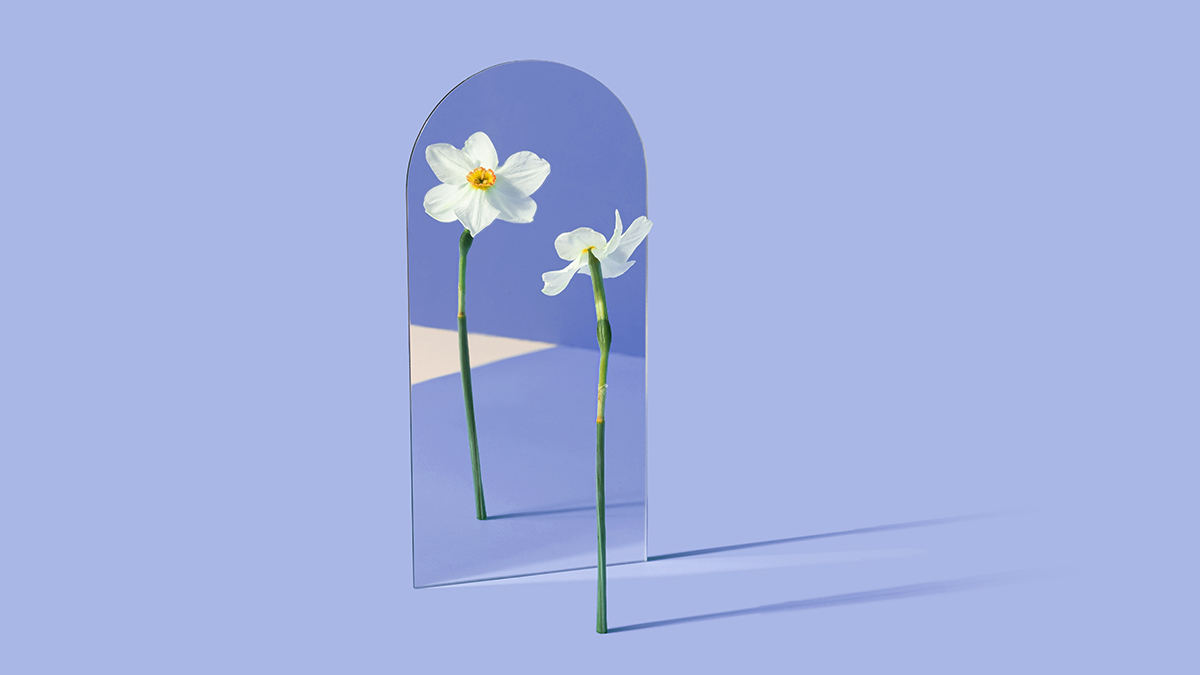
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
デジタルツインは中小企業でも活用できる
戦略のリスクが最も高まるのは、実行時である。この時点からあらゆる誤算が具体的なコストを伴うからだ。そのリスクを減らす方法の一つは、実験環境でプロセスを何度も繰り返し、毎回少しずつ向上させていくことである。
この種の取り組みとしてトヨタの継続的改善のシステムが有名だが、継続的にデータを監視し、多くの細かい意思決定によって対応する必要があるため、実践は難しいかもしれない。
しかし、この実験をデジタルで行う方法がある。デジタルツインと呼ばれるもので、基本的にはモノやプロセス、たとえば風力タービンや配送ルートなどのデジタルレプリカを指す。継続的な使用を前提に設計されたデジタルツインを活用することで、企業は複雑で多くの変数を伴う課題を繰り返しシミュレートし、最適化できる。これにより、物理的環境で実験を行う場合に生じる学習コストが削減される。
かつては大企業の独占分野であったデジタルツインだが、高度なAIの登場によって、いまでは中小企業も利用できるようになった。本稿では、重要なサービスプロセスのデジタルツインを構築した中小企業のケーススタディを通じて、構築に向けた5つのステップを詳述する。
デジタルツインを自作する5つのステップ
1. ビジネス目標を定義する
一連の取り組みは、デジタルツインのビジネス目標を明確に設定することから始まる。自社が解決したい問題は何か、具体的にどのような成果を求めているのか、である。
小さなビール醸造所を営むブルーマスターズ(仮名)の例で見ていこう。同社は従業員27名の独立系ビールメーカーだ。現代的な機械化によって年間2万樽以上を生産し、大手ビールメーカーとの厳しい競争に直面している。消費者は価格、入手しやすさ、ブランディング、味を重視し、主要顧客であるホテルは特に迅速なサービスを求めている。
樽の効率的な供給と回収は、ブルーマスターズの顧客サービスにおける重要な要素だ。ホテルは樽を切らさないよう安定的な供給を必要とし、保管スペースを最大化するために空樽の効率的な回収も求めている。一方でブルーマスターズは、何千もの樽という高額な資産が配送を待って無駄に放置される事態を避けなければならない。
したがって、同社が樽の稼働のデジタルツインを構築するうえでの目標は、ビール樽が醸造所から顧客のもとに移動し、再び戻ってくるまでを効率的に管理することであった。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









