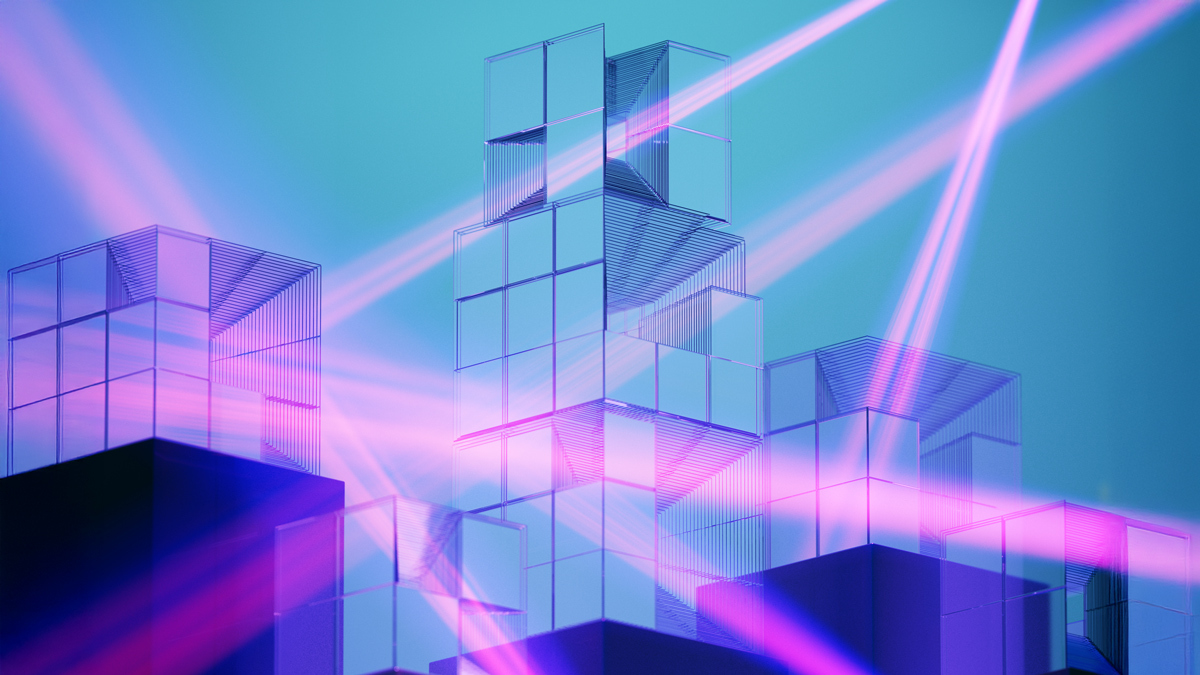
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AI活用の成果に格差が生じている
2021年、筆者らは企業を対象に調査を行い、自社のオペレーションでどのようにAIを活用しているかを尋ねた。すると、とりわけ高い成果を上げている企業、言わば優等生企業は、ガバナンス、テクノロジーの導入、パートナーシップ、人材、データの入手しやすさという、5つの領域で他の企業より傑出していることがわかった。
この調査を実施してから3年が経ち、その間に生成AIという新しいテクノロジーが華々しく登場した。そこで2023年の後半に、筆者らは再度、調査を行うことにした。自動車産業から鉱業に至るまで100社以上の企業を対象に、幹部に掘り下げたインタビュー調査を実施したのだ。
その結果、注目すべき傾向が3つ浮き彫りになった。
第1は、とりわけ高い成果を上げている優等生企業と、それ以外の調査対象企業の差が3年前よりもさらに広がったということ。2023年に行った調査では、上位25%の優等生企業は、下位50%の企業と比べて成果のレベルが3.8倍高かった。この差は、2021年には2.7倍だった。このように差が拡大した理由の一つは、時間を経るにつれて、優等生企業の強みが言わば雪だるま式に膨れ上がっていったことにある。
第2は、AI関連プロジェクトへの投資が回収されるまでの期間が以前より短くなっているということ。2023年の調査では、すべての調査対象企業でその期間は6~12カ月程度になっている。2021年の調査では、この程度の期間で投資が回収できるのは優等生企業に限られていて、それ以外の劣等生企業は、投資を回収するまでにたいてい18~24カ月を要していた。
3年間の経験を通じて、企業は多くの有益なことを学んだのだろう。ガバナンスの慣行が進化したことにより、企業が特に有望なAIの用途を見出し、そのようなプロジェクトを選びやすくなった面もある。加えて、以前に比べれば、手に入るデータがより完全なものになり、よりアクセスしやすくなり、質も向上した。
いまでは、AIソリューションのプロバイダーで構成されるエコシステムの規模も3年前より大きくなっている。そうしたプロバイダーを利用することにより、月額の料金を支払えば安定した成果を得られるようになり、前もって莫大な資金を投資する必要がなくなった。
また、AIが価値を生み出す潜在的可能性を持っていることが明らかになり、導入段階で直面する障害や、社内でぶつかる組織上の障害が小さくなったことも見落とせない。以前は、そうした障害が原因でコストが増大していた。
第3は、途方もない数のAI関連のプロジェクトが登場しているが、成功を収める企業は、小さなリスクで好ましい結果を生み出せるプロジェクトを見出し、それを実行に移すことに長けているということだ。
筆者らの研究により、これらの現象の根底にある4つの要因が見えてきた。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









