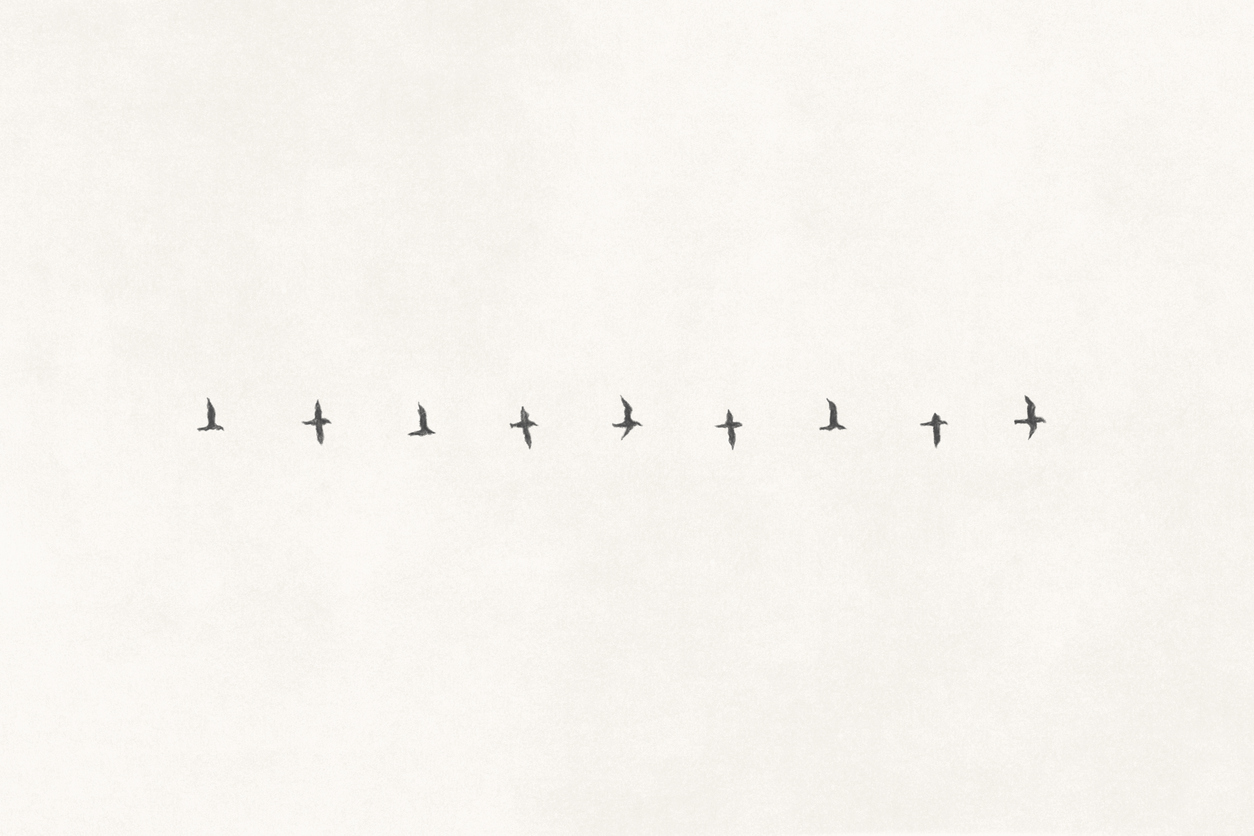
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
業種や規模を問わず共通する基本的なプロセス
経営システムを構成する基本的な経営プロセスとは何だろうか。どんな業種、どんな規模の会社も、次の14のプロセスから経営システムを組み立てることができる。
・経営理念を打ち出す
信念、価値観、会社としての姿勢など骨太な、しっかりした方向性を確立する。こうしたものを「我々のやり方」として定着させていく。
・経営目標を設定する
会社全体または事業部が何をするのかを決め、その事業で目指すものを定める。経営目標は、時代や流行に左右されない不変の価値を持つものが望ましい。
・到達目標を設定する
経営目標という大きな目標に対して、期限あるいは範囲を狭めた具体的な数値目標を定める。この到達目標を達成するために、戦略を立て計画を立案する。
・戦略を立案する
経営目標を達成し競争に打ち勝つためのアイデアを練り、計画を立てる。戦略立案は計画立案プロセスの一部であり、このプロセスにはほかに中期的な事業計画、単年度の業務計画が含まれる。
・行動方針を定める
経営理念の下で戦略を実行する時に、あらゆるレベルの具体的な行動指針となるべきものを定める。
・基準を設定する
経営目標の達成に向けて参照すべき業務基準や評価基準を設定する。
・手順を定める
重要な仕事や反復的な作業をどう進めるかについて決まりをつくる。
・組織計画を立てる
組織の設計図を引く。経営理念の下で戦略、方針に従って行動する時に、社員の力を一つにする役割を果たすのが組織である。
・人材を配置する
人材を募集・選抜・養成し、組織図に用意されたポストを満たす。この時、幹部候補を適切な比率で確保する。
・事業計画・業務計画を練る
経営資源の配分や業務の進め方に関する計画を策定する。事業計画・業務計画は到達目標の達成を目指し、定められた戦略の下で行動方針・基準・手順に従って実行する。事業計画・業務計画の立案は、戦略計画から始まる一連の計画立案プロセスの一環である。
・施設設備を用意する
事業の遂行に必要な工場、設備などの施設を用意する。
・資金を手配する
施設の建設や運転資金に必要な資金を手配する。
・社員に情報を提供する
社員に事実や具体的な数値などの情報を提供する。こうした情報があれば戦略も行動方針も遂行しやすい。また事業環境に働く外部要因の予測や業績評価にも役立つ。
・社員に行動を促す
計画の実行局面で、経営理念に従い方針・基準・手順に基づいた行動を促す。
14のプロセスを自社に合わせた経営システムとしてまとめ上げるのが、CEOを筆頭とする経営幹部の仕事である。そして経営システムを浸透させ、守り、守らせるのは業務面の仕事であり、上はCEOから下は現場主任まであらゆるマネジャーがしなければならない。これが経営の基本である。
基本に忠実であることの大切さは、チームワークが大切な集団行動を見るとよくわかる。たとえば1964年のNFL決勝戦はその好例と言えるだろう。戦前の予想ではボルチモア・コルツが圧倒的に有利だったが、いざフタを開けてみるとクリーブランド・ブラウンズが27対0で圧勝した。理由を聞かれたコーチのブラントン・コリアは「基本に立ち返っただけさ」と答えている。試合前の2週間、フットボールの基本をみっちりやらせたというのだ。シーズンを終えたばかりのプロ選手に、である。実業界でも、「チャンピオン」と呼ばれる企業はやはり基本に忠実だ。
とは言えいくら基本に立ち返っても、実際に活用しなければ役に立たない。クリーブランド・ブラウンズが2週間かけて練習しなおした基本にしても、試合で使わなければ勝てなかっただろう。企業経営に基本を適用することの大切さは、GMの会長を務めたフレデリック G. ドナーの言葉にもよく表れている。1965年、GMは売上高2070億ドルに対し利益が20億ドルを上回った。この素晴らしい業績が発表された直後の会見で、ドナーは次のように語っている。
「原則、方針、手順などの基本は、会社の経営陣が十分理解し毎日の業務と適切に結びつけて初めて効果を発揮する。つまり基本の実践が成功の鍵であり、その成否は最後に業績として表れるのだ。GMの業績が我々のやり方の正しさを証明してくれると私は信じている[注1]」
ドナーが「成功のカギ」と言った基本の実践を助けるのが、システムによる経営にほかならない。
事業の成功を測る物差し
経営システムの確立が望ましいのは、事業を成功に導く助けとなるからである。となればここで、事業の成功とは何かを確認しておかねばなるまい。事業の成功は、次の3つの基準で測るのが適切と私は考えている。
(1) 売上高とシェアの拡大
売上高が毎年伸びているか。製品またはサービスのシェアが安定して拡大しているか。この2点は、競争優位を測る物差しとなる。
(2) 長期的な投資利益率
収益性を測る基準はさまざまだが、投資利益率(本書では営業利益/総資産を使用)は株主、従業員、ひいては社会経済の利益を最もよく反映する。
(3) 経営の継続性
事業の繁栄を持続できるような経営者を次々に輩出できる会社こそ、成功企業の名にふさわしい。
事業の成功を測る物差しはほかにもある。たとえば製品のラインアップ、社員の能力、世間的な評判、社会的責任などだ。だが売上高とシェアを増やし、長期的な投資利益率を高め、優秀な経営幹部が次々に出てくる会社は、自ずと他の基準もクリアすることになる──これが、成功企業を数多く見てきた私の確信である。
また、成功企業は柔軟であることも付け加えておきたい。事業環境への適応、先進的な製造プロセスの導入、コスト削減、最新の経営手法の活用を、経営幹部は常に心がけるべきであろう。経営システムが機能している企業は変革の必要性を察知しやすく、環境の変化に素早く対応できるし、進んだ経営手法を採用しシステムに組み込むことも容易にできる。システムがしっかりしていれば、むやみに新しいものに偏らず、バランスよく新しい技術や手法が取り込まれていく。
【注】
1)Frederic G. Donner, "The Development of an Overseas Operating Policy," McKinsey Foundation Lectures, Columbia University, April 28, 1966.
[著者]マービン・バウワー
[監訳]平野正雄[翻訳]村井章子
[内容紹介]経営とは何か。いかにすれば企業は成長するか。経営の原点とも言える根源的な問いに、今日のマッキンゼーを築いたバウワーが、それは「経営の意思」だと明解に答える。世界最高のコンサルティングファームを築いた男が1966年に書き残した伝説の経営書The Will to Manage の翻訳。時代の変遷を超え、いまなお通用する経営の真髄がここにある。
[目次]
監訳者まえがき
序章
第1章 経営の意思──意志あるところ道あり
第2章 経営理念──これが我々のやり方だ
第3章 戦略──我々はこの道を進み、こう戦う
第4章 行動方針・基準・手順──行動と戦略を結びつける
第5章 組織──人々を束ね、力を発揮させる
第6章 経営幹部──会社の宝を育てる
第7章 事業計画・業務計画とコントロール・システム──道順を決めるシグナルを設置する
第8章 計画から実行へ──社員を動かす
巻末注






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









