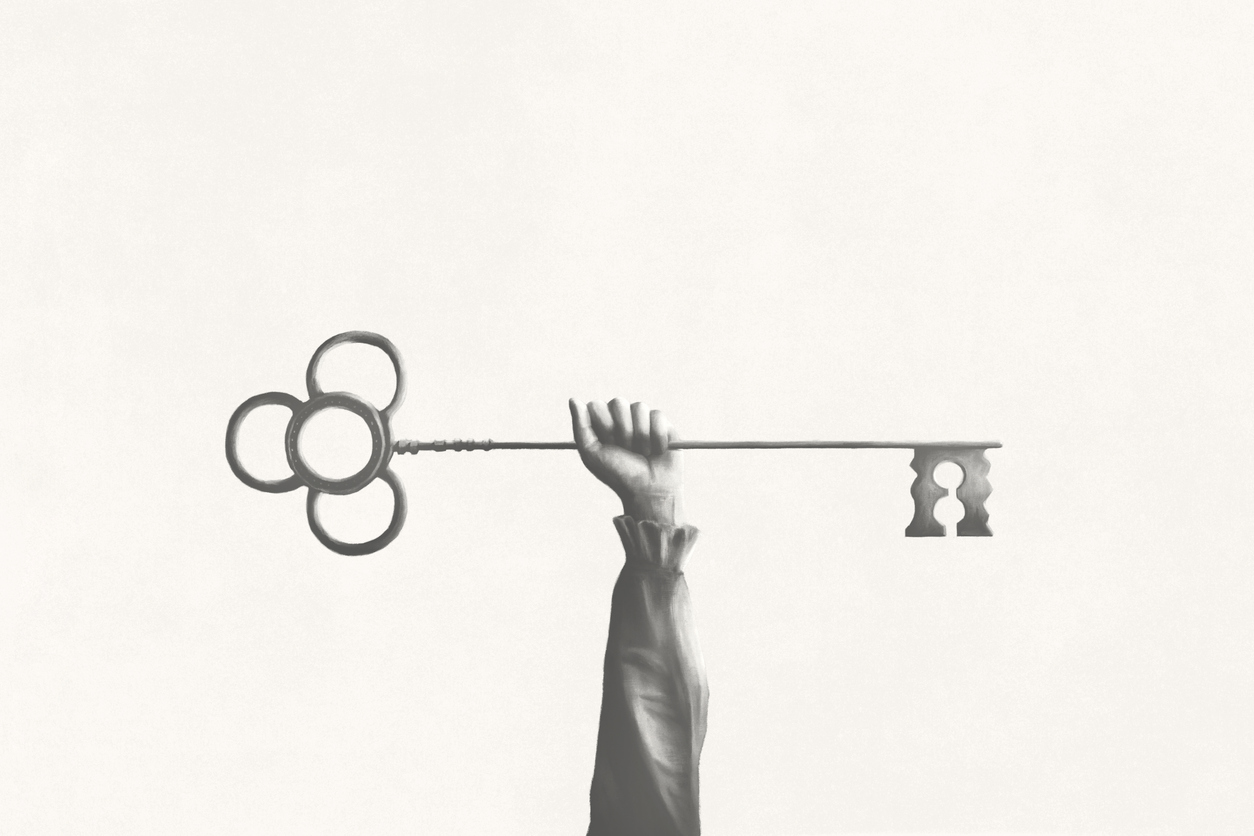
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
経営理念を掲げる
企業理念とは自然発生的に生まれるのを待つのではなく自ら掲げるべきものだという考えから、第5回では成功している企業に共通する5つの要素を選んで紹介した。ここで紹介した例は、どんな企業にとっても健全な土台となるものである。これらの理念に、それぞれの組織にふさわしい信条をつけ加えてはどうだろうか。単なるガイドラインを超えた普遍的な信念を選ぶのだ。
とりたてて努力をしなくても、どの企業にも徐々に基本的な考え方は生まれてくる。社員が試行錯誤して「我々のやり方」を見つけ、学んでいくからだ。だが経営トップが自ら進んで健全な経営理念を打ち立てるなら、それは経営システムの礎となり、あらゆるものに影響を与える思想となるだろう。
会社としてどんな理念を掲げるにせよ、社内にあまねく根づかせるためには、経営トップが行動で示すべきことは言うまでもない。だが理念が実際に生かされるためには、経営幹部のお手本以上の何かが必要だ。経営幹部が理念を絶えず強調し、現実に直面している問題を経営理念に照らして考えること。どんな行動が会社の信条に一致しどんな行動は反するのかを部下に教えること。上に立つ人のこうした実践や指導を通じて、経営理念はより堅固なものとなる。
1961年のある日曜日。私はロンドンから帰ってきたばかりの同僚と食事をしていた。彼がイギリスで最高に感激したのは、どうやらステンレス製の剃刀だったらしい。その刃がいかに鋭くいかに長持ちするかをひとしきり喋った後、彼はウィルキンソンの剃刀をポケットから取り出し、試してみるようしつこく勧めた。私は従った。──そしてさんざん聞かされた誉め言葉でもまだ足りないと思ったものだ。
その数週間後、私はロンドンに行き、薬局でウィルキンソンの剃刀を買おうとした。ところが「あいにく品切れでございまして」と慇懃無礼に断られてしまった。常連客でさえ滅多に買えないのだ。ロンドンの事務所長など、どこかで見つからないか秘書に薬局回りをさせるという。
ウィルキンソンの剃刀はなぜこれほど成功したのだろう。それは使った人がこぞって抜きん出た品質を認めたから、需要が供給を上回ったのだ。以来、このサクセス・ストーリーは語り種となっている。業界の巨人ジレットに挑んで勝利を収めた新参のウィルキンソンは、もはや伝説的存在と言えるだろう。ウィルキンソンのように鮮やかに狙いを定め競争力を磨くにはどうすればいいのか。事業の針路と重点競争分野を決める作業は、どんな企業でもまず戦略を立てることから始まる。
計画立案プロセスとは
戦略の立案は、実は全社の計画立案プロセスの一段階に過ぎない。そこでまず、プロセス全体について考えてみよう。ごく普通の言葉で言うなら、計画を立てるとは心を決めることである。何をどんなふうに実現するのか、どんな日程でどれくらい費用をかけるか、などを決めることだ。おそらくだれもが毎日の生活のなかでそうした決定を下しているだろう。
人間は大昔からずっと、自分の生活環境に働く力を理解しようと努力してきた。こうして得られた知識の助けを借りて、自分にとって不利な力から身を守り、有利な力を利用するのだ。この意味で、人間は自らの環境に作用する力を理解し対処できる範囲に限れば、自らの運命を自ら選び取ることができる。もしも運命の大きな力に身を任せてしまうと、挫折と無力感を味わうだろう。
同じことが、企業の計画立案にも当てはまる。経営者は事業を運任せにしてしまうこともできれば、信頼度の高い経営手法を適用し、自らの命運を自ら制することも可能だ。とは言え会社の将来に関わる決断を下すのはきわめて複雑な作業である。いくつもの経営資源が絡む決断には多くの人間が介在し、計画の実行にもたくさんの社員が関わる。したがって事業環境を評価し対応策を計画するにあたっては、何らかの手順が決まっていることが望ましい。
事業は行動を伴い、行動は計画を必要とする。計画立案の手順が決まっていない場合、日々の仕事に追われながら、よく考えもせず大あわてで計画を立てることになってしまう。これでは業務上の決定を下すのと変わらない。会社全体の計画が組織的に立案されず社員に正確に伝えられない場合、各部門の責任者は、会社の目標や戦略を自分なりに解釈して部下に指示せざるを得ない。こんな調子でいろいろな決定が下され、それが積み重なって会社あるいは事業部の計画になる。実際、たいていの会社はこんな具合に経営され、それで何とかやっている。
私が見てきた限りでは、大半の企業で計画立案が経営プロセスとして十分に確立されていない。実は計画立案はいまなお経営学の未知の領域の一つである。注目されるようになったのはごく最近のことに過ぎず、標準的な手法もまだ確立されていない。したがって計画立案についてこれからお話しすることは、主に私自身や同僚の考え、経験に基づくものであることをお断りしておく。
個人が計画を立てる時と、企業の経営者が計画を立てるときの類似点をもう少し考えてみよう。自分の将来を決めようとするとき、たいていの人が両親や先生、妻(または夫)、友人にアドバイスを求めるだろう。だが最後に決めるのは自分自身である。ビジネスでも同じだ。たとえば事業部長はスタッフ、部下、コンサルタントなどから意見を聞くことはある。だが最終的には事業部長自身が決断を下さなければならない。計画立案スタッフは彼を助けることができ、またそうしなければならないが、最終的な決断の責任は事業部長の双肩にかかっている。
企業では、製品別・サービス別の事業ごとに計画を立てる。それとは別に、会社全体の計画も必要だ。つまり計画立案プロセスとは、事業単位、そして会社全体のための計画を立てるプロセスである。本書で取り上げる計画立案プロセスでは、会社の経営幹部と各事業部の長が定期的に集まって会社全体と事業部の計画を話し合う機会を持つ。これがこのプロセスの最大のメリットと言えるだろう。そこでは問題点と機会の両方について、さまざまな観点から自由な発想で話し合う。
このような計画立案の意義について、大手化学品メーカー、セラニーズ・コーポレーションで会長を務めたハロルド・ブランケは次のように話している。
「今日の企業経営では計画立案がきわめて重要であり、優れた経営者はそのために多くの時間を費やしている。セラニーズも例外ではない。計画を立てるからこそ、変革が可能になるのだ。計画を立てるためには予想を立て、実行手段を練らなければならない。計画立案は、優れた発想や価値を引き出し成長のための最善の方法を見つける最も効率的な手段である。
長期的な視点に立った計画のおかげで、セラニーズは主要事業を国際展開した初の化学品メーカーとなった。わずか一年足らずで3つもの新たな関連分野に進出し、1965年の売上高は61年の2.5倍にも達している。
計画は成長を支える知の柱であり、計画立案は未来へのプロローグだ。計画立案はごく少数の人間が独占するのではなく、組織にいる全員の仕事である。セラニーズの繁栄の道案内をするのが計画である。緻密な計画は、セラニーズの未来を支える重要な柱の一つなのである[注1]」
計画立案の3段階
企業における計画立案のプロセスは連続的なものだ。まず大きな経営目標を定め、次に経営目標を目指す過程で節目とすべき到達目標を設定する。続いて到達目標を達成するための戦略を立て、戦略を実行に移す事業計画を策定する。さらに事業計画を単年度の詳細な業務計画に落とし込む。計画立案という作業の性質から言って、これらのプロセスを分割して取り扱うのは難しい。ちょうど色のスペクトルと同じように、あるプロセスは次のプロセスに溶け込んでいる。一つのプロセスだけを取り出そうとするのは、赤がオレンジに変わるポイントを見つけようとするようなものだ。
こうした事情から、計画立案を便宜上いくつかの段階に分割する場合、分け方は会社によって違ってくると考えられる。ともあれ社員全員に関わってくるプロセスだから、社内でコミュニケーションが取りやすいよう、単純明快な手順を決めておくことが望ましい。計画立案の手順は、わかりやすいガイドブックかマニュアルのかたちで文書化しておくといいだろう。
計画立案のプロセスを論じるに当たっては、手続き的なことに深く立ち入るつもりはない。まず最初に計画立案プロセスを簡単に説明し、用語の解説をする。その後はケーススタディを通じて、実際にどのように活用されているのか紹介していこう。計画立案プロセスをいかに分割しどんな手順で進めるかは、それぞれの企業がやりやすいかたちで決めるのが一番である。
ちなみに私の経験に照らすと、次の3段階に分割するのがわかりやすく運用しやすいように思う。
戦略計画(第3章にて詳述する)
事業計画(第7章にて詳述する)
業務計画(第7章にて詳述する)
本書『マッキンゼー 経営の本質』第7章でも述べるが、事業計画と業務計画は同時に立てることが多い。色のスペクトルと同じで、両者は重なり合っているからである。だがこの2つを2段階に分けて取り組むほうがよい結果が出ると、私は考えている--実際には相当部分を渾然一体と進めることになるかもしれないが。
また戦略計画と事業計画は同じ情報を根拠にして立てることができるが、戦略計画には特に力を注ぐべきだろう。本書で戦略計画を先に取り上げ、事業計画・業務計画を第7章で扱う構成にしたのも、持続的な成長と利益の拡大には戦略がきわめて大切と考えるからである。
* * *
本連載は今回で最終回である。計画立案以降の戦略の考え方、行動指針や組織づくり等、バウワーならではの経営の真髄をぜひ書籍『マッキンゼー 経営の本質』で確認していただきたい。
【注】
1)Celanese World, January, 1966.
[著者]マービン・バウワー
[監訳]平野正雄[翻訳]村井章子
[内容紹介]経営とは何か。いかにすれば企業は成長するか。経営の原点とも言える根源的な問いに、今日のマッキンゼーを築いたバウワーが、それは「経営の意思」だと明解に答える。世界最高のコンサルティングファームを築いた男が1966年に書き残した伝説の経営書The Will to Manage の翻訳。時代の変遷を超え、いまなお通用する経営の真髄がここにある。
[目次]
監訳者まえがき
序章
第1章 経営の意思──意志あるところ道あり
第2章 経営理念──これが我々のやり方だ
第3章 戦略──我々はこの道を進み、こう戦う
第4章 行動方針・基準・手順──行動と戦略を結びつける
第5章 組織──人々を束ね、力を発揮させる
第6章 経営幹部──会社の宝を育てる
第7章 事業計画・業務計画とコントロール・システム──道順を決めるシグナルを設置する
第8章 計画から実行へ──社員を動かす
巻末注






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









