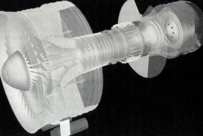-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
軍隊経験のある取締役から学ぶCEOの説明責任
企業の業績が悪化すると、すべての目がCEOに向けられる。株主は結果を求め、従業員は指示を仰ぎ、社内にいるライバルは弱点を分析してトップの座に就くための準備を始める。CEOは問題を解決できなければ、解任を強く期待されることになる。だが、取締役会は別だ。大胆で毅然とした手段を取ることに尻込みし、重大な問題を避けた議論を延々と続けるケースがしばしばある。業績の低迷が続いても、長期間、CEOを留任させる取締役会は少なくない。
最近のボーイングの例を考えてみよう。世間に知られた数々の失態を犯したにもかかわらず、デーブ・カルフーンは業績悪化が4年以上続く中でCEOの職に留まり続けた。同様に、IBMのジニー・ロメッティはCEOを退任するまでのおよそ10年間、収益の減少と株価低迷が続いても同社を率い続けた。またゼネラル・エレクトリック(GE)のジェフ・イメルトは株価が急落し、多くの事業の財務安定性が低下したにもかかわらず、16年間トップの座に居座った。そのため後継者は、事業を再生するのに数年を要し、会社を分割するに至った。
こうした事例は、けっして珍しくない。それどころか、ある研究によると、企業の業績が低迷している時にCEOが解任されることは稀だ。CEOは取締役会に対して相当な力を振るうことができる。特にCEOがかなりの持ち株を保有している場合がそうだ。この影響力は、CEOと特に親しい関係にある取締役や、CEOによって任命されたために忠誠心を持つ取締役によって、さらに強化されるおそれがある。ここで、重要な問いが浮かび上がる。業績が低迷した時、取締役会はどうすればCEOにより効果的に説明責任を取らせることができるのだろうか。
最近、筆者らは大規模な定量的研究プロジェクトで、米国の上場製造企業865社の2010年から2020年までの取締役会を分析した。研究結果は、説明責任の原則として見落とされがちな源泉を指し示していた。それは軍隊である。サンプル企業の取締役会の約4分の1には軍出身の取締役が少なくとも一人含まれ、複数含まれる企業もあった。軍出身の取締役は、防衛産業に多く存在すると考えられるが、幅広い業界に存在していた。軍隊経験のある取締役がいる取締役会は、業績低迷を招いたCEOに毅然とした態度で臨み、必要ならばCEOを解任することも少なくなかった。
筆者らの考えでは、このアプローチは現代的なコーポレートガバナンスの要求とぴたりと一致する。それでは取締役会は、CEOの説明責任について軍隊経験のある取締役から何を学べるのだろうか。
3つの教訓
この問いに答えを出すために、筆者らは30人以上の取締役にインタビューした。彼らが取締役を務めた上場企業を合計すると、約50社になる。そしてインタビューからエッセンスを取り出し、CEOの説明責任の強化を望むすべての取締役会のために、3つの実践的教訓を導き出した。
責任を明確にする
取締役会がCEOの責任を曖昧に定義しているため、たとえ成功の原因が運や市場の発展、ライバルの失策、あるいは部下の努力だったとしても、CEOが自分の手柄にしてしまうことがあまりに多い。そして、そうしたCEOは業績目標が達成されないと、それを他人や外的環境のせいにして失敗の説明責任から逃れることがよくある。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)