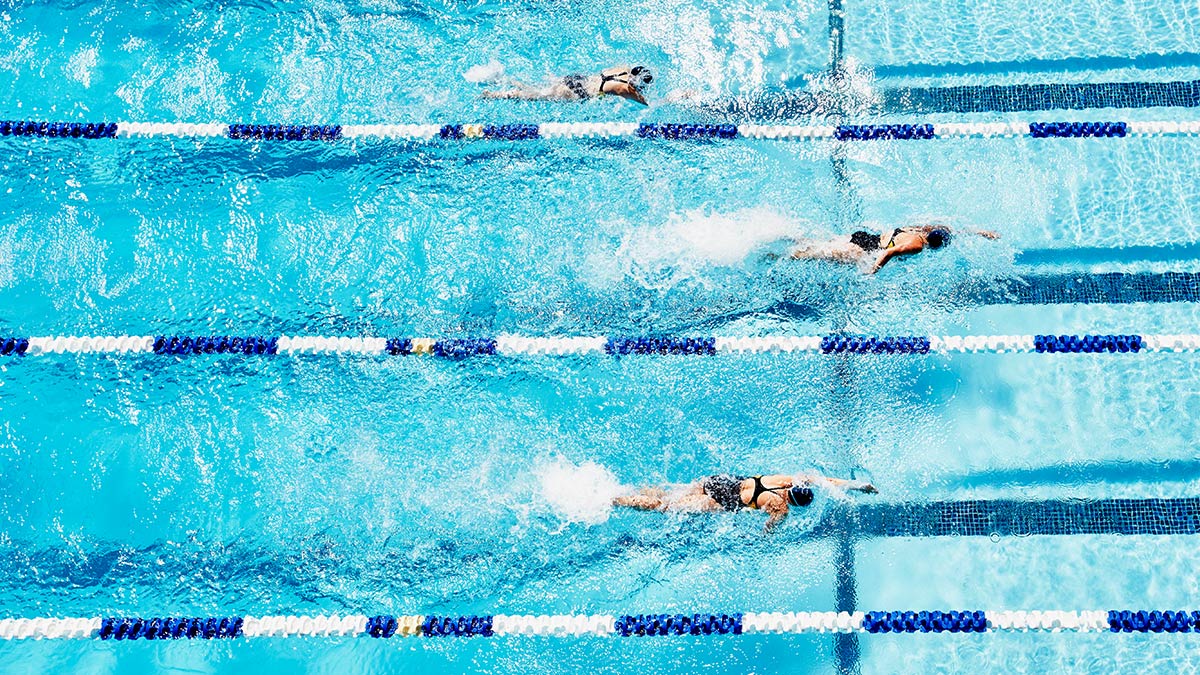
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
サイロ化は漠然とした対処では解決できない
いわゆる「サイロ現象」──企業内の部署間でコミュニケーションが不足している状況──は、昔から多くの企業を悩ませてきた問題だ。この現象がもたらす弊害の大きさを明らかにした研究はいくつもある。
セールスフォースの調査によると、顧客体験の担当者および担当幹部の70%は、質の高い顧客サービスを実現するうえで最大の障壁になっているのがサイロ現象だと考えている。また、ハーバード・ビジネス・レビュー・アナリティクス・サービスの2017年の調査によると、部署間のコラボレーションが失敗するケースの67%はサイロ現象が原因だという。
こうしたことは、最近始まった問題ではない。たとえば、2002年の米国マネジメント協会の調査によると、企業幹部の83%は、自社内にサイロが存在していると認識しており、そのうち97%は、それが会社に悪影響を及ぼしていると述べている。
これらの調査結果が浮き彫りにしているように、サイロ現象は、企業がオペレーションの質を向上させ、コラボレーションの成果を高めるうえで対処しなくてはならない重要課題なのだ。
筆者らは、企業のトレーナーおよびコンサルタントとして、アジア、南米、アフリカ、そして米国の何百社もの企業と関わってきた。その経験を通じて、サイロ現象の実例を多く目の当たりにしてきた。
企業は、社内のサイロを取り除くために膨大な量のリソースを費やして、さまざまな対策を実行している。部署横断型のチームを設けたり、コラボレーションを後押しするテクノロジーを導入したり、全社規模でアップスキリングに取り組んだり、といったことだ。しかし、多くの場合、思うような成果は上がっていない。成果が上がらないのは、企業が異なるタイプのサイロ現象を一緒くたに考えて、さまざまな解決策の寄せ集めによって対処しようとすることが原因だ。
筆者らのこれまでの経験と研究からいうと、サイロ現象と呼ばれているものは、深層レベルのさまざまな根本原因が表面化した現象と見るべきだ。一口にサイロ現象と言っても、根本原因が異なれば、有効な解決策も異なる。社内のサイロを完全に打ち壊すためには、自社が直面しているサイロに適したツールを用いる必要があるのだ。
本稿では、3つの架空の企業を例に、サイロを解体するための洗練されたアプローチを紹介する。「システム型サイロ」「エリート型サイロ」「防衛型サイロ」というタイプごとに、どのような戦略が求められるのかを説明したい。目指すべきなのは、漫然とサイロに挑むのではなく、もっと標的を絞り、根本原因に応じた戦い方をするように発想を転換することだ。そのために、筆者らの専門知識を駆使して、より持続可能性があり、効果的なソリューションを示す。
サイロ現象の根本原因を診断する
3つのタイプのサイロの違いをより深く理解するために、以下では3つの企業の例を用いて話を進める。これらは、筆者らが実際に関わってきた企業の経験を集約した架空の企業だ。それぞれを「目標バラバラ飲料」社、「エリート主義製薬」社、「自己防衛志向部品」社と呼ぶことにしよう。この3つの例は、業種を問わずよく見られるサイロのパターンを描き出している。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









