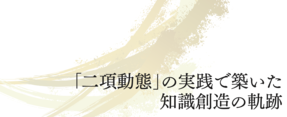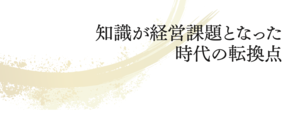-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
*本稿の初出は、Harvard Business Review, November-December 1991(邦訳『DIAMONDハーバード・ビジネス』〈DHB〉1992年3月号)であるが、DHB1999年9月号の「ナレッジ・マネジメント」特集の際に新訳を施し、再掲載した。今回の追悼特集においてはこの1999年の翻訳を再掲載している。
企業はマシンではない
「有機体」がゆえに知識がエネルギーとなる
不確実性の存在のみが確実にわかっている経済下において、永続的な競争優位の源泉の一つとして、企業が信ずべきものは「知識」だ。大きく変化する市場、多様化する技術、重層化する競争、そして急速に陳腐化する製品。このような状況下で成功する企業とは、新たな知識をたゆまず創造し、それを組織に広く浸透させ、新技術や新製品にスピーディに具現化できるところである。これらの企業の行動から「知識創造企業」(ナレッジ・クリエイティング・カンパニー)という姿がくっきりと浮かび上がる。そこでは、イノベーションをたえず生み出すことがその務めである。
しかし、「脳力」や「知識資本」に関する話題があまねく広まっているにもかかわらず、ほとんどの経営者が、企業が知識を創造することの本質を把握できていない。ましてや、そのマネジメントの方法については言うまでもない。その理由は、「知識とは何か」「そのために企業は何をすべきか」について、誤解していることにある。
フレデリック・テイラーからハーバート・サイモンに至るまで、欧米のマネジメント観には、「組織とは“情報処理”マシンである」という伝統が深く浸透している。このような観点に立つ限り、唯一有効な知識とは、形式的で体系立ったもの、すなわち、定量的なデータや規則化された手続き、普遍的原理ということになる。それゆえ、新たな知識の価値を測る物差しも、効率性やコスト、ROI(投資利益率)など、同じく定量的である。
知識そのもの、そして企業組織における知識の役割については、別の考え方がある。それは、本田技研工業(ホンダ)やキヤノン、松下電器(現パナソニック)、日本電気(NEC)、シャープ、そして花王など、非常に成功した日本企業に共通して見出すことができる。これらの企業は、顧客への迅速な対応、市場の創造、短いリードタイムでの新製品開発、新技術による優位性などによって注目されるようになった。その秘密とは、知識創造のマネジメントに対するユニークなアプローチにある。
欧米の経営者にとって、これら日本企業のアプローチはしばしば奇妙に、時には理解しがたいものに見える。次のような事例に考えをめぐらせてみてほしい。
・「クルマ進化論」というスローガンは、新しい自動車を開発するうえで、しかるべき意義を持った設計コンセプトたりうるのだろうか。実はこの標語こそ、ホンダの革新的都市型自動車、ホンダ・シティを開発させる端緒となった。
・ビール缶がパーソナル複写機の開発にとって有効なアナロジー(比喩)となる理由は何か。このただ一つのアナロジーがキヤノンの革命的製品、ミニコピアの設計にブレークスルーを起こす引き金となった。そして、この製品はパーソナル複写機市場を創造し、キヤノンは停滞していたカメラ事業から、より高収益なオフィスオートメーション(OA)分野への移行に成功した。