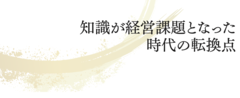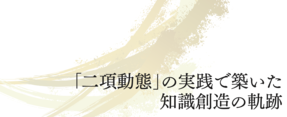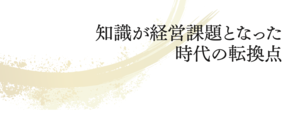-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
野性味あふれる生き方
野中さんと私の出会いは1970年に遡る。カリフォルニア大学バークレー校にMBAを取得するために留学した際、当時、博士課程4年目の野中さんと出会った。もう55年も前のことになるが、その時の縁がなければ、間違いなくいまの私はない。
夫人の幸子さんのカレーや餃子といった手料理に惹かれ、よくお宅にお邪魔し、野中さんの話を聞いた。ただ、食事目当てだった私にとって、正直なところ興味の湧くものではなかった。大東亜戦争やワイン、そしてクラシック音楽の話。戦後生まれで下戸、演歌好きの私とは、興味や関心が正反対だ。いつも最後には学問の話題に移ったが、MBAを取得後はコンサルタントになるつもりでいた私には、話が右から左へ流れるばかりだった。
しかし、就職の話が立ち消えになった時、博士課程に残れるように計ってくださったのが他ならぬ野中さんだった。成績があまり振るわなかった私のために、いろいろ手を尽くしてくれたのだと思う。野中さんは何度聞いても、最後までそれを認めようとはしなかったのだが。
私たちは興味や考え方だけでなく、育った環境も大きく違っていた。野中さんは公立校を経て早稲田大学に進学し、富士電機に就職。一方、私はインターナショナルスクール出身で国際基督教大学に進学し、広告代理店に入社した。対照的な道を歩んできた私たちだが、共通点もある。一つは親が商いをしており、その精神を叩き込まれていたこと。次に軍歌が好きだったこと。そして、お互いに「脱優等生」であろうとしたことだ。
野中さんが「脱優等生」と言うと意外に思われるかもしれないが、私からすればその生き方は野性味にあふれ、まるで野武士のようだった。エリート街道を進んできたにもかかわらず、そのすべてを捨て、ハワイ経由の貨客船でカリフォルニアに留学。ワインを飲むと、べらんめえ調で本音を語ってしまうチャーミングさもある。こうした型破りな日本人がいることに驚き、強い憧れを抱いた。
知的コンバットの日々
野中さんは私のことを「ロジカル」だと評してくれた一方、自身については「勘で動くタイプ」だと語っていた。ただ、実際には野中さんは理論の構築を重視し、私は実践的な物の見方をする傾向があったと思う。そうした異なるスタンスの中で協働することが増えていき、共著論文や書籍も数多く執筆した。