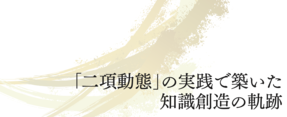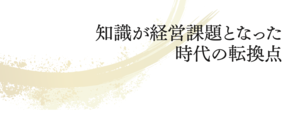-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
異なる大陸、異なる文化でほぼ同時に達した結論
野中郁次郎教授の画期的な論文「ナレッジ・クリエイティング・カンパニー[注1]」は1991年に『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)に掲載された。野中教授がこの論文に取り組んでいたまさに同じ時期に、私は米国で『フォーチュン』向けに知的資本について一連の記事を執筆しているところだった。
その前年には、C. K. プラハラッドとゲイリー・ハメルがHBR誌上でかの有名な論文「コア・コンピタンス経営[注2]」を発表し、さらにその1年前には、スウェーデンの証券アナリストであるカール・エリック・スビービー、エリサベト・アネル、コンラッド・アーベッツグルッペンが、その研究論文"The Invisible Balance Sheet"の中で、情報化時代の企業価値は帳簿上の資産ではなく、無形資産によって説明できることを示した。
異なる大陸に住み、異なるビジネス文化の中で、おそらく互いに面識もなかった見知らぬ者同士の我々が、ほぼ同時に同じ結論に達していたのだ。野中教授が書いたように、唯一確かなことは不確実性だけという経済下において、永続的な競争優位の源泉として確実なものは「知識」(ナレッジ)である、と。
それから数年後、経営者の間で、またビジネス思考の一つとして、瞬く間に知識が重要な経営課題──知識アジェンダ──と見なされるようになった。米国でこのアジェンダが取り上げられる時には、ナレッジマネジメントの技術とともに、組織設計の劇的な変化が強調されていた。これは1990年代のITブームと、アイデアを製品化する米国人気質の産物といえる。一方、懐疑的で慎重な欧州人は、持続可能な優位性の源泉としての知的資本をより重視していた。
そして、野中教授に代表される日本人が考えたのは、調和、形式、美という文化的な価値観に合った知識アジェンダを展開することだ。そこでは、人々が安心して自分の無知をさらけ出し、アイデアを試し、成功を分かち合うためのコミットメントを再確認できる、物理的で形而上学的な場所──野中教授の言う「場」の創造に重きが置かれた。