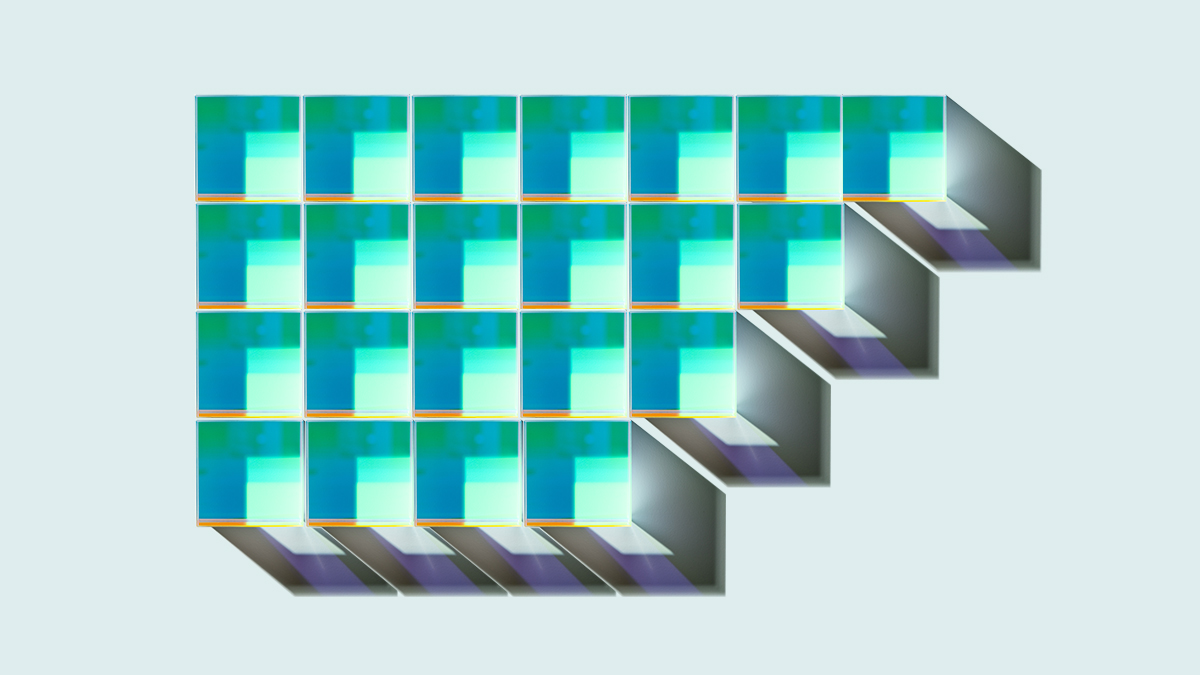
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
SAPの取り組みからAI導入を成功させる方法を学ぶ
企業は生成AIと大規模言語モデル(LLM)に何十億ドルも投資してきた。いまでは最高AI責任者を設けている企業もある。だが投じられる資金や大きな話題性とは裏腹に、ビジネス成果を生み出すことが依然として難しいのは明らかだ。
2024年5月、マッキンゼー・アンド・カンパニーは、記事の中で「生成AIのハネムーン期は終わった」と述べた。同8月にガートナーは、生成AIは同社提唱の「新興技術のハイプサイクル」を進み、「幻滅の谷」へと急速に落ち込んでいると発表した。2025年1月、14カ国2770人の企業幹部を対象とするデロイトの調査で、組織は生成AIへの取り組みの価値を実証すべく依然奮闘中であることが示された。そして2月に『フィナンシャル・タイムズ』紙は、「生成AIは素晴らしいが、利益を生めるのだろうか」と疑問を呈した。
しかし、生成AIが企業に価値をもたらすことは可能だ。本稿では、統合基幹業務システム(ERP)ソフトウェアの最大手であるSAPのケーススタディを用いて、営業部門にAIを実装するためのフレームワークを提示する。熟慮に基づいてAIを拡大することで、大企業は数十億ドルもの収益を生み出せる可能性があると実証することが筆者らの狙いだ。
市場動向を把握する
ビジネスにおける価値は、顧客のいる市場において創造されたり、毀損されたりする。「AI戦略」から始めるのではなく、まずは自社が事業を成長させるためにどの問題を解決したいのか、またはどのような機会を得たいのかを明確にしなければならない。そのうえで初めて、AIやその他のツールがどう役立つのかを考えるべきだ。新しいテクノロジーが人気を集めると、企業は往々にしてそれを導入しなければというプレッシャーを感じる。このことが、投資を正当化するためにユースケースを探すという本末転倒を招いてしまう。
SAPはまず、市場動向が自社の事業に及ぼす影響を調べることから始めた。顧客がオンプレミス型のソフトウェアからクラウドに移行するにつれて、同社は事業をサブスクリプションモデルへと進化させる必要に迫られ、2007年に同社初のクラウド型のSaaSソリューションをリリース。2024年には収益の半分以上をクラウドサービスから生むようになっていた。
クラウドへの移行は、3000万~4000万社に及ぶ中小企業にリーチする機会ももたらした。サブスクリプションモデルは中小企業の初期費用を削減し、柔軟性と拡張性を提供する。またクラウドサービスによって、自社のソフトウェアをカスタマイズして配布する機会が増える。
しかしながら、同社はこれらの顧客の市場を開拓するうえで、ブランドとコストの壁に依然直面していた。中小の顧客企業の多くは、SAPを大企業向けのソリューションと見なした。断片的な中小企業市場における小規模な注文に対しては、SAPのエンタープライズ顧客向けの対面式コンサルティング営業ではコストがあまりに高く、12~18カ月の営業サイクルも長すぎた。より小規模な企業に売り込むための効率的なアプローチをSAPは必要としていた。
ビジネスプロセスをマップ化する
自社のビジネスニーズの変化を把握したら、新たな環境におけるビジネス遂行のプロセスをマップ化する必要がある。最初にカスタマージャーニーから取りかかる。これは、サービス提供コストやオペレーションといったもろもろのビジネス要素に影響するためだ。このマップ化は、AIやその他のテクノロジーが役立ちうる部分も含め、拡大可能な投資対象を優先するためにも不可欠である。
SAPはカスタマージャーニーを5段階にマップ化した。中小の顧客企業がどのようにSAPの一連のソリューションを発見し、特定のソリューションを選択し、それを自社に導入し、そこから価値を導出し、自社とSAPの関係を発展させるかを示したものである。購入金額が少ない小規模な顧客には、対面営業モデルは経済的に採算が合わないことをSAPは認識していたため、各ステージでAIツールを使って顧客を支援する方法を模索した。
同社は現在、カスタマージャーニー全体を通して中小企業を支援するために、「デジタルモダリティ」と呼ぶ40以上のAIツール群を用いている。
・発見(Discover):ここでの目標は中小企業に対し、ビジネスニーズに見合ったSAPのソリューションを探索するよう促すことだ。
AIツールの「デジタルローンチパッド」はデータベースと接続し、業界ごとに分類されパーソナライズされた没入型の顧客アウトリーチ活動を数分で作成する。「プロスペクティング・アシスタント」は、さまざまな情報源からリストをアップロードして見込み客の質を分析する。
感情分析を行うAIツールはそれらの見込み客の好み、たとえばどのようなインタラクションの方法を好むかなどを特定する。キャンペーン自動化ツールはその情報を取り込み、見込み客が好むトーン、フォーマット、スタイルでカスタマイズされたメッセージを作成する。リンクトインのメッセージ、メール、あるいは複数言語で話す実在の幹部の人型アバターによる動画メッセージなどだ。
・選択(Select):関心を持った見込み客に向けて、このステージではビジネスケース(ビジネス価値を説明するための素材)を作成する。
AIツールは見込み客から提供された情報とSAPのデータベースを用いて、各見込み客向けに主要なメリットと可能なソリューションを示した「バリューワンページャー」を作成する。別のAIツールは見込み客にソリューションを体験してもらい価値を視覚化するために、パーソナライズされたデモとガイドツアーを作成する。
その後、さらに別のAIツールが取引条件の設定、契約、コンプライアンス、売上計上、回収といったタスクを自動化し、「見積もりから入金まで」のプロセスを支援する。驚くことに、多くの中小企業がSAPの営業担当者に初めて直接会うのは契約締結時である場合が少なくない。
・導入(Adopt):ERPソフトは顧客の業務プロセスへの統合が必要であり、SAPは導入にチャネルパートナーを活用している。しかし導入は、顧客との関係の始まりにすぎない。サブスクリプションモデルでは、製品の価値を実感できない顧客は更新せずに解約する。
顧客に価値を見出してもらうために、SAPはアバター付きのトレーニング動画を作成するAIツールを用いて、ソリューションの機能とメリットを強調している。別のツールでは、ユーザーはドキュメントをアップロードして大規模言語モデル(LLM)の機能を活用し、インタラクティブなQ&Aを行うことができる。さらに別のツールはSAPの社内データを利用して、従業員によるメールや会議、プレゼンテーション用のコンテンツの生成を支援する。
・価値の導出(Derive):クライアントが継続的な改善を推進できるよう、AI駆動のカスタマーサクセス・プラットフォームが複数の情報源から顧客データを統合し、すべての関連情報に1カ所でアクセスできるカスタマイズされたランディングページを作成する。そして別のツールが、パフォーマンス改善に向けて個々の顧客に合わせた助言を提供する。
・関係の発展(Extend):顧客との関係を強化して発展させるために、デジタルローンチパッドは関連性が高そうなSAPの新製品を特定し、バリューワンページャーが製品のメリットを示したビジネスケースを提示する。別のAIツールは、SAPのソリューションアドバイザーが質問に素早く対応できるよう支援する。
AIツール群を活用することで、SAPのデジタルハブは購買ジャーニーの90%をバーチャルで誘導している。これにより営業生産性が著しく向上するうえに、まったく新たな中小の顧客層への売り込みが可能になるため、獲得可能な最大市場規模(TAM)が拡大する。
アイデアの培養、試験運用、規模拡大
AIツールがなければ、SAPにとって中小企業はリーチしても採算が取れない断片的な市場であった。AIツールによって、この市場はアプローチしやすく利益を生むものとなった。しかし、AI市場にある何百もの選択肢からどのAIツールを選べばよいかは、些細な問題ではない。
最終的に40を超えるAIツールを導入する過程で、アイデアの培養、試験運用、規模拡大という体系的なプロセスが必要であった。まずSAPは2年間にわたり、2万5000人の従業員を対象とする社内イノベーションチャレンジへの公募を通じて、数百のアイデアを生み出した。
次の段階として、有望なアイデアを試験運用し、問題や改善機会を見つけ出し、ツールの価値を理解し定量化するためのテストを実施した。1250を超えるGPTプロンプトが考案され、オブジェクション・ハンドリング(応酬話法)、エレベーターピッチ、製品インサイトなどを含む50種類以上のユースケースごとに分類されたプレイブックとして文書化された。試験運用では、多くの活動の完了時間がAIツールによって平均で60%以上減ることが判明した。
概念実証を完了した後は、有意義なビジネス成果を生むために規模を拡大する必要がある。SAPはツールの導入、更新およびサードパーティのサプライヤーの統合を行う場を一元化するために、プラットフォームのアプローチを用いた。これにより、同社の既存のインフラにAIツールを統合することも可能になる。
その過程では障害もあった。プラットフォームは当初、CRM(顧客関係管理)システムや価格モデルとうまく統合されなかった。そこでデジタルチームが開発部門と協働し、さまざまなプロセスの統合に取り組んだ。そのためにはコミットメント、経営首脳部のサポート、変革マネジメントのプロセスが必要であった。
購入か、自社開発か、迅速化のための提携か
AIの分野は指数関数的なスピードで進んでいるため、高度な技術力を持つ企業でも、より迅速に動くためにサードパーティ製アプリケーションとの提携を求めることが多い。
SAPのデジタルチームはその必要性を認識していたが、同社の伝統とエンジニアリング品質への誇りが、提携かツールの自社開発かをめぐる社内での激しい議論を引き起こした。ここでも社内文化の変革が必要となった。最終的にSAPのデジタルプラットフォームは、自社製と外部のAIツールを組み合わせて用いることになる。社内システムへのサードパーティ製ツールの統合は、克服すべきもう一つの課題となった。
成果を測定し、定量化する
最も困難な課題の一つは、AI投資によるビジネス成果を切り分けて測定し、定量化することだ。大規模な組織ではこれが特に難しい。メリットは効率化、コスト節減、あるいは新たな機会を獲得するケイパビリティといった形で生じるかもしれない。精度よりも、エビデンスで裏づけられた合理的な概算のほうが大事である。
SAPは一つのタスク、たとえば「見込み客1000件へのリーチ」に営業チームが費やした時間をモニタリングし、基準値を設定した。次に、同じ数の見込み客にAIツールを用いてリーチした場合に要した時間を追跡した。どちらの方法でもコンバージョン率に顕著な差はなかったが、営業チームは見込み客の創出にデジタルモダリティを使うことで、時間を約40%節約した。
SAPのデジタルハブは、平均12~18カ月だった営業サイクルを3~6カ月に短縮させた。2024年には2万2000件を超える新規顧客への営業機会を後押しし、営業パイプラインの案件を倍増させ、同社の主要クラウド製品への需要を生む最大の源泉となっている。
自社の状況に合わせて調整する
SAPのアプローチにおける多くの要素は、ほとんどのビジネスの状況に当てはまる。市場機会の把握から始め、カスタマージャーニーをマップ化し、適切なツールを開発または提携によって入手し、それらを試験運用して規模を拡大し、成果を測定する──これらはすべて、有望なテクノロジーをビジネス上の現実へと転換するために不可欠だ。ただし、企業の状況に合わせて調整すべき他の要素もある。
以下は、AIの取り組みを策定する際に考慮すべき3つの領域である。
顧客の選択
これは戦略の核心であり、どの購買ジャーニーをテクノロジーツールでマップ化、誘導、管理する必要があるのかを決定づける。顧客は製品・サービスに対する好み(市場セグメンテーションの基準になる)が異なるだけでなく、テクノロジーを活用したインタラクションにどう反応するのかも異なる。新しいテクノロジーの導入具合は顧客によって非常にさまざまであり、その好例として新聞業界は収益の大部分をいまだに印刷物から得ている。
製品
B2B市場では、顧客は自社の既存のプロセスに製品がどう適合するのかに関する詳しい情報を求める場合が多い。このことは、SAPが中小企業の購買ジャーニー全体においてAIツールをどう選んで実装するのかに影響を及ぼした。しかしAIを活用すべきタスクや情報は、業界、製品カテゴリー、購買ジャーニーによって異なる。
例としてアドビは、クラウド型のサブスクリプションモデルに移行した後、やはりカスタマージャーニーを5つのステップ──発見、試用、購入、利用、更新にマップ化した。だがSAPとは違い、アドビは個々の消費者向けに製品をカスタマイズする必要はなかった。代わりにサブスクリプションモデルによって、フリーミアムの価格モデルを通じて体験版を何百万人もの消費者に無料で提供できるようになった。SAPのソフトウェアは複雑かつクライアントのプロセスに統合する必要があるため、これは不可能だ。
無料トライアルは、消費者がどこで助けを必要とするのかに関する貴重な洞察をアドビにもたらし、多数の動画とチュートリアルの開発につながった。製品チームは現在、独自の判断を根拠に機能を構築するのではなく、消費者の実際の利用状況に基づいてソフトウェアを継続的に改善できるようになった。各ステージでAIツールを用いることで、プロセスの効率と効果を高めることができている。
自社の製品カテゴリーと顧客の意思決定プロセスについて十分に理解していなければ、顧客とのインタラクションの中で、AIの能力が自社にどう成果をもたらしうるのかを把握できない。あるいは広告、既存の営業チャネルやその他の活動において、AIの能力がどの部分を効果的に代替できるのかを知ることができない。これは技術ではなくマネジメントの問題だが、理解が欠けている場合、AIは「ソリューションを探すためのツール」に留まるか、または単なる事業運営上の新たなコストとして扱われかねない。
変革マネジメント
事業開発の取り組みにおける大規模な変革は、通常は社内の抵抗に直面する。変革は一度きりのイベントでもCEOのスピーチでもなく、プロセスである。そのプロセスは会社の歴史と文化に左右される。
たとえばSAPは、長い歴史と独自の専門知識を持つ複数の部門から賛同を取りつけるために、連合型のモデルを用いた。AIの機能を中央集権化すれば、より早く実装できたはずだ。しかしそのやり方では、自分たちの事業領域をかなり自律的に管理することに慣れている多くのステークホルダーの抵抗を軽減できなかっただろう(むしろ助長していたかもしれない)。同社のデジタルハブは各地域の事業リーダーたちに直属し、グローバルデジタル本部とは間接的な報告関係にある。
しかし、市場ポジションが異なる他の企業は、AIが生む絶好のチャンスはすぐに終わってしまう可能性があることに気づくだろう。したがって、異なる変革マネジメントのアプローチが必要となる。
この点において、AI技術は新しくても、付随する課題と選択肢は目新しいものではない。ルイス・ガースナーは自伝『巨象も踊る』の中で、1990年代のIBMでの経験を振り返り、このことを的確に表現している。「企業文化は経営の単なる一側面ではなく、経営そのものであると私は理解するようになった。結局のところ組織とは、それを構成する人々が集合的に価値を生み出す能力に他ならない」
"How One Company Used AI to Broaden Its Customer Base," HBR.org, March 27, 2025.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









