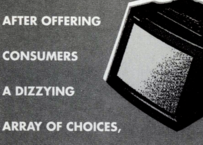-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ビジネスにおける「供給者誘発需要」の現状
1900年代初頭、英国はボーア戦争の余波のなか、自国の状況を見つめ直していた。当時の英国は地球上で最も強大な帝国の一つだったが、兵士たちは戦闘で失態を見せ、その原因が誰にも分からなかった。そこで、ある人物が意外な元凶を指摘した──兵士の劣悪な健康状態である。
すると一夜にして、「国を救うには子どもの扁桃腺を切除しなければならない」という信念が広まった。免疫系において重要な役割を果たす柔らかなリンパ組織である扁桃腺は、あらゆる感染症の元凶として非難された。子どもがわずかな喉の痛みを訴えただけで──一部の町では、まったく別の理由で病院を訪れただけでも──医師たちはすぐにメスを手に取った。扁桃摘出術の熱狂は、都市から都市へと一気に広まっていった。
多くの親はこの手術を奇跡の治療法と受け止めたが、実際の事情はより複雑だった。扁桃摘出術が普及するにつれ、大半の子どもの健康状態が改善しておらず、しかも深刻な合併症に苦しむケースもあることが明らかになったのだ。
医学史に残るこの教訓は、いまでは「供給者誘発需要」(Supplier-Induced Demand)の典型例とされている。これは、サービスの必要性を訴える人物が、その提供によって報酬を得ている状況を指し、実際のニーズを超えて推奨が広がる事態を招きやすい。
20世紀の英国では、世論の強い反発によって医師たちがこの手術の科学的根拠を疑問視するようになり、扁桃摘出術はようやく廃れていった。しかし、供給者誘発需要という現象自体は、その後もけっして消え去ることはなかった。
現代の企業幹部のオフィスでも、供給者誘発需要は姿を変えて存在している。高額報酬を得る戦略コンサルタントが次々と組織再編を推奨し、外部の法律顧問がさらなる訴訟を勧め、ファイナンシャルアドバイザーが次の大型買収を後押しする。
英国の医師たちと同様、こうしたプロフェッショナルの多くは陰謀を企てる悪人ではなく、みずからが顧客を正しい判断へ導いていると心から信じている。しかし実際には、不要なサービスを推奨しやすい条件が整ってしまうことも少なくない。その結果、質の疑わしい業務が渦巻き、予算が際限なく膨れ上がり、時には壊滅的なビジネス上の結果を招くことすらある。
不確実性という問題
現代の組織において供給者誘発需要が生まれる主因となっているのは、複雑さと、それに伴う不確実性である。過去数十年の間にプロフェッショナルの世界はさらに専門分化し、財務、法務、テクノロジー、業務運営といった各分野には、それぞれ独自の新しいツール、規制、可能性が雪崩のように押し寄せている。しかも、こうした分野は互いに独立しているわけではない。複雑な経営判断を行う場面では、これらの分野がしばしば絡み合い、最も有能な経営幹部ですら圧倒されるような迷路を生み出す。
経営幹部の受信箱に殺到する数々の課題を考えてみてほしい。AI、コンプライアンス分析、ブロックチェーン、予測モデリング、新たな規制枠組み、デジタル・トランスフォーメーションなど、いずれも急勾配の学習曲線を伴う。どのリーダーもすべてを習得することは不可能であるにもかかわらず、判断は待ったなしだ。どのツールを採用すべきか。どの変革から着手すべきか。知的財産をどう保護するか。あるいは、そもそも何か行動を起こすべきなのか。
このような不確実性に直面すると、人は専門家の助けを求める。だからこそ、混乱を整理し、秩序を与えると約束するプロフェッショナルサービスが繁栄しているのである。
実際、こうしたサービスの多くは驚くべき規模にまで成長を遂げている。デロイトやアクセンチュアといった経営コンサルティングファームの大手2社だけで、100万人以上を雇用しており、PwCやKPMGもそれぞれ数十万人規模の従業員を擁する。なお、典型的なフォーチュン500の従業員数は約6万人程度である。グローバルな法律事務所や投資銀行も同様の成長を遂げ、なかにはそれ自体が巨大企業となった例もある。
専門家の助言を求めたり、提供したりすること自体には、何の問題もない。問題が生じるのは、問題を診断する人物が、その解決によって報酬を得る構造にある場合だ。
複雑かつ先端的な分野においては、依頼者自身が本当に何を必要としているのかを明確に把握できていないことが少なくない。サービス提供者は新たな戦略の導入を勧め、その実行を請け負って報酬を得る。また、訴訟を提案し、その案件を担当して報酬を得ることもある。こうした場合、サービス提供者は必要性の特定と実行の両方で対価を得ることになる。「髪を切るべきかどうかを理髪師に尋ねるな」とはよく言われるが、プロフェッショナルサービスにおいてはまさにそれが日常的に行われている。
とはいえ、こうした実態を懐疑的に見て、単なる金儲けだと一笑に付すのは早計である。プロフェッショナルサービスの多くは、長期的な関係性を基盤として成り立っている。シニアパートナーのなかには、自社の幹部以上に顧客企業のビジネスを理解していると胸を張る者もいるが、それは彼らが長年にわたってその企業に関与し続けてきたからである。研究によれば、こうした埋め込まれた関係は、機会主義的な行動を大幅に抑制する効果があるとされている。
筆者の研究によれば、供給者誘発需要を引き起こしているのは、陰謀を企てる強欲で不道徳なプロフェッショナルではない。むしろ、善意を持つ専門家ですら、自身のソリューションを過剰に推奨したくなるような、より微妙な力が働いているのである。
行動重視の専門家の台頭
筆者の著書The Influence Economy(未訳)は、プロフェッショナルサービスの買い手と売り手に対する数十件のインタビューを活用している。また、企業による法務サービスの利用に関する独自データを分析し、社会学、経済学、経営学、社会心理学、さらには神経科学における数百件に及ぶ研究を精査した。
筆者の調査から明らかになったのは、供給者誘発需要の背後にある真の要因は、プロフェッショナルサービス提供者がみずからとその役割を捉える認識における根本的な変化であるということだ。数十年前、プロフェッショナルサービス企業は「助言を提供する」という単純明快な論理に基づいて運営されており、年功序列や長期的な献身を重視した控えめなパートナーシップの文化が根づいていた。パートナーシップは終身雇用を意味し、他社からの人材引き抜きはほぼタブーとされ、広告や収益性を話題にすることはほとんどなかった。
だが、現在では状況はまったく異なる。コンサルティング会社、法律事務所、投資銀行は、いまや大規模な営利企業の様相を呈しており、なかには株式上場を果たしている企業もある。パートナー選出の基準も大きく変化し、クライアントの獲得と収益の創出が重視されるようになった。業績の芳しくないパートナーは、ライバル企業から引き抜かれた高業績のスター人材と交代させられる。
この変化はプロフェッショナルに明らかな売上げプレッシャーをもたらしているが、より深刻なのは、彼らの職業的アイデンティティそのものを根本から再構築している点である。いまや多くのプロフェッショナルは、継続的な行動、成長、そして絶え間ないクライアントとの関与を、クライアントの成功──ひいてはみずからの成功──を示す指標とする商業的なマインドセットを内面化している。
この新たな論理は、プロフェッショナルを単なる中立的な助言者ではなく、変化・革新・進歩を推進する積極的な担い手として再定義する。そこでは、不作為よりも行動が重視される。もはや現代のプロフェッショナルは、必要な時にだけ助言を行うという旧来の姿勢に留まらず、たとえその行動の真の価値が不確かであっても、継続的にソリューションを提案し、プロジェクトを立ち上げ、戦略的な取り組みを推進することを当然の義務と感じている。
ある著名なコンサルティングファームのシニアリーダーは、筆者に対してパートナーになるための要件を率直に語ってくれた。「すべての基準がレインメーカー(多大な収益をもたらせる人物)であることに関わっている。つまり、自分のプログラムを自力で回し続けられることが大切だ」
筆者が話を聞いたプロフェッショナルたちにとって、供給者誘発需要は、積極的な関与によって価値を提供しているという誠実な信念の下に静かに生じている。また、クライアント側も、継続的な行動、自信に満ちた助言、そして積極性を示す明確な行動を期待することで、この力学をさらに強化している。このようにして、相互に強化し合うサイクルが形成され、供給者誘発需要が蔓延する環境が作り出されているのである。
どう対処すべきか
供給者誘発需要を見抜くのは、意外なほど難しい。プロフェッショナルサービスは多くの場合、非常にカスタマイズされており、その成果も明確に測定しにくいためである。訴訟や買収、組織再編が期待外れに終わったとしても、原因としては戦略ミス、実行の不備、クライアントが関連情報を共有しなかったこと、あるいは外部専門家の判断ミスなど、複数の要素が絡み合っており、真の原因を特定するには多くの推測が必要となる。
加えて、そもそもそのプロジェクトを実行しなかった場合にどうなっていたかを知ることはできない。そして、この点こそが、供給者誘発需要の存在を見極める真の試金石である。
だからこそ、真の手掛かりは、大規模なデータセットの中にしか現れない。たとえば筆者は、バイオテクノロジーと製薬業界の405社を対象に、9年間にわたる1100件以上の特許侵害訴訟を分析した。すると、不確実性が高く、外部の法律顧問に容易にアクセスできる企業ほど、訴訟件数が多いことが判明した。これらの訴訟は長期化しやすく、それに伴いコストが増加し、成功する可能性は低くなる傾向にある。
もちろん、個別のケースごとに「何もしなかったほうがよかったのかどうか」を判断するのは、ほとんど不可能である。したがって、単発の事例に注目するのではなく、供給者誘発需要がそもそも発生しやすい条件に目を向けるべきだ。つまり、リーダーや専門家がそのリスクを避けられるよう、あらかじめ行動の指針(ガードレール)を与える必要がある。以下に、筆者が推奨する6つの具体的なアクションを示す。
1. 専門的な業務を選択的にインソースする
リスクが高く、不確実性も大きいプロジェクトでは、業務の一部を社内に取り込むことを検討すべきである。複雑な業務をアウトソースすれば、それに伴って専門知識も社外に委ねることとなり、組織としての学習能力を損なうおそれがある。
M&A(企業の合併・買収)、複雑な訴訟、高度な技術導入といった分野において社内で専門人材を採用または育成することで、発注者とサービス提供者との間にある「専門知識のギャップ」を縮小できる。これにより、外部アドバイザーの提案を的確に評価し、必要であればそれに異を唱えるだけの知識と判断力を備えることが可能となる。
インソースには当然ながら一定のコストが伴うものの、重要な意思決定を「行動を起こすこと」を優先しがちな外部関係者に委ねるリスクを回避できる。
2. 社内の専門性と監督機能を強化する
筆者が行ったフィールド調査では、プロフェッショナルサービスに圧倒され、「何を質問すべきかさえわからなかった」と語る経営幹部もいた。
仮に複雑なプロジェクトのすべてを社内で担わない場合でも、その進行に密接に関与する「SWATチーム」を編成し、適切な権限を付与すべきである。このチームは、外部提供者の業務について、その必要性、進捗、範囲、成果を把握・監督できる十分な専門知識と独立性を備えている必要がある。
たとえば、退職したばかりの幹部や学識経験者、あるいはそのプロジェクトに直接関与していないその他の専門家を活用することを検討すべきである。彼らがすべての工程を細かく管理する必要はないが、不要な業務の追加やプロジェクトの範囲拡大を見逃さないよう注視する役割を担わせるべきである。
3. 診断と実行を分離する
供給者誘発需要を抑制するもう一つの方法は、「何が必要か」を診断する役割と、それを実行に移す役割を分離することである。この原則は、多くの医療制度において長年にわたり慣行とされており、医師が薬を処方し、かつ販売も行うことは、何世紀にもわたって禁じられてきた。近年の研究でも、このような制度が有効であることが実証されている。
企業においては、ある会社に課題(たとえば戦略上のギャップ)の診断を依頼し、その解決策(組織再編、マーケティング戦略、IT刷新など)の実行は別の会社に委託するという体制を取ることで、問題の有無にかかわらず、単一の業者が課題の発見と解決の両方を強く推し進めるというリスクを軽減できる。
4. 知識とプロセスを文書化する
意思決定、前提条件、成果を文書化するよう組織全体に促すことは、供給者誘発需要を抑制する強力な手段となる。たとえば、組織再編、合併、訴訟といった判断を下す際に用いる明確なチェックリストを策定すべきである。外部の業者を起用する場合には、どのように診断に至ったのか、なぜ特定の解決策を選択したのか、どの指標で成果を評価するのかといった点について、透明性のある記録を求めるべきである。
業務をある外部業者から別の業者へと引き継ぐこと(ステップ3の形式)は、知識やプロセスの文書化を自然に促進する。こうした情報があれば、提案された施策が本当に必要かどうかについて、より本質的かつ深い議論が可能になる。また、新たな助言が提示された際に過去の記録を遡って参照できるため、同じ誤判断を繰り返していないかを検証しやすくなる。
5. 形式的な依頼を避ける
「他社もやっているから」という理由だけでプロフェッショナルサービス企業に業務を委託すべきだというプレッシャーを感じている発注者は少なくない。ある社内弁護士は、「群れで泳いで失敗するほうが、自分の判断で失敗するよりもキャリアへの影響は小さい」と語った。
よくあるのが、すでに下された賛否の分かれる決定や社内で不評な判断を正当化するためだけに、コンサルタントを起用するケースである。筆者の調査によれば、このような一見無害な依頼の始まりが、他の分野における供給者誘発需要を誘発することがある。この点を念頭に置き、プロフェッショナルサービス企業に依頼する際の明確かつ厳格な基準を設けるべきである。
6. 適切な自制を重んじる文化を育む
企業が常に「次の大きな変革」を追い求める文化を持っている場合、その企業は、内容にかかわらず何らかのアクションを取り続けようとする銀行家、コンサルタント、弁護士を報いる構造を生んでいる可能性がある。プロフェッショナルサービス企業もまた、同様に「行動優先」の方向に傾きがちである。
しかし、立ち止まって「とにかく何かをしよう」という衝動に疑問を呈する人々に敬意を払う姿勢には、重要な意味がある。あえて動かないという判断が最善であると気づいた経営幹部やアドバイザーの実例を社内で共有すべきである。
ある大手コンサルティング会社のシニアパートナーは、自身のキャリアにおいて最も誇りに思っているのは、チームに適さないと判断した数百万ドル規模の案件から手を引いた決断だと語った。彼がその後も同じ会社に長く在籍し、その決断がいまなお称賛されているという事実は、その判断の価値を如実に物語っている。
* * *
医療と同じく、ビジネスの世界でも、本当に重要なスキルとは、行動を起こすべきタイミングではなく、行動を起こすべきではないタイミングに気づくことだ。プロフェッショナルサービスの分野で供給者主導型需要が生まれる原因は、強欲や詐欺行為ではない。専門職のアイデンティティに生じた微細だが強力な変化、つまり、「常に行動し続けることで、常に前進できる」という誤った信念から生じるのだ。
しかし現実には、じっと待つこと、つまり手術や企業合併、華々しい新戦略といった誘惑に抗うことこそが、最も正しい判断である場合もある。賢明なリーダーをその他大勢と隔てるのは、変化を受け入れる姿勢だけではない。その変化が本当に必要かどうかを問い直す力こそが重要なのである。
社内に専門家を育て、課題の診断とソリューションの実行を切り離し、そしておそらく最も重要な要素として、「熟慮の結果、何もしない」という決断を評価することで、企業は供給者主導型需要を生み出す目に見えないサイクルを断ち切ることができる。
"When Outside Experts Diagnose Your Problem - and Sell the Solution," HBR.org, April 18, 2025.






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)