
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「集積力」が地域に与える壮大なパワー
「住んでいる場所は関係ない」というのが、グローバル時代の不文律と化している。アスペンのスキーロッジやプロバンスの別荘にいても、シリコンバレーのオフィスにいるかのように効率的にビジネスができる。ワイヤレス通信とモバイル機器がある限り、地理的な影響は微々たるものだ。
新技術の目覚ましい発達はさておき、物理的距離の消滅は決して最近に始まったことではない。初めは鉄道によって、交易と交通に大変革が訪れた。次に電話が人々の気持ちをつなぎ、近づけた。自動車や飛行機、そしてグローバル世界の象徴とも言えるワールド・ワイド・ウェブが発明された。あらゆるテクノロジーが広大な世界を一つに結びつけ、地理的な束縛から私たちを解放した。華やかな都会から、田舎暮らしへの転換も可能となったわけだ。
肥沃な土壌、天然の港や原材料の有無に、都市や文明が拘束を受けていた時代は過ぎ去った。現代のハイテク世界では好きな場所に自由に住むことができる。昨今、こうした見方はひときわ広まっており、住む場所はもはや重要ではないかのようだ。
これはなかなかに抵抗しがたい概念だが、実は大きな誤りがある。才能、イノベーション、クリエイティビティのような現代の主要な生産要素は均一に分布していない。むしろ特定の地域に偏り、集中しているのだ。
通信や交通における大規模なイノベーションにより、経済活動が世界的に拡大していることは周知の事実だ。しかし、それに比べて自明でないものがある。私が「集積力」と呼ぶ壮大なパワーだ。
現代のクリエイティブ経済における経済成長の真の原動力とは、才能と生産性に満ちた人々の蓄積と集中化である。彼らが特定の地域に寄り集まって住むことで、新しいアイデアが生まれ、その地域の生産性は増加する。集積化によって個々の生産力が高まり、今度は生産物と富の増加を生成しつつ、地域そのものの生産性を高めるのだ。
集積力により、都市や地域は経済成長の真の動力源となる。これは何ら不思議な現象ではない。今日、世界の人々の半分以上が都市圏に住んでいる。事実、アメリカでは国内総生産(GDP)の90パーセント以上を大都市圏が担い、さらに、そのうち23パーセントを、たった5つの主要都市が稼ぎ出している。都市とそれを取り囲む広大な一帯は数千億、場合によっては数兆ドルの経済生産を誇り、数千万の人口を抱えた巨大なメガ地域に変容しつつある。
いまや場所は私たちの時代の中心軸であり、世界経済や個人の生活に、これまで以上に重要な関わりを持っている。
現代人は人類史上、最も移動志向が強く、一方でアメリカ国内または世界を問わず、居住地選びの候補には事欠かない。私たちのニーズや優先事項はそれぞれ異なるだけにこうした選択肢の多さは重要だ。活況な労働市場を有する地域もあれば、教育や安全といった基盤に勝る地域もある。単身者向きの地域もあれば、ファミリー向きの地域もある。ビジネスに特化している場所もあれば、娯楽に特化している場所もあり、保守的な地域もあれば、リベラルな地域もある。各地域が異なる要件を満たし、それぞれに独自の個性と精神を有しているのだ。
なおかつ地域の個性は変動しやすい。その把握は難しそうに思えるが、実は不可能なことではない。調査の結果を地図に書き起こしたので、本書『クリエイティブ都市論』第11章を見てほしい。
変動しやすいのは、地域ごとの個性だけに限らない。私たち自身が居住地に求めるものも、ライフステージに応じて変化する。学校を卒業したての若い独身時代には、楽しいナイトライフと、デート相手に困らない「恋愛市場」の活発な場所に住みたがるものだ。刺激的で仕事が多く、出世のチャンスが豊富な場所ならなおさらである。
だが少し年齢が上がったり、結婚して子供ができたりすると、私たちのなかの優先順位は変化する。いい学校や安全な道路など、家族にとってより望ましい環境を求めるようになる。そして子供たちが大学に進学して家を出ると、私たちの関心は再び変化するのだ。
いま挙げた例のほかにも、人生にはさまざまなターニングポイントがある。その一つひとつにおいて、自分に本当に必要な場所を選ぶチャンスに恵まれた人たちは増えている。
居住地選びをサポートしてくれるフレームワーク
では居住地選びについて、私たちはまず何から考え始めればいいのだろうか。いまから50数年前、偉大な経済学者チャールズ・ティボーが、居住地の選択を行うにあたり、説得力あるフレームワークを概説している(注3)。
かつてティボーは教育、治安、街の活気、公園などの行政サービスや公共財について、それぞれの自治体には特徴があると述べた。その有名な主張にもあるとおり、人は「足による投票」を行い、自分の好みやニーズに合致した公共財や行政サービスを得られる自治体を選んでいる。
実際、自治体から受けられるサービスの内容や質に対して、私たちには税金という代価が生じる。すなわち私たちは居住地を選択する際、物理的な要素だけでなく、そこで得られる各種の公共財や行政サービスをも含めて選んでいるのだ。
幅広い選択肢を与えられた私たちに必要なのは、主要なニーズと優先順位を把握してから、自分の希望と支払い可能な予算に見合った場所を探すことである。たとえば高度な教育環境を望み、そのための費用を準備している人がいる一方で、単身者や子供が独立した人は教育環境をさほど重視しない。こうした人は上等なレストラン、世界的に有名なビーチ、素晴らしいゴルフコースがあり、納税負担の軽い場所を望む傾向にある。
次は代価の話だ。住む場所の選択は、人生の目標を実現するうえで、最も重要な手段の一つだ。ゆえにロンドンやニューヨークのような大都会で得られるスリルや興奮、チャンスを欲しがる人もいる。だが、それには法外な出費が伴うことを忘れてはならない。ロンドンやニューヨークをはじめ、サンフランシスコ、アムステルダム、ボストン、シカゴ、トロント、シドニーといった大都会に住むには、きわめて多額のコストがかかる。金融関係の仕事をする人なら察しがつくだろうが、ニューヨークやロンドンで得られる経済的収入から生活費を差し引くと、ほとんど何も残らない。各産業をリードする、ほかの地域についても同様である。映画産業のメッカであるロサンゼルスや、ファッション産業の中心地であるミラノやパリもまた同じである。
一方、地理的優位性に左右されない業界で働く人や、所属業界のトップに立つことを志向しない人の場合はどうだろう。そうした人には、ささやかな生活費で暮らせる素晴らしい場所がたくさん待ち受けている。絶対に忘れてはならないのは、自分が目指す生活の質と、職業人としての目標とを比較検討することだ。
本書『クリエイティブ都市論』が述べる3つのポイント
私が本書『クリエイティブ都市論』を書いたのは、読者が、自分に適した居住地を選ぶのに役立つためだ。25年以上にわたる独自の調査結果と、ほかの人が行った多数の研究や調査結果について、皆さんと共有することにしたい(4)。本書『クリエイティブ都市論』では次の3つのポイントに沿って、私自身の意見を構築している。
1.グローバリゼーションや「フラットな世界」について、誇大な主張が数々なされている。だが現実には、居住地がグローバル経済のなかで占める重要性は、これまでになく増している。
2.住む場所の多様化と特殊化は、さまざまな観点において進んでいる。それは経済的な構造や労働市場に始まり、得られる生活の質、そこに住む人間の性格にまでおよぶ。
3.私たちはきわめて移住志向の強い社会に生活している。ゆえに居住地について考える機会を何度も持ちえる。
以上、3つの事柄が総合的に意味すること、それは居住地の選択が、家計や仕事の選択肢、友人関係、未来の結婚相手、子供の将来に至るまで、ありとあらゆる物事に大きな影響を与えるということだ。
本書『クリエイティブ都市論』第1部は総論である。居住地がグローバル経済で重大な意味を持ち続ける状況と、その理由について考察する。また、グローバリゼーションの現実とメガ地域の機能を地図に示す。新しい経済単位は私が「スパイキーな世界」と名づけた様相を呈しているが、そのことを地図や統計資料によって提示する。
本書第2部では、住む場所の選択が、それぞれの家計にどのような影響を与えるのかについて触れる。具体的には労働市場の現状や住宅市場の動向、不動産評価といった身近な経済問題に対し、地理的条件が与える影響を取り上げる。なぜ一部の地域では、ほかの地域よりも経済的メリットが発生しやすいのか、その仕組みについても示す。そして才能や技術のある人々が、ごく限られた地域へ移動する現実を詳しく説明する。さらに住宅市場の浮き沈みを引き起こす原因を検証する。加えて、シリコンバレーやオースチンにおけるハイテク産業や、ニューヨークの金融産業、ハリウッドの映画産業などのように、ある特定の地域に経済活動が集中し、かつ専門化する傾向についても述べたい。
本書第3部では、居住地の選択にあたり、最も考慮すべき事柄であろう取捨選択の問題、つまり職業人としての目標と自分のライフスタイル、その他の要求とのバランスのとり方について考える。また居住地と、幸せで満ち足りた生活を送るための条件との間にある相関関係についても考察する。この考察はギャラップ・オーガニゼーションとの協力で、2万8000人を対象に行った大規模な調査結果に基づいている。「居住地と幸福に関する調査」と題したこの研究によって、居住地は職業や家計、私的な人間関係と同様、人間の幸福に大きな影響を与えることが判明した。
最終章は実用的な内容となる。読者が自分に最適な居住地を探すための基本的なツールを紹介する。現在の居住地に満足している人も、この章を読めば自分が本当は何を望み、何を必要としているかについて理解が深まるだろう。また転居を考えている人にとっては、何をどこで探せばいいのかがわかる詳しいガイドとなるだろう。
本書『クリエイティブ都市論』を読了する頃には、今日のグローバル経済において、居住地がどれほど重要な役割を担っているかが理解できるはずだ。また自分にふさわしい居住地を選び、幸福で充足感に満ちた人生を極限まで引き出すにはどうすればよいか、有効な知識が得られるだろう。
【関連記事】
リチャード・フロリダらの最新記事>>ナレッジ・キャンパス:知識経済に生産性を最大化する都市モデル――東京のCBDの発展から読み解く
[著者]リチャード・フロリダ
[翻訳者]井口典夫
[内容紹介]「クリエイティブ・クラス」という新たな経済の支配階級の動向から、グローバル経済における地域間競争の変質を読み取り、世界中から注目を浴びた都市経済学者リチャード・フロリダ。2008年に発表された本書は、クリエイティブ・クラスが主導する経済において、先端的な経済発展はメガ地域に集中し、相似形になっていく世界都市の現実と近未来像を描いている。さらに、クリエイティブ・クラスにとって、いまや自己実現の重要な手段となっている居住地の選択について、独自の経済分析、性格心理学の知見を使って実践的に解説する。
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
【注】
1)Charles Tiebout, “A Pure Theory of Local Expenditures,” Journal of Political Economy 64, 5, 1956, pp. 416-24.
2)特筆すべきはJane Jacobsによる研究である。The Death and Life of Great American Cities, Vintage, 1992 (first ed., 1961)(邦訳『アメリカ大都市の死と生』鹿島出版会、1977年); The Economy of Cities, Vintage 1970 (first ed., 1969)(邦訳『都市の原理』鹿島出版会、1971年); Cities and the Wealth of Nations, Vintage, 1985 (first ed., Random House, May 1984)(邦訳『都市の経済学』ティビーエス・ブリタニカ、1986年).このテーマに関する著者自身の研究成果はThe Rise of the Creative Class, Basic Books, 2002(邦訳『クリエイティブ資本論』ダイヤモンド社、2008年) にまとめられている。

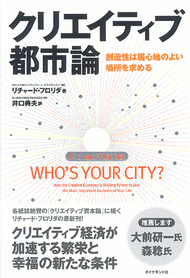




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









