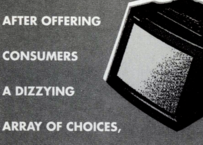-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
地政学的な混乱と技術革新が与える変化
地政学的な混乱と技術革新が、製造拠点網を再編しつつある。リーダーたちはこれらを別々の力学と捉えているかもしれないが、多くの企業は両方に同時に直面している。これら2つが相まって、経営者に戦略の見直しを促す強力な動機とインセンティブを生み出している。
企業は通常、コスト、物流、貿易制度といった予測可能な要因を評価して、製造拠点の配置を決定する。その分析は、しばしば低コスト国への生産移転という結果をもたらしてきた。こうしたオフショアリング主導のモデルは、世界的な効率性と規模に最適化され、比較的自由な貿易環境において安定性をもたらしてきた。
しかし、ボストン コンサルティング グループ(BCG)による未発表の調査によると、その構図はいま変わりつつある。BCGヘンダーソン研究所(BHI)が製造業の経営幹部1000人以上を対象に実施した最近の調査によれば、かつては周辺的な懸念であった地政学的リスクが、現在直面している課題の上位5つまでに入っている。貿易障壁の高まり、政治の不安定化、国家安全保障をめぐる圧力が、製造拠点の配置に関する意思決定に高い不確実性をもたらしている。
同時に、新たな機会も生まれている。ロボティクスのコストの低下とAIの急速な発展により、人間の労働を必要とせず自律的に稼働する「完全自動化」という長年の構想が、現実化しつつある。調査に回答した製造業者の62%はすでに複数のAIアプリケーションを導入しており、グローバルなオフショアリングの意思決定を支えてきた労働コストの格差という前提を覆しつつある。
製造業のリーダーは、国内製造が既存のグローバルな競争環境を上回るタイミングを見極めるために、より動的なアプローチを取る必要がある。そのためには、関税による(現行および将来の)影響や、「未来の工場」の導入が現地生産コストに与える影響、さらに進出先の外部環境を理解しなければならない。
関税により「コスト競争力に最も優れた国」は変動する
かつて安定した前提条件であった関税は、いまやコスト優位性を一瞬で消し去る変動要因として再浮上している。たとえば、従来の分析によれば、メキシコでの製造は業界を問わず米国よりも生産・配送コストで平均16%の優位性があったが、この優位性は関税の圧力によって容易に消滅する。メキシコで工場を操業している回答者のおよそ20%は、関税が10%に達すると輸出が経済的に成り立たないと答えている。この割合は、関税が25%になると90%に跳ね上がる。
このような状況において、製造業者は静的なコスト比較を超えて、「関税の転換点」と呼ばれる新たな視点を取り入れる必要がある。つまり、製品を輸入して関税を支払い続けるよりも、現地生産に切り替えたほうが経済的に有利になる関税率を意味する。言い換えれば、関税がこの数値を超えた時点で、現地生産のほうが経済的に合理的な選択となる。この数値は事例ごとに異なり、下記3つの主要な要因によって形づくられる。
1. どのようなコスト構造か
生産コストの中で、現地市場にとって不利な要素が占める割合が大きいほど、関税の転換点は高くなる。たとえば、米国の労働コストが中国より高い場合などが該当する。バッテリーセルの製造のように資産集約型で労働コストが比較的低い場合は、10~15%の関税でも現地生産が合理的になることがある。一方、スマートフォンの組み立てのように労働コストが生産コストに占める割合が大きい場合、米国との労働コスト差を相殺するには30〜35%程度の高い関税が課されて初めて現地生産が合理的になる。
2. どの国からどの国に移転するか
移転先のコスト構造が現在の拠点に比べて不利であるほど、関税の転換点は高くなる。たとえば、欧州市場向けにバッテリーセルを製造する場合、ハンガリーでは要素コストが競争力を持ち、韓国からハンガリーへの生産移転は関税が5%未満でも成り立つ。しかし、韓国からドイツに生産を移転する場合は、ドイツの労働コストとエネルギーコストが大幅に高いため、関税の転換点は20〜25%に達する。
3. 関税コストをどこまで転嫁できるか
企業が関税コストを顧客に転嫁できる場合も、関税の転換点は高くなる。この転嫁の可否は、主に価格決定力と競争の激しさによって左右される。たとえば、医療機器や産業機械など製品の差別化が明確な業界では、価格引き上げによって関税を部分的に吸収し、販売量の減少を最小限に抑えることができる。一方、家具など代替性が高い業界では、関税が低くても利益率が急速に圧迫される。
BHIの調査データでも、10%の関税で貿易が成り立たなくなると回答した企業は、医療機器と産業機械業界ではわずか5%だったが、家具業界では50%に達した。価格引き上げの規模はコスト構造と移転先・移転元の組み合わせに大きく左右される。たとえば、労働集約型の製品を低コスト国から高コスト国に移転する場合、資産集約型の製品を移転するよりも価格の引き上げ幅が大きくなる。
個別のシナリオプランニングが求められている
製品や地域ごとに関税の転換点を把握することは不可欠であるが、依然として不確実性の高い潜在的な関税の影響も考慮に入れなければならない。この不確実性は、関税の規模と期間の両面に及ぶ。政治的な変化や貿易紛争により、一夜にして関税が引き上げられることもあれば、段階的に導入されたり、業界や貿易ルートによって不均等に適用されたりすることもある。
こうした環境において、経営陣は静的な前提に依存せず、シナリオベースのプランニングを中核的な分析手法として採用する必要がある。主要な製造業では、5%、15%、25%といった関税率帯をモデル化し、特定の現地生産戦略が多様な政策シナリオの下でも実行可能かどうかを評価している。さらに、政権交代に伴う関税の撤廃、長期的な保護主義への移行、輸出管理の導入といったシナリオも検討している。オペレーション、戦略、法務、税務、政府対応などの部門を横断するチームが連携し、こうした動向を予測しながら、拠点戦略のレジリエンス(回復力)を検証している。
こうした構造化された感度分析によって、外部ショックに耐えうる製品と拠点の組み合わせ、あるいは脆弱で短期的な前提に依存している組み合わせが明らかになる。またシナリオ策定においては、製造拠点の決定と実行が本質的に長期的プロセスであることも考慮しなければならない。新しい工場の建設には数年を要する一方で、関税政策は一夜にして変更される可能性がある。そのため、リーダーは将来的にまったく異なる地政学的環境の中で適用されるかもしれない決断を、いま下さなければならない。これにより意思決定の複雑性はさらに増し、グローバルな不確実性に直面する製造業にとって、シナリオベースの計画立案は戦略上不可欠なものとなっている。
自動化によって現地生産によるコスト増を相殺できる
企業が現地生産を選択するか否かにかかわらず、関税はコストの上昇要因となる。既存の拠点を維持すれば、製造業者またはその顧客が追加関税を支払うことになり、コスト競争力の低い国へ移転すれば、それに伴うコスト増が発生する。
関税の転換点を算出するのと同様に、現地生産を検討する製造業者は、生産要素コストの差異、物流コストの削減効果、規模の経済の喪失などを踏まえ、自社製品にとって現地化によるコスト増がどのぐらい深刻かを評価しなければならない。
筆者の分析によると、中国から米国へ製造を移転する場合、同一の生産体制およびグローバルに調達された資材を前提とすれば、スマートフォンの組み立てでランデッドコストが31%、自転車フレームの製造が22%、バッテリーセルの製造が10%増加する。国の組み合わせによって結果は異なるものの、基本的な分析手法は普遍的に適用可能である。
現地生産によって輸送コストが削減され、コスト増を軽減できる場合もあるが、今後は「未来の工場」がこのコスト増を大きく相殺し、場合によっては完全に打ち消すことも可能になる。筆者は未来の工場を、最適なレイアウト設計、AIを活用したデジタル化プロセス、最先端の自動化技術を含む、製造における最先端の設計概念として定義する。こうした工場は、高度に自律的かつ自己制御的に稼働する。
未来の工場は、労働集約的な工程を自動化することで、全体としてのコスト競争力を高め、とりわけ労働コストの削減によってその効果を発揮する。その恩恵はグローバルに適用可能であり、特にコストの高い国において顕著である。高コストな労働力への依存度を下げることで、未来の工場は、これまで国内生産の実現可能性を制限してきた労働コストの格差を相殺する手段になるだろう。
ただし、未来の工場の効果は業界によって異なる。その労働集約度やエネルギー集約度、自動化の可能性、顧客との距離などの要因に左右されるのである。たとえば、スマートフォンの組み立て工程では、光学検査や部品の配置といった作業は自動化が可能である一方、最終組み立ての自動化は依然として困難であり、コストも高い。つまり、中国から米国へ生産を移転する場合(両拠点で未来の工場が導入されていると仮定すると)、追加コストは31%から25%にまで削減されるが、完全に相殺できるわけではない。
一方、自転車フレームの製造では、アルミフレームに対する高度な自動溶接セルや、カーボンコンポジットフレームに対する先進的な射出成形技術の導入によって、未来の工場から得られる効果はより大きなものとなる。こうした技術革新により、中国から米国への生産回帰に伴う追加コストは、物流コストの大幅な削減効果とも相まって、22%からほぼゼロにまで低減可能となる。
外部環境を軽視してはならない
関税や未来の工場が現地生産コストに与える影響を定量的にモデル化することは、経営判断における確固たる基盤となるが、熟練労働力の確保、政治・規制の安定性、主要市場への近接性といった定性的な戦略要因を軽視してはならない。たとえ関税や未来の工場が現地生産を後押ししていたとしても、現実の実現可能性がそれとは異なる結論を導くこともある。その逆もまたしかりである。
BCGの調査では、製造業の経営幹部の30%が、こうした定性的な要因をコスト以上に重視すると回答している。業界を問わず、高度な技能を持つ労働力の確保は、拠点設計における最も重要な定性的要因と評価された。他の要因は、特定の業界により強く依存する傾向がある。
たとえば、スマートフォンの組み立てには、精密で反復的な作業を遂行できる訓練を受けた労働者が大量に必要である。フォックスコン(鴻海精密)は、10万人を超える従業員を擁する工場を複数運営している。しかし、高コスト国への大規模な生産移転を支えるだけの労働力プールが存在するのか、またそうした労働者がその移転を受け入れる意志があるのかは明らかではない。
ブランド価値もまた、重要な検討要素となりうる。高級ブランドにおいては、自国における「製造」によってブランド価値が高められている場合もあり、米国での現地生産はその価値を毀損する可能性がある。
グローバルな製造業の新しい戦略ガイド
最終的には、関税や、自動化による現地生産コストの相殺効果、外部環境といった要因が総合的に作用し、国内製造がグローバル拠点に比べて競争力で上回るかどうかが決定される。
これらの要因を包括的に評価するため、筆者は定量的および定性的要因を組み合わせた統合スコアリングモデルを構築した。このモデルには、製造業の経営幹部を対象としたグローバル調査に基づく重みづけを、業種ごとに最適化して適用している。各業種にこのモデルを適用することで、リーダーの意思決定にいかに高度な個別対応が求められるかが明らかになる。
スマートフォンの組み立て
筆者の分析によれば、米国への生産移転の実現可能性は依然として低い。労働集約的な最終組み立ては自動化が難しく、中国の競争力の源泉となっている大規模な労働力プールは、米国には存在しない可能性が高い。自動化は検査や部品配置といった一部の工程には貢献するものの、全体のコスト増を解消するには至らない。
したがって、未来の工場が導入されたとしても、関税の転換点は25%を超えると見られる。このような状況下では、製造業者は米国への移転ではなく、インドやベトナムといった低コスト国を分散先として選好する可能性が高い。たとえば、アップルは米国市場向けのアイフォン生産を中国から米国ではなくインドに移転しており、脱・中国の動きが必ずしも国内回帰を意味するわけではないことを示している。
バッテリーセルの製造
この業界は、筆者の分析では中間的な位置づけにある。労働集約度が低く、米国のような市場での手厚い公的支援によって、コスト格差は縮小しやすい。ただし、物流コストが低いため、生産回帰による利点は限定的であり、中国メーカーは規模、経験、エコシステムの成熟度に支えられ、依然としてコスト面で優位に立っている。
戦略的観点から見ても、中国は正極活性材のような主要原材料において約90%の世界シェアを占めるなど、上流のサプライチェーンを支配している。現地生産は実現可能だが、競争力のギャップを埋めるためには、10%程度の中程度の関税が必要となる。
自転車フレームの製造
3つの業界のなかで、自転車フレームの製造は現地生産が最も現実的な選択肢と考えられる。高度な自動溶接技術や革新的な射出成形プロセスの進展に、物流コストの高さが相まって、関税の支援がなくとも国内生産の競争力が高まりつつある。
戦略的観点を加味すると、現地生産の利点はさらに強まる。米国での製造は「メイド・イン・アメリカ」志向に訴求しやすいだけでなく、同一拠点にブランドとフレームメーカーが共存することで連携が促進され、製品開発のリードタイムも短縮される。実際、米国の自転車市場ではすでにその動きが見られており、未来の工場は、関税による消費者価格の上昇を相殺する有効な手段ともなっている。
* * *
CEOにとってのメッセージは明確である。グローバル製造拠点の設計に関する従来のルールは、もはや適用できない。オペレーションの見直し方針を定めるに当たり、以下の4つの指針に基づいて、現地生産の検討がさらなる詳細分析に値するのか、それとも優先順位を下げるべきかを初期段階で選別する必要がある。
・関税:予想される関税は利益率を侵食するか。
・現地生産のコスト:現地生産に伴うコスト増はどの程度深刻か。
・未来の工場:自動化やデジタル化により、これらのコストを(少なくとも部分的に)相殺できるか。
・外部環境:現地生産における障害や利点はあるか。
これらの要因とその相互作用を正しく理解して初めて、リーダーはたえず変化する地政学的環境に対応することができる。成功のカギは、不確実性の下で定量的なモデリングと戦略的判断を統合した動的な意思決定にかかっている。
"Tariffs, Technology, and the New Geography of Manufacturing," HBR.org, June 02, 2025.






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)