
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
競争と戦略──『[新版]競争戦略論』の根幹を成す概念
本書『[新版]競争戦略論Ⅰ』は、第1章「五つの競争要因」(邦訳Ⅰ巻・第1章)から始まる。1979年に初めて出版されて以来、ビジネスの現実とアカデミックな思索に大きな影響を与えてきた論考の更新版である。すべての企業の業績は、その源泉を二つの面に求めることができる。一つは、その企業が属する業界の収益性、もう一つは、その業界の中での当該企業の相対的な収益性である。私の理論の全容を理解したいと思う人から、何を最初に読めばよいかと尋ねられることがある。「五つの競争要因」なら知っているという人にも、この章は必須の入り口である。この新版では、ストラテジストと投資家にとっての業界分析の意味についても掘り下げている。
戦略の失敗の多くは、競争とは何か、競争はどう進行するのかについての根本的な認識間違いから始まる。競争は狭く定義されることが多く、まるで直接のライバル企業との間だけで起こっているかのように考えられている。この章では、経済理論に立脚して、あらゆる業界の競争を評価するフレームワークを提示した。また、あらゆる業界の構造を評価するための体系的な方法と、業界構造がどう変化するかも論じた。五つの競争要因のフレームワークは、業界の競争構造に焦点を合わせ、業界の平均的収益性に大きな差があるのはなぜか、それが継続するのはなぜか、その事実を戦略にどう活かせばよいのかを説明する。五つの要因──買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、新規参入者の脅威、代替品・代替サービスの脅威、企業間競争の激しさ──は、あらゆる産業の長期的な収益性を決める要因を説明し、どうすれば自社に有利な方向に競争を導けるかを示すものである。
本書『[新版]競争戦略論Ⅰ』第2章「戦略とは何か」(邦訳Ⅰ巻・第2章)は、収益性の方程式の後半、すなわち、なぜライバルを上回る業績を上げられる企業があるのか、に迫っている。私が最初にポジショニング、すなわち業界において競争を優位に進める方法を論じたのは『競争の戦略』においてであった。同書で私は基本戦略の概念を発表した。次に私は『競争優位の戦略』でバリューチェーンの概念を導入し、その考察をさらに前に進めた。この章は1996年に最初に刊行された論文で、ポジショニングの概念を大きく前進させたものである。
企業は、競争相手よりも高い価格または低いコストのいずれかを達成することによって、業界内で高収益を実現する。本章は、競合する企業間に存在する価格やコストの相違は、業務効果(operational effectiveness)(企業がベストプラクティスを達成しているかどうか)と、戦略的ポジショニング(strategic positioning)という二つの異なる源泉から生じていることを示した。
ベストプラクティスの実現を競うことを、私は「最高を目指す競争」と呼んでいる。すべての企業は自社の活動の業務効果を高め続けなくてはならないが、それは誰にとっても勝つのが難しい競争である。収益性の違いは、確固たる戦略的ポジションによってもたらされることが最も多い。それを私は「ユニークネスを目指す競争」と呼んでいる。ユニークネスを目指す競争は、最高を目指す競争よりも持続可能性が高い。本章はなぜそうであるのかを説明する。
この章は、戦略的ポジショニングの根底にある理論を提示している。戦略の違いはバリューチェーンにおけるさまざまな活動(activities)──ロジスティックス、受注処理、製品設計、組み立て、社員の教育訓練など──への取り組みの違いによって決まる。戦略はトレードオフと適合性によって持続可能になる。トレードオフとは、ある特定のタイプの価値を提供すると決めたら他の価値の提供は追わないということであり、適合性とは、バリューチェーン内の複数の選択肢を結び合わせるということである。企業の競争優位は、競合他社とは異なるトレードオフを内包する独自のバリュープロポジションを、多数の活動が適合し補強し合うバリューチェーンを通じて提供できるかどうかで決まる。
本書第1部の最初の二つの章では、個別の企業レベルで戦略を策定する際の中核的フレームワーク(業界構造と競争的ポジショニング)を論じた。それに続く二つの章では、現代の競争において情報技術(IT)が果たす普遍的な役割を検証する。いずれの章でも、中核的なフレームワークを援用してイノベーションを理解する方法を論じた。
本書第3章「情報技術がもたらす競争優位」(邦訳Ⅰ巻・第3章)は、ITが競争において果たす役割の包括的な議論である。ビクター・ミラーと私は、ITが業界構造と競争的ポジショニングの両方で一定の役割を果たしていることを示唆した。五つの競争要因のフレームワークは、ITが業界に及ぼす影響を分析するための構造を提供し、バリューチェーンは、急速に進化している分野でITが競争優位に及ぼす影響を検証するための構造を提供してくれる。
これは何年も前に書いた論考だが、最新のトレンドの紹介ではなく、根底にあるコンセプトを論じているので、いまでも古びず有用な内容を提供している。これを読めば、新世代情報システムの競争上の意義を理解できるだろう。
私たちは「インターネットはすべてを変える」と何度聞かされたことだろう。第4章「戦略とインターネット」(邦訳Ⅰ巻・第4章)では、競争におけるインターネットの役割を論じた。何が変わり、何が変わらないかを考察し、インターネットが自社の競争力に及ぼすインパクトを評価する方法を探った。業界構造分析はここでもまた、インターネットの強い力を解明しかねている組織に戦略的洞察をもたらす強力なツールとなる。
多くの人がインターネットによって戦略は時代遅れになると主張していたが、事実はその反対だった。この章は、なぜインターネットがそのパワーに見合った利点を提供していないのか、なぜ業界の収益性を弱めているのかを解明し、インターネットの登場によって戦略の重要性がかつてないほど高まっていることを論じている。
その延長でもあるが、この章では、テクノロジーの不連続性について戦略的に考える方法を論じている。イノベーションの研究のほとんどは、イノベーションは破壊的で、企業は手痛い打撃を被るだろうと推測している。業界構造を分析するツールは、新技術のインパクトを受けた業界が収益性を保てるかどうかを予測するのに役立つ。競争優位のロジックは、既存企業が新規参入企業よりも新技術を上手に利用できるのはいつ、どのような場合かを示し、企業(既存企業であれ新規企業であれ)が変化する業界の中で占めることのできる高収益ポジションを見つける方法を示唆する。
21世紀には、優勢な業界の顔ぶれを変えるテクノロジーの革新が途絶えることなく続くと思われる。それは、周囲の至るところで、否が応でも競争を激化させる推進力である。私はかねがね、大きなテクノロジーの変化に直面した時、企業は戦略上の思考停止に陥って不利益を被ることが多すぎると考えている。
本書第1部の最初の四つの章は、単一の事業における戦略──私はそれを「競争戦略」(competitive strategy)と呼ぶ──を扱っている。これは戦略の中核レベルである。なぜなら、そこで業界の収益性が決まり、競争優位による優劣が決するからである。しかし、多くの企業は事業を多角化して複数の業界で競争している。そこで第5章「競争戦略から企業戦略へ」(邦訳Ⅰ巻・第5章)は、もう一つの重要なレベルでの戦略、つまり複数の事業に多角化された企業全体の戦略──私はそれを「企業戦略」(corporate strategy)と呼ぶ──を扱っている。
多くのケースで、多角化が事業レベルの競争戦略とは切り離された別個の問題として扱われている。しかし、この誤った二分法によって多くの多角化が悲惨な結果に終わっている。それを最初に論じたのがこの論考であった。多角化を検討する際に、多様な複数の事業で競争することの現実を見ようとしない企業には、しばしば悪いことが起こる。
第5章は、企業戦略は競争戦略とは異なる問題を含んでいるものの、二つの戦略には密接な結び付きがなくてはならないということを論じている。業界という視点から見ると、企業戦略とは、企業がどの業界で事業を行うべきか、どのようにその業界に参入すべきかの選択に関係している。競争優位の立場からは、企業レベルでの中心的な問題は、各事業単位の競争優位が他の部門によっていかに強化されているかである(損なわれるようなことがあってはならない)。
この章も、業界構造とバリューチェーンの概念を使って、これらの質問をもう一度掘り下げている。そして、多角化の戦略的ロジックを理解するにためには活動という概念をどのように使えばよいのか、多様化の成果を刈り取るためには企業戦略を組織体制と業務遂行にどのように結び付けなければならないかを示している。
この論考が最初に出版されてから久しい。企業が多角化を好む傾向はいまも続いているが、その結果には依然として問題が多い。事業ポートフォリオモデルには疑いの目が向けられるようになり、多数の企業で、多様化の根拠としてはコアコンピタンスやクリティカルリソースといった概念に取って代わられている。しかし、それらにしても単純化が過ぎるため、多角化の成果はいまも芳しくない。そうした経験から、事業レベルでの持続可能な競争優位と結び付かない多様化は、経済的価値を創出するより破壊する可能性が高いことがわかっている。
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]競争戦略論の第一人者マイケル E. ポーター(ハーバード・ビジネス・スクール教授)の「競争戦略論」の改訂増補新版。競争戦略、競争優位の戦略、企業戦略のエッセンスがこの1冊でわかる。経営者、ビジネスマン、経営学者の必読書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]先進国産業や企業の成功要因を徹底分析した新立地・集積理論「クラスター理論」や都市問題の解決策を論じるなど、競争戦略の可能性を広げる話題の論文集。国の競争優位、環境対応、都市問題、医療システム競争など企業の競争戦略を鳥瞰して再構築するための理論書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※本書は1998年発行の『競争戦略論Ⅰ』(原著はOn Competition first edition, 1998)の改訂新版です。原著がOn Competition Updated and Expanded, 2008として、first editionから3本の論文を削除して5本の論文を加え、さらに2本の論文を改訂したのに伴い、翻訳書の増補改訂新版としてⅠとⅡとに二分冊して発行しています。Ⅰでは、第1章が改訂、第4章と第6~9章が原著で加わった増補論文です。

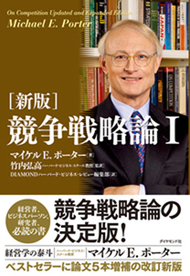





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









