
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
立地の競争力──グローバル化時代に高まる重要性
競争戦略と企業戦略の中心にある考えは、あらゆる競争状況を検証する際のベースになる。国境を超える競争においてもしかり。今日、競争はしばしば国境を超えて展開する。企業は、国レベル、地域レベル、そしてグローバルレベルの戦略を携えて、地理的に複数の場所をまたいで競争している。同時に、国や地域は、他の国や地域と競争して、企業が事業を展開しやすい環境を提供しなければならない。
複数の立地間で競争を行っている企業や国には、二つの新しい考え方が必要である。第一は、競争において立地が果たす役割についての認識である。国境を超えて競争する企業は、活動の場をどこにでも置ける能力を身につける。その際、場所が競争優位に及ぼす影響は、企業にとって死活的重要性を持っている。それは、政府が経済発展のための政策を立案するうえでも決定的に重要である。第二は、地域や国の境界を超えて、バリューチェーン内の活動をどのように分散させ、どのように調整すれば、競争優位を獲得できるかを理解するということである。バリューチェーンは、貿易や投資の障壁が撤廃され、新しい国が費用対効果の高いアウトソーシングを提供し始めるにつれ、かつてないほど国境を超えて広がっている。
『[新版]競争戦略論Ⅱ』に掲載されている第2部は、立地(location)の問題から始まる。本書第6章「国の競争優位」(邦訳Ⅱ巻・第1章)は、国や州やその他の地理的区分が持つ競争力に関する新しい理論を展開している。国の競争力についての議論は、ほとんどマクロ経済政策(政府の財政赤字、通貨政策、市場開放、民営化など)か、その国に備わっている投入資源(労働力、天然資源、資本など)による比較優位の議論に終始している。しかし、この章での私の主張は、立地の競争力は、主に立地が企業に提供する事業環境の性質に根差しているというものである。
これは従来の考え方とは非常に異なっている。労働や資本や天然資源へのアクセスは、もはや競争力の源泉ではなく、繁栄を約束してはくれない。なぜなら、それらはどこでも手に入るから。競争力は、企業が投入資源をどれほど効率よく使って、価値ある財やサービスを生産するかにかかっているのである。
ある立地での生産性と繁栄の可能性は、企業がどの業界で競争しているかで決まるのではなく、どのように競争しているかで決まる。ハイテクかローテクかとか、製造業かサービス業かといった昔ながらの区別は、製造とサービスの境界が曖昧になり、あらゆる業界が先進的な技術や高度なスキルを持つ人材を採用できるような経済においては、ほとんど意味を持たなくなっている。
この章は、企業の生産性は立地している国や地域の競争環境によって大きな影響を受けることを示している。この章は競争力のダイヤモンド理論を紹介する。ダイヤモンドには四つの主要な側面──要素条件、需要条件、企業戦略と競合状況、関連産業と支援産業──があり、政府の政策は、これら四つの側面のすべてにプラスまたはマイナスの影響を与える可能性がある(図式化すれば野球場のダイヤモンドのよう形になる)。この章は、競争力の源泉を掘り下げ、それがどう変化するか、政府と企業にどんな影響を及ぼすかを探る。ダイヤモンド理論は、経営者のためのツールであるだけでなく、政府のためのミクロ経済学的な経済発展のアプローチでもある。
本書第7章「クラスターと競争」(邦訳Ⅱ巻・第2章)は、私の競争力の理論体系の中で最も重要なアイデアの一つであるクラスター(cluster)の概念を追究している。クラスターとは、国や州あるいは都市に形成される、特定分野の企業、サプライヤー、関連業界、専門機関の地理的集中である。クラスターの例としては、金融サービスのウォールストリート、エンタテインメントのハリウッド、自動車の南ドイツなどがある。この章は、私が研究と実践の両面でクラスターについて学んだことに基づき、競争におけるクラスターの役割、政府の政策、企業の行動、諸機関(大学や業界団体など)にとってのクラスターの意味について論じている。
クラスターは経済先進国にあまねく見られる顕著な特徴であり、クラスターの形成なくして経済の発展はない。クラスターは経済と経済発展について考える際の新しい視点を提供し、企業や政府やその他の機関に新しい役割を与える。また、企業と政府、企業と大学の関係を構築する新しい方法を提供する。クラスターを形成するための取り組みが世界中で何百も立ち上がっており、この章では先進国と開発途上国の両方から事例の一部を紹介した。
本書第8章「複数の立地にまたがる競争」(邦訳Ⅱ巻・第3章)では、国境を超える競争の二つの側面──立地とグローバルネットワーク──を取り上げる。企業の活動とバリューチェーンは、一般論としての競争優位を理解するために重要な概念だが、それは国際戦略のための基本的フレームワークにもなる。国境を超える競争では、企業は立地の優位性をつかむために複数の国で活動することができ、分散した活動を調整してネットワークの優位性を活かすことができる。
第8章は、このフレームワークが特定の事業のグローバル戦略においてどのような意味を持つかを論じる。グローバル戦略は、本社やホームベース活動はイノベーションや生産性の利点を活用するためにクラスターが存在する立地に置き、それ以外の活動は各地に分散させて、低コストのインプットの調達や、海外市場へのアクセスを図るというものである。
調整(coordination)は、分散した一連の活動をグローバルネットワークに変える。グローバル戦略についての古い考え方は、世界で活動するという一点に注目していただけで、明らかに単純すぎた。場所は依然として重要であり、この章はグローバル戦略思考を次のレベルに引き上げることを目指している。また、グローバル戦略といっても、より一般的な地理間の競合の特殊なケースにすぎないことも明らかにした。全国レベルの企業になろうと努力している地方企業は、この枠組みを使えば適切な考え方を知ることができるだろう。
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]競争戦略論の第一人者マイケル E. ポーター(ハーバード・ビジネス・スクール教授)の「競争戦略論」の改訂増補新版。競争戦略、競争優位の戦略、企業戦略のエッセンスがこの1冊でわかる。経営者、ビジネスマン、経営学者の必読書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]先進国産業や企業の成功要因を徹底分析した新立地・集積理論「クラスター理論」や都市問題の解決策を論じるなど、競争戦略の可能性を広げる話題の論文集。国の競争優位、環境対応、都市問題、医療システム競争など企業の競争戦略を鳥瞰して再構築するための理論書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※本書は1998年発行の『競争戦略論Ⅰ』(原著はOn Competition first edition, 1998)の改訂新版です。原著がOn Competition Updated and Expanded, 2008として、first editionから3本の論文を削除して5本の論文を加え、さらに2本の論文を改訂したのに伴い、翻訳書の増補改訂新版としてⅠとⅡとに二分冊して発行しています。Ⅰでは、第1章が改訂、第4章と第6~9章が原著で加わった増補論文です。

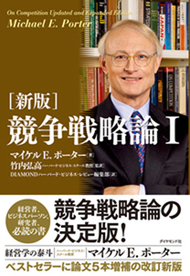





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









