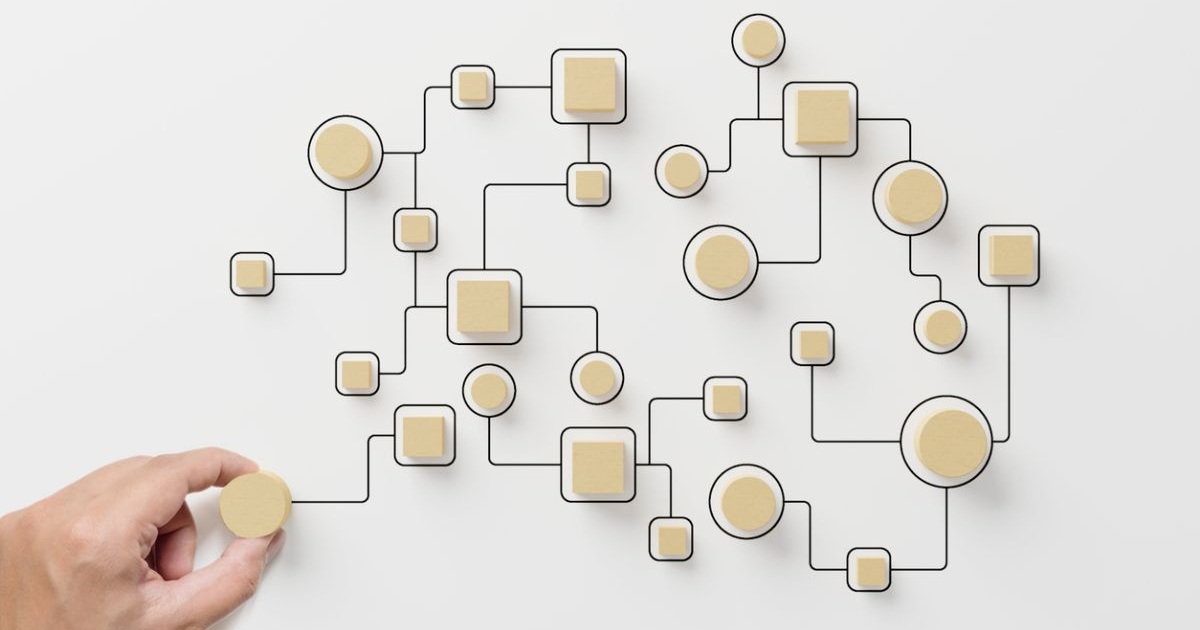
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
拡大する「競争」のフロンティア
本書『[新版]競争戦略論Ⅰ』と『[新版]競争戦略論Ⅱ』の読者には明らかであってほしいと願うが、私のすべての研究は、競争と価値創造についての中核的アイデアをめぐって展開されており、一貫した視点で貫かれている。一貫した中で、私のアイデアはもちろん常に進化し、時間の経過とともに広がり、新しい次元を取り入れてきた。
「五つの競争要因」は、業界構造が競争のフィールドのあり方を決定する、という考えを一言で表す略語として定着した。「バリューチェーン」は、企業の活動という視点から見た競争優位を示す略語となった。すなわち、高い収益性は、企業がコスト引き下げを可能にする活動か、より高価な料金を請求できる能力の違いによってもたらされるということである。「戦略的ポジショニング」と「業務効果」は、戦略の本質と、それが他のマネジメント課題とどう違うかを理解するための本質的な区別となっている。「ダイヤモンド」と「クラスター」は立地が競争に及ぼす影響のありようを一語で示す省略表現となった。これら一連の重要なフレームワークは、社会問題に関する著作も含め、私のすべての著作に顔を出している。個々の概念についての理解も、それらの間のつながりについての理解も、私の中でたえず深められ、拡張されている。
競争と戦略を研究する中で、一つの疑問が次の疑問、そのまた次の疑問へとつながっていった。単一の業界での競争と戦略から、多角化が業界の競争に与える影響へと関心が広がった。ポジショニングについての初期の研究がもとで、企業を活動という視点から見るようになり、そこから価値創造を考えるためのフレームワークが形づくられた。マネジャーにとって戦略立案と他の仕事は何が違うかを考えていた時に、戦略と業務効果の違いが見えてきた。
企業の活動について考えていると、グローバリゼーションの影響や地理的な活動の広がりについてもあれこれ考え始め、立地はどれほど重要なのかという疑問が生じた。場所に目を向けたことで、国や地域の競争力の源泉へと関心が広がり、企業だけでなく競争において政府が果たす役割についても考えるようになった。
国や地域社会を詳しく見ていると、競争と価値創造の原則を喫緊の社会的課題──環境の持続可能性、都市の貧困、質の高い医療など──の解決のために使うにはどうすればよいかという問題に引き寄せられた。財団や他のフィランソロピー組織を通じて配分される社会の資源が増えるにつれ、私はそのような組織が、どうすればもっと効果的になるかという問題に注目した。
時間が経つにつれ、分析対象とすべき新しい単位は何かということを考えるようになった。分析の単位は企業という考えが支配的だった当時、私は初期の研究において「業界」という分析単位を強調した。競争優位は企業全体から生じるのではないことが理解できると、その後の研究では企業の「活動」を強調した。マネジメントの研究が、もっぱら社内で起こっていることだけに目を向けていたころ、私は地理的「立地」を研究対象に加えた。産業政策といえば産業や国だけに目が向けられていたころ、私は「クラスター」の役割を強調した。医療分野では、主に保険、病院、診療所に目が向けられていたが、私たちの研究は、健康状態と診療サイクルこそ価値創造の本質を担う単位であるということを特定した。
新しい問題意識が生まれ、新しいアイデアを発展させる中で、私は以前のものを再検討するように導かれた。企業が行う活動を通して企業を見ることによって、一般的戦略についての以前の考え方を精緻化し拡張した。いまでは私は業務効果と戦略を区別しているが、その区別はそれ以前の研究に立脚しており、区別することで得られた情報をそれ以前の研究に返している。新しい理論によってポジショニングについての私の理解は深まり、それをより密接に活動に結び付けることができた。この新しい研究では、「トレードオフ」と「適合」というコンセプトを通して活動ベースの企業観を拡張することができた。
業務効果とポジショニングの区別は、他のさまざまな問題にも新たな光を当てた。たとえば、金融市場からの圧力は業務効果の改善を促す望ましい動機を生む可能性があるが、企業は真の優位性を持たないセグメントでの成長を追い求め、ユニークな戦略ポジションをしばしば傷つけている。
もう一つの例は、競争におけるITの役割の評価に関連するものだ。新しいITの多くは、ユニークなポジショニングを可能にするための努力にではなく、ベストプラクティス(つまり業務効果)の向上に向けられている。新世代のITツールの潜在的な危険性は、あまりにも多くの企業が同じ方法でそれを適用しようとしているところにある。これは、意図せざる競争の均質化を招き、顧客の選択を制限し、相互に破壊的な競争を誘発するだろう。
立地に関する研究も、重要な新しいつながりを開拓した。それが最もわかりやすいのはグローバル戦略のコンセプトが充実したことだ。立地という要因は、業界構造と競争優位に明らかに影響を及ぼし、実現可能な競争の形態に影響を与える。ダイヤモンドの状態とクラスターの深さは、業界への参入障壁を上げ下げし、顧客やサプライヤーの力を変え、代替品の組み合わせや脅威の程度を設定する。
立地は、国の経済において生じる競合状況にも影響を及ぼす。開発途上国における模造品や価格競争から、先進国におけるイノベーションや差別化に至るまで、競合状況にはさまざまなものがある。途上国では、立地の欠点が、魅力的な産業への企業の参入を難しくし、価格競争の激化を避けにくくしている。政府による介入と資本不足がしばしば競争要因を抑え込み、独占状態を継続させてしまうのも途上国にありがちな問題である。
さらに立地は、競争優位にも強く影響し、企業が選択する戦略のタイプや、導入して成功する戦略のタイプにも影響を及ぼす。地元のインフラの現状、現地従業員のスキルといったダイヤモンドの条件は、業務効率に直接的に影響する。ダイヤモンドの諸条件(現地ニーズの洗練度、ユニークなスキル・プール、関連産業の有無など)は、戦略的ポジション(顧客セグメントや製品のバラエティなど)のタイプや多様性に影響を与える。立地のビジネス環境は、戦略の選択に影響を与えるだけでなく、その戦略を実行する企業の能力にも影響を及ぼす。活動レベルでは、企業の独自性に大きく貢献する多くの経営資源、能力、スキルをどれだけ調達できるかは、明らかに立地の性質に依存するのである。
立地は企業戦略にも影響する。ダイヤモンドの条件は企業が提供する付加価値──それが競争優位に真の影響を及ぼす──に影響を与える。開発途上国では、親会社の資本提供能力とプロフェッショナルなマネジメントを導入する能力によって、価値が創出される。多くの新興経済国で大手コングロマリットが優勢なのはその理由による。先進国では、事業のポートフォリオマネジメントはわずかな価値しかもたらさず、事業の多角化のためには他のアプローチが必要である。ロジスティックスシステムやサプライヤー産業などのダイヤモンドの条件は、その立地でどのようなシナジーが生まれるかを決める。
多くの読者は、戦略に関する私の研究と、立地に関する私の考えとの間に明らかな矛盾があることに気づいている。まず、業界構造のフレームワークは、強力な買い手とサプライヤー、そして厳しい競合関係は収益性を押し下げることを示している。次にダイヤモンド理論は、地元の競争、要求の厳しい顧客、洗練された地元のサプライヤーが、高い生産性と迅速なイノベーションを刺激しサポートすることで競争力を育てると示唆している。どうすれば、この二つの視点に折り合いをつけることができるだろうか。
まず、単一の立地にある業界とグローバルな業界を区別する必要がある。一つの立地に好ましいダイヤモンドが存在すれば(地元の厳しい競合関係を含む)、そこに拠点を置く企業は、全体として見れば高いレベルの生産性を達成し、他の場所に拠点を置く企業よりも速く進歩する。現地市場での収益性は低いかもしれないが、そこに拠点を置く企業は世界的に見て優れた収益性を実現することができる。
折り合いをつけるもう一つの方法は、ある場所に拠点を置く企業が他の場所に拠点のある企業よりも競争優位をつかむ能力は、ダイヤモンドの状況によって左右されることを認識することである。しかし、業界の収益性の世界平均は、世界におけるその業界の平均的な構造に依存している。
立地に関する研究は、生産性を決定する要因を扱い、競争力のダイナミックな改善の重要性を強調する。業界構造のフレームワークと企業活動のフレームワークは、企業とその市場を理解するための知的枠組みを提供する。私の初期の探究は、より横断的なものであった(たとえば、ある時点である業界が他の業界より高収益なのはなぜか、ある企業が他の企業よりも高収益なのはなぜか、といった疑問に答えようとした)。これらは論理的な最初の質問であった。
しかし、業務効果とポジショニングについての最近の研究では、私はポジショニング、立地、ダイナミックな改善を結ぶ橋を構築しようとしている。それは、業務効果を改善し続ける必要性を強調する一方で、戦略を継続させる必要性を強調する。業務効果と戦略は、いずれも立地の影響を受ける。
社会問題を解決する競争の力
競争と価値創造を深く理解し、立地の研究によってその理解がさらに充実したことによって、競争と社会問題の関係という新しい研究のフロンティアが現れた。経済の競争力と社会の進歩は調和させることができ、同時に改善することができる。社会組織は価値創造の原則を受け入れることでパフォーマンスを向上させることができる。価値の創造をめぐって競争が行われるようになれば、社会的セクターは急速に進歩するだろう。
最後に、競争と社会問題の関連を理解しようとする過程で、私はフィランソロピー・セクターに目を向けるようになった。それは急速に成長しているセクターで、そこに注ぎ込まれている資源も急拡大している。山積する社会問題を解決する政府の能力には限界があることが認識されたいま、このセクターの活動を、社会に大きな価値をもたらすような仕方で展開することは喫緊の課題である。
まだまだ見出すべきつながりがある。競争と価値創造についての私の学びは、当分止まることはないだろう。ビジネス環境とテクノロジーに現れている多くの変化は今後、理論と実践に組み入れられていくだろう。そんな変化の一つが企業と資本市場の関係で、ほとんどの資本は個人による長期保有株ではなく、活発な売買を行う機関投資によって所有されるようになった。もう一つの展開は、経済戦略と社会戦略の融合であり、市場の枠組みの中で社会目標(たとえば環境保護)が追求されるようになった。しかし、そうしたトレンドは、それ自体が価値創造のカギを握っているわけではない。価値創造は、組織とその文脈を広く全体的に見る能力によってもたらされるのだ。戦略思考はこれまで以上に稀少で貴重なものになるだろう。
未来がどうなるかはわからないが、確かなことが一つある。それは、競争がこれからも進化し続け、我々の繁栄を時に揺さぶりながら、繁栄の多くをもたらす源泉となるということである。私の長年にわたる論考を集めた本書から、読者が一つのことを感じ取ってくださるとするなら、よりよい世界──企業と社会の両方にとって──を創造する競争の圧倒的なパワーであることを願いたい。
* * *
本連載は今回で最終回である。ポーター教授が追究してきた「競争」と「価値の創造」の全体的な成果は、ぜひ書籍『[新版]競争戦略論Ⅰ』と『[新版]競争戦略論Ⅱ』で確認していただきたい。
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]競争戦略論の第一人者マイケル E. ポーター(ハーバード・ビジネス・スクール教授)の「競争戦略論」の改訂増補新版。競争戦略、競争優位の戦略、企業戦略のエッセンスがこの1冊でわかる。経営者、ビジネスマン、経営学者の必読書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]先進国産業や企業の成功要因を徹底分析した新立地・集積理論「クラスター理論」や都市問題の解決策を論じるなど、競争戦略の可能性を広げる話題の論文集。国の競争優位、環境対応、都市問題、医療システム競争など企業の競争戦略を鳥瞰して再構築するための理論書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※本書は1998年発行の『競争戦略論Ⅰ』(原著はOn Competition first edition, 1998)の改訂新版です。原著がOn Competition Updated and Expanded, 2008として、first editionから3本の論文を削除して5本の論文を加え、さらに2本の論文を改訂したのに伴い、翻訳書の増補改訂新版としてⅠとⅡとに二分冊して発行しています。Ⅰでは、第1章が改訂、第4章と第6~9章が原著で加わった増補論文です。

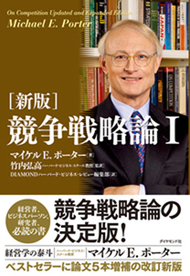





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









