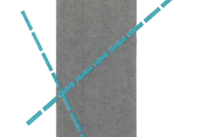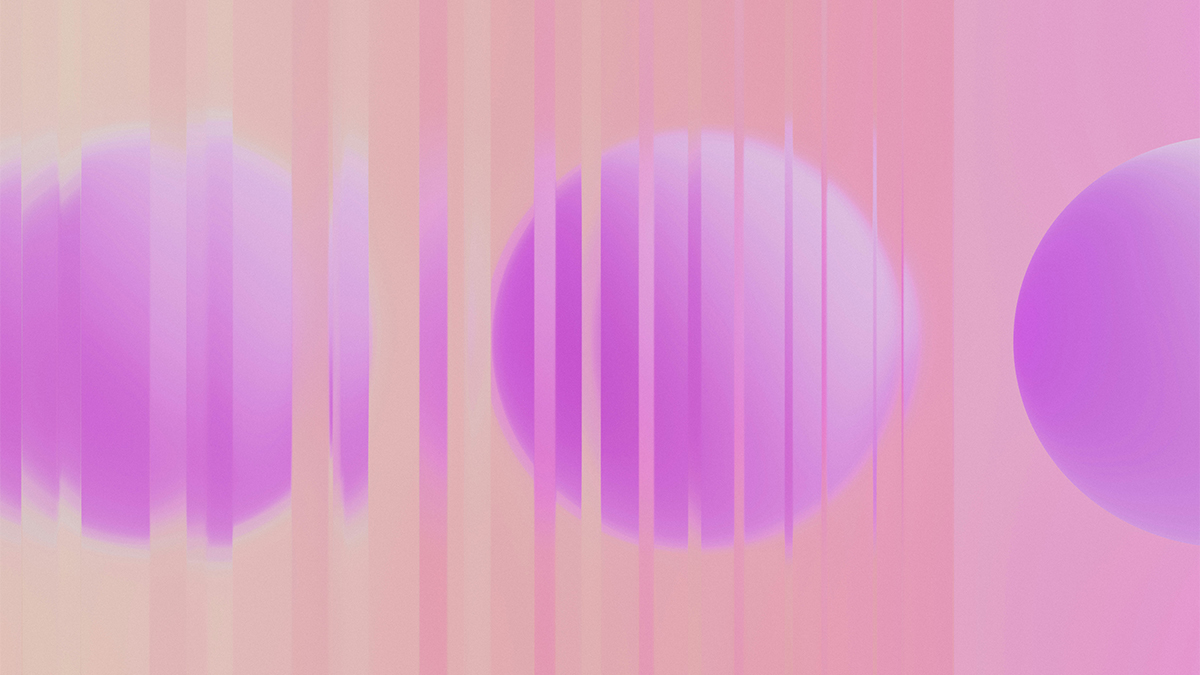
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
調達プロセスのデジタル化に成功した世界的企業
多くの企業が、特にAIのような新興テクノロジーを活用して、調達プロセスを迅速にデジタル化しようという野心的な計画を掲げている。このことは、筆者らが2024年10月にデジタル・プロキュアメント・ワールドと共同で、世界各地の調達部門の幹部200人以上を対象に実施した調査からも明らかだ。
一方で、調達部門の幹部20人以上と、サプライチェーンおよびIT部門の幹部数人に行った個別のインタビューでは、こうした計画の実現を阻む障害もいくつか浮かび上がった。そして、これから紹介する3社が、そうした障害を克服することに成功した手法も確認できた。
・世界的なエネルギー関連企業であるBPの「調達テクノロジー・ガレージ」は、複数のスタートアップが提供する新興テクノロジーを同時かつ迅速に調査して、それらの投資対効果の見込みを事実に基づいて把握する。
・オットー・グループ(ドイツのハンブルクを拠点とするEC・小売大手で、傘下に米インテリア・日用品ブランドのクレート・アンド・バレルやファッション通販のボンプリーなどを擁する)の「ニュー・テクノロジー・ベンチャーチーム」は、スタートアップや新興テクノロジーとの連携を強化して、実証実験やアプリケーションの共同開発を加速している。
・ウォルマートには、調達テクノロジーの「センター・オブ・エクセレンス」(CoE)があり、実証済みのテクノロジーをグローバルに大規模展開し、投資対効果を最大化することをミッションに掲げている。
新しいアプローチの必要性
筆者らが発見した大きな障害の一つは、従来のIT投資と導入プロセスである。「IT部門が管理する従来の契約交渉のプロセスは、スタートアップの環境には適していない」と、オットーの新興テクノロジーのベンチャーチームを率いるアルノ・バルトルシャットは語る。
従来のアプローチ──大手ベンダーを軸に長期にわたる交渉と契約手続きを伴うもの──は、スタートアップが開発する有望なデジタルイノベーションの調査に適していない。多くの企業が50ページを超える硬直的な契約テンプレートを使い、契約の最終化までに数カ月かかることも少なくない。これはスタートアップとの協業には過剰であり、遅すぎる。
こうした契約の硬直性は──予想される効果と事前に定められた展開計画に基づいて、一つのテクノロジーに複数年コミットする契約も少なくない──関係性の中からイノベーションが生まれる可能性を制限する。さらに、新興テクノロジーの潜在能力を最大限に引き出すためには実験的な導入が必要なことも無視している。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)