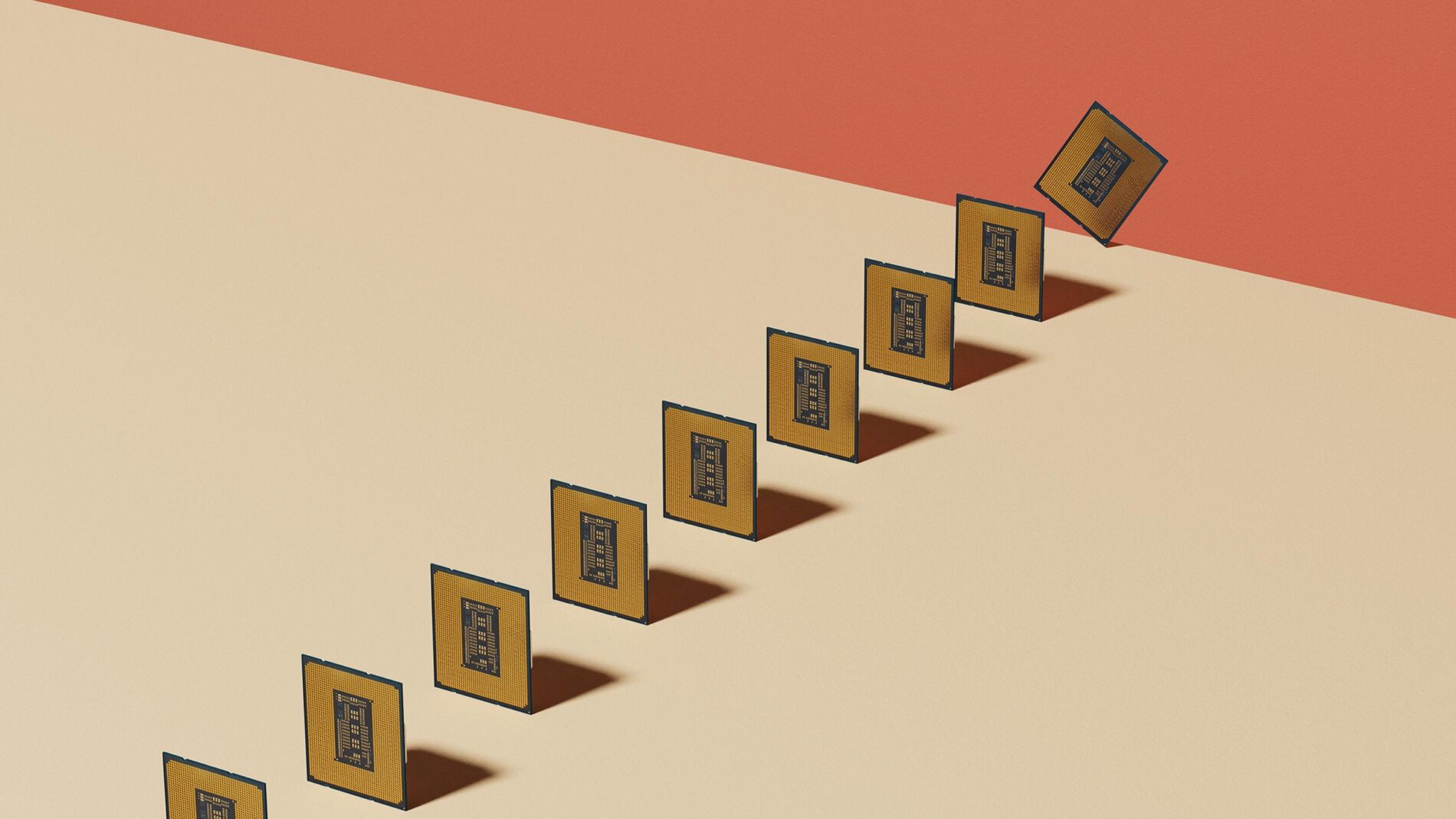
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
生成AIで真の価値を引き出す実践的なフレームワーク
ビジネス界で生成AIがパイロット段階から本格的な導入の段階へ移行し、数値に表れる成果が生まれ始めている中で、既存企業の多くが壮大な野心を実際の成果に転換させることに苦労している。生成AIの導入は増加しているにもかかわらず、ROI(投資利益率)の面でお粗末な結果になっているのだ。生成AI戦略の複雑性とその成否がビジネスに与える影響が著しく大きいという性格が、浮き彫りになっているといえるだろう。
いまビジネスリーダーたちは、決定的に重要な問いをいくつか突きつけられている。戦略面のインパクトを最大化させるには、どの領域で生成AIを集中的に用いればよいのか。長い目で見た場合の強みを生み出すために独自のシステムを開発することを優先すべきなのか、それとも素早く導入するために既成のツールを利用すべきなのか。導入の迅速さと、安定性や信頼性、コンプライアンスのバランスを取るには、どうすればよいのか。そして、自社の生成AI戦略を計画実行の方策とどのように連携させれば、変革を成し遂げ、数値にはっきり表れるインパクトを生み出せるのか。
これらは、単なる技術上の問題ではない。それは、ライバル企業に差をつける企業と後れを取る企業を分ける戦略上の選択に関わるものである。そうした戦略の選択は、2つの基本的な問いから出発する。その問いとは、「我が社の生成AI戦略はどのようなものであるべきか」「どうすれば、その戦略を有効に実行できるのか」というものである。
これらの問いに答えるためには、単に実験するだけでは十分でない。優先順位を明確にし、規律を持って戦略を実行する必要がある。優先順位を明確にするとは、以下の4つの領域におけるトレードオフの関係に適切に対処することを意味する。具体的には、ユースケースと戦略上の目標のすり合わせ、システムを構築するか購入するかの選択、リスクの度合いの調整、スピードと安定的なオペレーションのバランスの4領域である。一方、戦略実行の柱になるのは、強力なデータの基盤、拡張可能なインフラ、責任あるガバナンス、組織の準備態勢、そしてターゲットを絞った能力構築だ。
2024年、筆者らは膨大なアーカイブとメディア報道、オンラインレポートを分析して、100件に上る生成AIのユースケースに関してデータを構築した。業種は、ロジスティックス、金融、ヘルスケア、エネルギー、小売りなど、多岐にわたる。この分析の結果、AIシステムの採用、戦略的ポジショニング、導入方法の決定、実行を支える組織モデルに関する主要なパターンが見えてきた。
筆者らはそうしたインサイトをもとに、企業が戦略を構築・実行して真の価値を引き出すための実践的なフレームワークを編み出した。そして、現実世界での生成AIの導入について企業幹部たちと議論を重ね、既存企業と協働することを通じて、そのフレームワークに磨きをかけていった。
生成AI戦略を形づくる
既存企業のリーダーたちは、ポートフォリオをめぐる新しいタイプの課題に直面している。これまでのデジタル・トランスフォーメーション(DX)はITの近代化やプロセスのデジタル化が中心だったが、生成AIはより複雑でより多面的な課題を生み出している。ここで優先順位を的確に判断するためには、期待できる便益とコストへの影響のバランス、そしてリスクの度合いと導入ペースのバランスを取らなくてはならない。
期待される便益とコストへの影響のバランス
AIのユースケースを戦略的な目標とすり合わせる必要がある。賢明な企業は、生成AIを活用して、インパクトの大きな問題を解決し、明確なリターンを得ている。
小売大手のカルフールは、在庫管理のスマート化を実行し、廃棄される商品を減らして利益率を引き上げることに成功した。製薬大手のノバルティスは、臨床試験設計のスピードを向上させた。チューリッヒ保険は、加入審査で用いる言葉を平易なものにすることにより、コンプライアンスと信頼を改善させ、スピードと生産性の面で目に見える成果を上げた。ネットフリックスやワーナー・ブラザース・ディスカバリーなどのクリエイティブ系企業は、生成AIを活用して、コンテンツのローカライズを行ったり、台本の要約をつくったり、新しいアイデアを模索したりして、生産とイノベーションを加速させようとしている。
効率性を追求するにせよ、イノベーションを追求するにせよ、カギを握るのは、どのような価値を引き出したいのかをはっきりさせ、その目標に直接資するユースケースを選ぶことだ。
企業は、生成AIを導入する場合、ソリューションを自社で構築するか、既成のソリューションを購入する必要がある。そのための投資は、しばしばかなり大がかりなものになる。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









