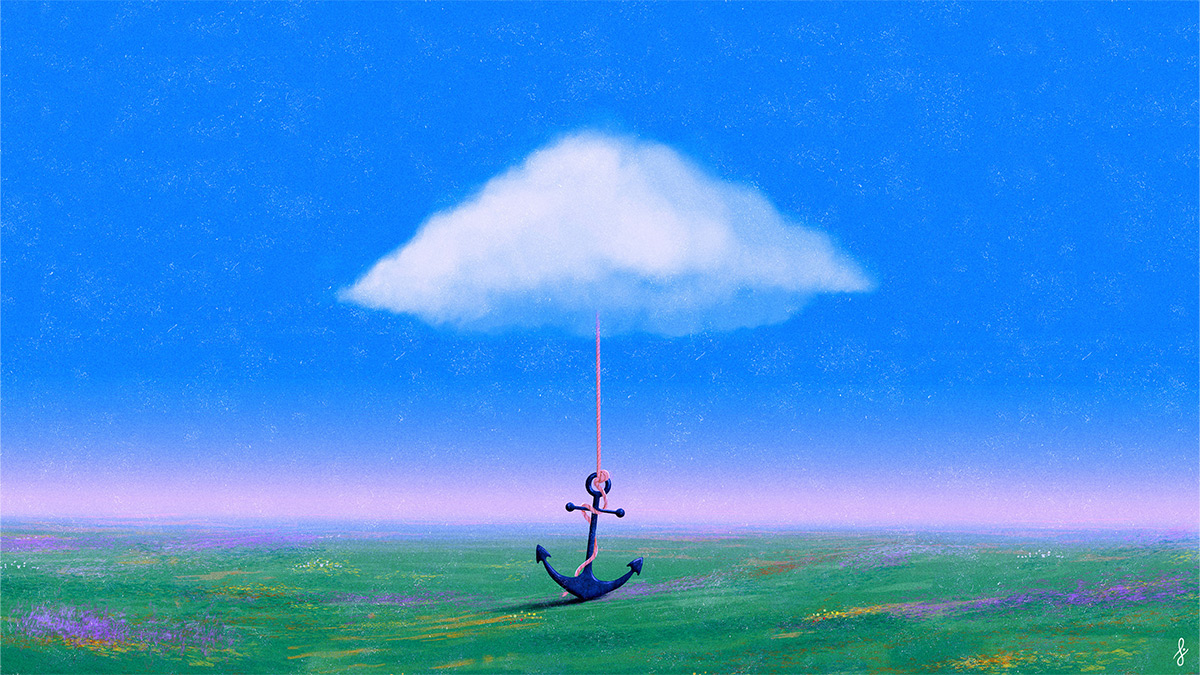
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AIを導入する企業が直面する課題
AIがビジネスのやり方を根本的に変えるという見解には、ほとんど異論がない。だが、ほとんどの企業はまだAIへの取り組みから実質的な効果を得られていない。ボストン コンサルティング グループ(BCG)が20以上の業界の経営幹部1000人を対象に行ったグローバル調査では、AIによって価値を創出し、同業他社よりも平均45%のコスト削減と60%高い収益増を達成した企業はわずか26%にとどまっていた。
なぜ、このような失望させる結果となったのだろうか。この調査によると、AIの取り組みの導入に当たって企業が直面する種々の問題の中で、人材とプロセスに関する問題が70%を占めている。たしかに企業はデータ品質の低さ、統合の複雑さ、インフラのコストといった技術的障壁にもぶつかるが、この調査結果は、何百もの企業と協力してきた筆者らの集合的経験とも一致している。すなわち、最大の障壁は、新しい仕事のやり方に適応し、再構築し、規模を拡大する企業の能力にある。筆者らはこの能力を「変化へのレジリエンス」と呼ぶ。
なぜ変化へのレジリエンスが不足しているのか
従来、組織変革は断続的なものだった。システムを最新化し、人材を訓練し、次の混乱の波が訪れるまで安定した環境で活動していた。ところが、いまやAIは大半の企業の適応能力をはるかに超えるペースで進化し、変化は容赦なく続いている。
ビジネスリーダーは、AI変革を従来のロードマップに定着させたり、従来の手段を使って経営変革の取り組みを推進したりすることが難しいと気づいている。5カ年戦略はもはや通用せず、年間計画のサイクルでも変化に追いつかない。財務、リスク、法務に関する従来の管理方法は、新たなタイプのリスクの発生に対して後手に回るばかりだ。固定的な運営モデルは重荷となる。比較的新しい仕事のやり方、たとえばソフトウェア時代の台頭により広く取り入れられたアジャイル方式でさえ、十分に対応できない。この不安定な環境では、リーダーはたえず変化することを受け入れる必要がある。さもないと、無為のまま時代に取り残されてしまうか、いたずらに目新しいものを追い求めてバーンアウトするだろう。
変化へのレジリエンスとは、企業が急発展するテクノロジーがもたらす機会を捉え、脅威に先手を打てるよう備える組織能力である。それは、次々に襲う混乱を価値創造の反復可能な学習ループへと転換する、企業全体での反射的な反応である。それには3つの力を使う。
・感知:テクノロジー、競争、社会における小さな兆候を早期に感知する能力
・再構築:人材、データ、資本、決定権を、四半期単位ではなく日単位や週単位で再配置する能力
・固定化:次回の取り組みが一からのやり直しではなく、より高いベースラインから始められるように、チームが学習したことを(プロセス、規則、方針において)体系化する規律。
これらの力を一緒に動かすことで、企業の代謝スピードは、AIの急速な発展と歩調を合わせることができる。
ECプラットフォームを提供するカナダの企業である、ショッピファイ(Shopify)はまさに変化へのレジリエンスを発揮した好例だ。既存のオペレーションにAIをつけ加えるのではなく、自社を再構築し続けることによって、次に起きることに先手を打っている。
2023年、ショッピファイは商品のイノベーションに再び集中するため、長年かけて築いたロジスティックス部門全体を分社化するという大胆な決断をした。このリセットのおかげで、ショッピファイは、マーケティングのコピーから営業のインサイトまであらゆる面で起業家を支援する組み込み型アシスタント「サイドキック」のようなAIネイティブ機能を短期間でローンチすることができた。
複雑さを削ぎ落とし、過去の方向転換からの学びを体系化したショッピファイは、スピードと集中力を高め、デジタルコマースの進化する期待を反映したツールを100万社以上に提供することができた。新しい働き方を感知し、再構築し、固定化する能力によって、ショッピファイは単なるAI導入企業ではなく、AI時代において繁栄するために絶えずみずからを変革し続ける企業として位置づけられている。
あなたの会社が変化へのレジリエンスをどの程度備えているかを把握するには、次の質問に答えてみよう。
・予算や組織図を抜本的に見直すことなく、動きが速く優先度の高い取り組みに従業員を再配置して、技術的な能力の変化に対応できるか。
・いま、チームのメンバーがアイデアを持っていたら、実験を開始できるモチベーション、アクセス、ツール、サポートがあるか。
・実験して可能性があることがわかった時、その規模を拡大して企業全体に組み込むための明確な経路があるか。
・失敗を学習機会として捉え、次回に活かすためにオープンに情報を共有しているか。
これらの質問の大半に「はい」と答えられないならば、あなたの会社には、AI戦略を持続的なパフォーマンス向上へと転換するために必要な変化へのレジリエンスがまだ備わっていないことを意味する。
変化へのレジリエンスを高める5ステップ
以下は、変化へのレジリエンスを高めるために、リーダーや組織が実行すべきステップである。
1. 学習する:ツールセット、マインドセット、スキルセットを理解する。
ツールセット、マインドセット、スキルセットの弱点を洗い出すためには、従業員にAIに関わらせ、実験を始めることが重要だ。そうした実験を通して、自社がどのようにプロセスを再考できるかについて直観を養う。同時に、失敗したパイロットプロジェクトに罰を与えるような企業文化の障壁や、データへのアクセスに1カ月かかるような技術的ボトルネックを特定して取り除く。
アクセンチュアでは、まず営業から人事に至るまでのあらゆる部署に、何か一つのペインポイントを解決するマイクロアプリを作成することを奨励した。この「サンドボックス」方式によって、10カ月以内に300の生成AIアプリが作成された。その大半は提案書の下書き作成を支援するものや会議録を要約するものなど、特定のタスクを手助けするシンプルなツールだった。作成したチームが各アプリを所有するため、従業員はAIが日常業務をどのように変えるかをただちに確認でき、受動的に導入する文化から積極的に試してみる文化へと変容した。
アクセンチュアは参加を促進するために、従業員25万人に生成AIのスキルを訓練し、安全にデータを扱って試せる環境をすべての学習者に提供している。初期の分析では、こうした小規模な試みの重要性が示されている。すでに生成AIによって、労働時間が12%削減され、アウトプットの質が8.5%高まり、より大きな変革への弾みとなっている。
2. 実行する:ターゲットを絞った介入を開始する
変化へのレジリエンスの個々のギャップに対し、四半期単位ではなく週単位で勢いを生み出せる最小限の動きで対処しよう。リスクを敬遠する企業文化ならば、「小規模な試み」を導入する。
たとえば、10日間の実験を行い、結果ではなく学びを称賛する儀式をする。スキル面で遅れているなら、特定領域の専門家とデータサイエンティストをペアにして期間終了までに実用的なAIコンセプトを完成させる、コホート型のスプリント(短期間の集中的作業で成果を出す手法)を実施する。その成果は能力と可能性の証明にもなる。もしツールセットが障害となっているなら、安全かつ自由にデータを扱って実験できる場やローコードのワークフロービルダーを導入して、チームがアイデアを試せる環境を整える。ある戦術で顕著な成果が出たら、それをプレーブック、再利用可能なコード、改訂方針に体系化し、そのテンプレートを社内全体に展開する。
シンガポール拠点のDBS銀行は、月1回の「ノーススターとフィードバック」という儀式を設定した。そこでは文化やスキル、ツール面の摩擦を明らかにし、最大の課題に取り組ませるために機能横断的な「小部隊」を任命する。ある初期調査で、手作業の引継ぎが融資承認を遅らせていることが明らかになった。数週間以内に新たなAIによる信用評価ワークフローが導入され、現在では年間約38万件の融資申請を処理し、手作業を85%削減している。また同じような小規模介入をきっかけに、350のユースケースで800以上の本番稼働AIモデルが生まれ、2024年だけで推定5億6300万ドル相当の経済価値を創出した。成功した取り組みはすべてDBSのデジタルアカデミーによって同行全体のプレーブックに体系化され、各実験のサイクルごとに組織の変化へのレジリエンスが目に見えて向上している。
3. 構想する:チームを新たなスタートに挑戦させる
古い運用モデルを刷新するのではなく、新しいモデルを開発しよう。未来の職場の機能は現在と同じではない。AIを活用する組織は、まったく新しい職務、ワークフロー、価値提案を持つようになる。
モデルナはテクノロジーと人事の部署を合併して、一つの部門にし、そうした創造性を体現した。狙いは、人間に最も適したタスクと自動化できるタスクを区別して、仕事の責任を再定義することにあった。オープンAIとの提携に影響を受けたこの戦略的取り組みによって、治験や人事オペレーションなど多様なビジネス機能に対応する3000以上のカスタマイズされたAIエージェントが作成された。その結果、職場のダイナミクスや人事とテクノロジーの役割は根本から新しく生まれ変わったのである。
4. 実行する:測定、学習、再投資の継続的なサイクルを受け入れる
新しいテクノロジーへの期待がピークに達した後に訪れる幻滅期で、立ち往生してはいけない。あらゆるテクノロジーの波には、過剰な期待と真の戦略的可能性が伴う。したがって、早く動き出し、速やかに学習し、前進し続けることが大切だ。
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)は変化へのレジリエンスを継続的な能力として捉え、ツールセット、スキルセット、マインドセットのすべてにわたって測定可能な成果を生み出す機運を醸成した。同社のカスタム生成AIプラットフォーム「チャットPG」には、現在、3万人以上の従業員が参加し、35以上の本番環境でのユースケースを支えている。マーケティングでは、コンセプトテスティングのサイクルを月単位から日単位に短縮し、コストを大幅に削減した。サプライチェーンのオペレーションでは、AIと工場の現場センサーを組み合わせたパイロットプロジェクトによって、すでにP&G傘下のジレットの施設で完全自律型シフトが実現されている。これは同社のCFOが20億ドルの生産性向上を見積もる広範な計画の一環である。
スキル面ではAIリスキリングを導入し、従業員200人の最初のコホートは4400以上のバッジと約90の認定資格を取得し、学んだことを多数のデジタル施策に応用した。P&Gはこうした指標によってアップスキリングを事業の成果に直接結びつけ、それに沿って学習への投資を最適化している。
文化面では、正式な研修(10%)、メンターシップ(20%)、実地体験(70%)を統合した「スクール・オブ・P&G」によって、成長マインドセットを強化している。また、AIを活用して、個人の目標や行動に即したコンテンツや進め方を推薦し、学習をさらにパーソナライズしている。社内調査によると、この方法によってエンゲージメントスコアが向上している。P&Gは思い切った取り組み、迅速な学習ループ、ターゲットを絞った再投資を組み合わせることによって、AI実験を企業全体のパフォーマンス向上へと転換している。
5. ケアする:人間のウェルビーイングを変化の中心に据える
急激な変化は、どんなに優秀な人材であっても疲弊させてしまうことがある。ウェルビーイングへの周到な配慮がなければ、新しいテクノロジーへの熱狂はたちまち疲労や抵抗へと変わってしまう。だからこそケアとは、従業員が新しい仕事のやり方を学んでいる間、心理的安全性を築き、リアルタイムで感情をモニタリングし、従業員の健康と熱意を維持するのに必要なリソース(時間、コーチング、柔軟性)を提供することに重点を置くことである。リーダーがウェルビーイングのデータを財務指標と同じように厳格に扱えば、従業員を守れるだけではなく、競争優位を生み出すイノベーションの活用を加速できるだろう。
シスコシステムズの事例は、従業員の身体的・精神的・社会的ニーズを満たすことが、デジタル変革を遠ざけるのではなく、むしろ加速させることを示している。2024年に、同社では従業員の84%が総計230万回のチーム・チェックインを記録し、リーダーは彼らの感情や作業量をリアルタイムで読み取ることができた。同時に、シスコはAIボット「ウェルネスト」を導入し、身体的・精神的・経済的・社会的ウェルビーイングのために個別最適化されたリソースを提供した。こうした全人的なサポートによって、AIパイロットプロジェクトを社内全体に拡大しながら、高いエンゲージメントを維持することができた。これは、従業員へのケアが、持続的でレジリエントな変革を実現するために欠かせない条件であることを示している。
* * *
リーダーが変化へのレジリエンスを受け入れた時、たえず適応し続ける好循環が生まれるだろう。それによって、個々のAI実験がスピードアップし、再構築が容易になり、成功例は規模を拡大しやすくなる。ショッピファイ、DBS、モデルナ、P&Gなどの企業の例は、変化が単なる反応ではなく企業の力となった時に何が可能になるかを示している。
逆に、AIを一回限りのアップグレードと捉える企業は、古いモデルを維持するために新しいツールを利用するという落とし穴にはまってしまう危険がある。今日のAI時代では、先行者とすぐ後ろを追随する者との隔たりは大きく広がりつつある。その差はテクノロジーへのアクセスではなく、変わり続けることへの勇気と規律なのだ。
"A Guide to Building Change Resilience in the Age of AI," HBR.org, July 29, 2025.

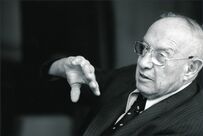





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









