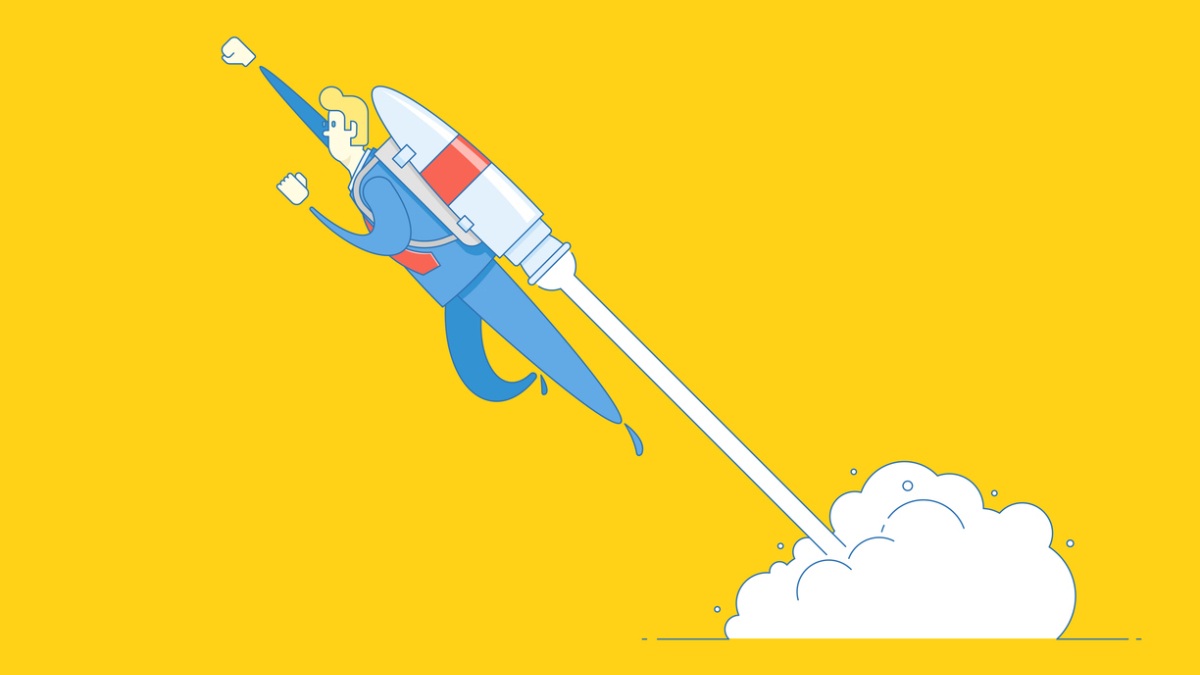
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
指示待ち傾向が強く、みずから動こうとしない部下とどう向き合うか
VUCAと表現される変化が目まぐるしい現代にあっては、上司の指示や命令を待って部下が動くようでは、組織として迅速かつ的確に対応することはおぼつかない。組織の持続可能性を高めるためにも、部下がみずから考え行動することで成果を挙げていく組織づくりが重要な課題となっている。
ところが、現実の組織では、個人の業績が評価される一方で、責任を問われる成果主義的人事考課が浸透した結果、従業員の間で失敗を避けようとする意識が高まっている。それゆえ、やるべきことを明瞭に指示してほしいという部下の指示待ち傾向がむしろ強まっており、部下に自律的に動くことを期待するのは容易ではない。まるで自分の役割と責任という「タコ壺」に入り込んでしまったかのような部下が増えているのが実情だ。上司は、そのような部下の態度を見ると、叱責したり、叱咤激励したりして、つい力任せに部下を動かそうとしてしまうことがある。しかし、そのような力任せの関わり方でどれほどの効果が期待できるだろうか。
タコ漁では、タコが壺に入り込んで出てこない時、海水よりも塩分が濃い塩水を壺に流し込むことで、タコが自分から壺を出てくるように仕向けるそうである。そうした現場の知恵を手がかりに工夫を凝らせば、力任せに引っ張り出さなくても、部下がみずから動いてくれる効果的な戦略がありそうなものである。
部下の自律性・自主性を引き出す効果的な戦略とはどのようなものなのかを考える時、組織に「心理的安全性」を醸成して、信頼と理解に基づく部下との関わり方を構築するアプローチに重要なヒントが潜んでいると思われる。本稿はそうした視点から論考していく。
部下との関わり方はけっして「戦」(いくさ)ではないものの、相手があることを考えれば、孫子の兵法にある「彼を知り己を知れば百戦殆(あや)うからず」という考え方は示唆に富む。ここでは、部下の自律性や自主性を引き出すことにつながる考え方や言動の取り方を、上司が戦略的に選択するという視点に立って論を進めることにしたい。
ステップ1:自分のリーダーシップタイプを把握する
部下との関わり方を戦略的に検討する時、すぐに「部下をどう変えるか」を考えてしまいがちだが、その前に、おのれを知ること、すなわち「自分はどのようなリーダーなのか」を客観的に理解することが大切である。ことあるごとにタコ壺に入ってしまいそうになる部下を相手に、その自主性や自律的を引き出せるか否かは、ひとえに上司の思考や言動が、部下の「よし、自分で考えてやってみよう」という思いを刺激し、その実践を後押しする特徴を持っているかどうかにかかっている。
上司が「自分はどのようなリーダーなのか」を客観的に把握する際には、リーダーシップ研究において開発されてきたリーダーシップスタイル評定尺度が役に立つ。優れたリーダーシップとは、「課題達成を指向した行動」と「メンバーの円満な人間関係を指向した行動」の双方を高いレベルでバランスよく実践することだという点は、数多くの理論が共通して指摘するところである。これらの理論の代表である三隅二不二(注1)のPM理論では、前者を「目標達成行動」(performance:P行動)、後者を「集団維持行動」(maintenance:M行動)と呼んでいる。そしてP行動を水平軸に、M行動を垂直軸に組み合わせて、リーダーシップを4つのタイプに分類するモデルを提唱している(図参照)。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









