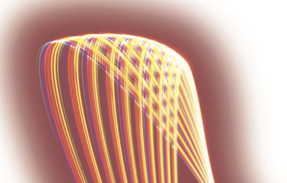-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
思考停止状態のeプライシング
eコマース(電子商取引)において商品やサービスの価格をつける場合、これまではたいてい、両極とも言える2つのアプローチが採られてきた。実はいずれも、およそ戦略的とは言えない代物だった。
一つは、多くの新興企業に見受けられるものだが、他社に先んじて優位性を確立しようと急ぐあまり、ビジネスとして成り立たないレベルの廉価を設定するものである。
もう一つは、リアル企業に見られるもので、従来の販売チャネル──ここではオフラインと呼ぼう──での価格をそのままeコマースでも適用することが多い。というのも、自社商品には揺るがぬブランド力があり、価格で競争力に差をつける必要はない、と信じていたからである。
もちろん、なかには「eコマース市場の一角に食い込まなければ」というプレッシャーを感じながらも、複数のチャネルで販売すると価格設定が複雑になり、ひいては「カニバリゼーション」(共食い)のおそれもありながら、しかるべき備えを整えなかったという例もある。
いずれにせよ、どちらのアプローチでも、このままでは大きなビジネスチャンスをつかみ損ねてしまう。そもそもインターネットでは、オフラインよりはるかにきめ細かいプライシングが可能となるばかりか、その過程で多くの価値が創出されるのだから──。
インターネットがもたらした透明性と効率性によって、企業も消費者も明らかにプラスの効果を享受している。顧客は容易に価格を検索・比較できるし、企業も消費者の行動を追跡し、それに応じて価格を調整できる。
しかし、従来からのやり方が習慣化し、また顧客からも「この程度の値段だろう」と値踏みされる前に、オンラインでのプライシングを早急に見直す必要がある。対応が遅れれば遅れるほど価格変更は難しくなり、ひいては取り返しのつかない事態を招きかねない。
消費者と顧客企業の本音
多くの企業が信頼できるデータを持っていないため、そのeプライシング戦略も依然として直感や推測に頼っている。たとえば、業界筋の一部はこのように主張する。
「インターネットは、価格を可能な限り低い水準に引き下げる強力な武器となるだろう。顧客はインターネットがもたらす価格の透明性を利用して、最も安い価格のものを選ぶからだ」