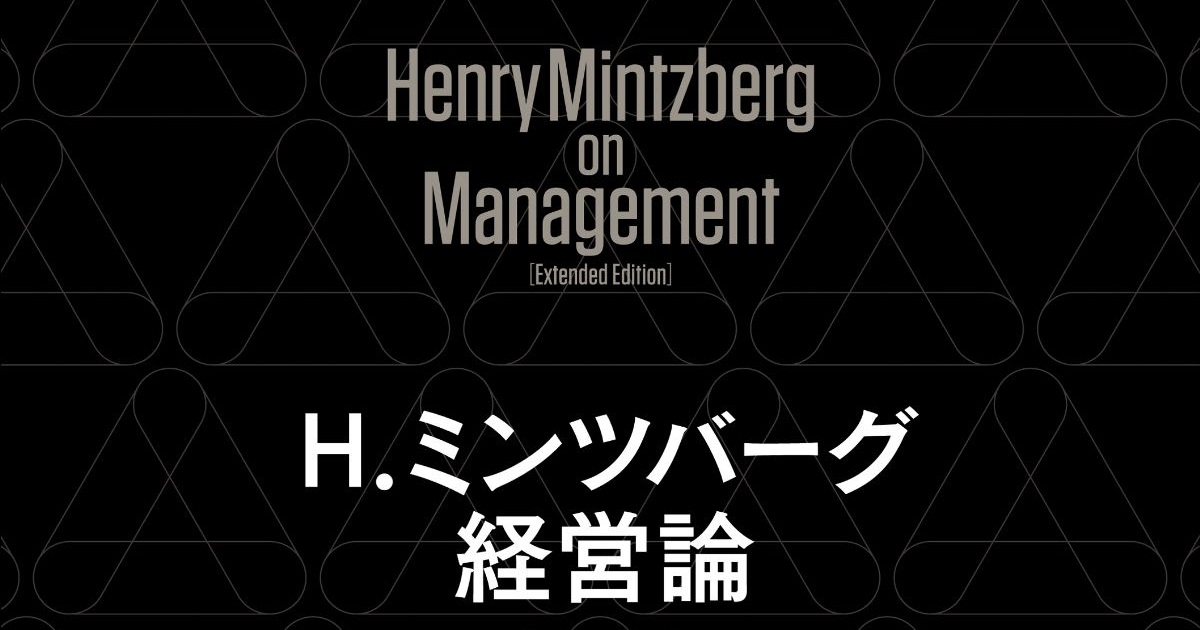
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
『H. ミンツバーグ経営論 [増補版]』に寄せて
入山章栄 早稲田大学ビジネススクール 教授
本書『H. ミンツバーグ経営論[増補版]』は、世界の経営学・ビジネス思想における「知の大巨人」ヘンリー・ミンツバーグ氏の論文、論考、インタビューをまとめ、日本のビジネスパーソンに「ミンツバーグ経営論」の全貌を味わい、理解し、活用してもらうことを目的としている。オリジナル版は日本で2007年に出版されたが、今回の増補版では、近年の最新論考やインタビューも加わっている。日本に関する言及も新たに含まれており、まさに必読の一冊だ。
筆者としては、まず何より読者の皆さんに、「いまこそミンツバーグ経営論が世界の、そして日本のビジネスにとって極めて重要になっている」ことをご理解いただきたい。筆者から見ると、ミンツバーグ氏は間違いなく人類史において五本指には絶対入る「ビジネス思想の巨人」なのだが、ピーター・ドラッカー氏やマイケル・ポーター氏と比較すると、日本では同氏の話題が上る機会はそこまで多くないかもしれない。
しかし、世界のビジネス思想におけるミンツバーグ氏の存在は極めて大きい。影響力で言えば、ドラッカー氏と比肩するか、あるいは現代ではそれ以上かもしれない。かつて筆者が米国の経営大学院の博士課程で戦略論を学んだ際、最初に必読として読まされた課題論文は、ミンツバーグ氏が1987年に発表した代表作“Crafting Strategy”であった(本書第4章「戦略クラフティング」がその邦訳である)。
また、10年ほど前に参加した世界最大の経営戦略学会である「ストラテジック・マネジメント・ソサエティ」でのミンツバーグ氏の講演セッションは、会場から人があふれるほどの大盛況であった。日本でも、優れた経営者には同氏のファンが多い。実は2025年5月にミンツバーグ氏は久しぶりに来日されたのだが、その際には、多くの著名経営者やコンサルタントがさまざまなルートで面談を希望した、と聞いている。
※来日時のミンツバーグ教授と入山教授の対談、コープさっぽろの大見英明理事長との鼎談などをまとめた記事はこちら。
【連載】リバランシング・ソサエティ 私たちはどこまで資本主義に従うのか
ではなぜミンツバーグ経営論はここまで世界で支持され、そしてなぜ、いまこそ重要なのか。筆者の目からは、その理由は大きく3つある。
第1に、「ミンツバーグ氏ほど、経営論において包括的な視点をバランスよく持つ人はいない」点である。多くの経営学者は、それぞれが独自のスタンスを持っている。たとえばマイケル・ポーター氏であれば、ミクロ経済学を基盤としたポジショニングの競争戦略論が中心となる。逆に言えば、ポーター経営学は素晴らしい体系である一方で、「経営の全体像」を包括的には捉えているわけではない。
ポーター氏と遜色ない知名度を誇るジェイ・バーニー教授の、有名なリソース・ベースト・ビューについても同様だ。結果として、「ポーター対バーニー論争」のような議論対立が生じることもあったほどだ。
これに対し、ミンツバーグ氏の優れている点は、「こうしたさまざまな経営の視点は、いずれも間違いではない、ただし条件付きで」という立場を取るところにある。ミンツバーグ氏ほど、世界の経営学の根幹にある多様な考え方に、広く深く精通している人はいない。その圧倒的な包括性をもってそれぞれの視点を公平に比較し、長所と弱点を見極め、どの視点がどの条件で機能するかを整理・再構成し、実際の経営に何が必要かを提示していくのである。
第2にミンツバーグ氏は、包括的に経営の視点・考え方を整理したうえで、それらを巧みに再構築し、独自のわかりやすい言葉に置き換えることに圧倒的に長けている。たとえば本書『H. ミンツバーグ経営論[増補版]』第16章では、経営へのアプローチを「アート」「サイエンス」「クラフト」の3つに分類し、その違いを明快に解説している。また第3章では、組織のあり方を5つのコンフィギュレーションに整理し、それぞれの特徴を浮き彫りにしている。率直に言って、このような包括的な比較・整理は、現代の経営学における学術論文では、ほとんど見られない。なぜなら、現代の経営学者の多くはみずからの狭い専門分野に特化し、自身の主張する理論だけを強調する傾向があるからだ。
一方のミンツバーグ氏は、現実のビジネスをよく理解したうえで、経営論の包括的な視点をビジネスパーソンに伝わる言葉に再構成している。ビジネスパーソンにとって、両者のどちらに価値があるかと問われれば、それは明らかではないだろうか。「ミンツバーグ経営論」と聞くと特殊性が高いように思えるが、実はそれは逆で、実務家に伝えるという意味では、これこそが「経営論の本質・王道」なのだ。だからこそ学者だけでなく、経営の本質に肉薄した世界中のトップ経営者から支持されているのだろう。
【第3の理由は、次回に続く(11月26日掲載)】
期間限定プレゼントのお知らせ
書籍『H. ミンツバーグ経営論[増補版]』の第10章「[インタビュー]アングロサクソン経営を越えて」の一部をまとめたPDFを期間限定(2025年12月31日まで)でプレゼント中です。本インタビューは、『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』編集部が2002年に行った、日本オリジナルコンテンツです。
DHBR電子版の無料会員にご登録のうえ、対象論文をダウンロードしてください。

[著]ヘンリー・ミンツバーグ
[訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]ヘンリー・ミンツバーグ教授の『ハーバード・ビジネス・レビュー』に掲載されたすべての論文、および日本版限定インタビューを収録。入山章栄・早稲田ビジネススクール教授も「ミンツバーグ氏ほど、経営論において包括的な視点をバランスよく持つ人はいない。これからのAI全盛時代において、経営者・マネジャーが果たすべき役割を明確に示している」と絶賛! 1975年に発表され、新たなマネジャー論に先鞭をつけた論文「マネジャーの職務」を皮切りに、ミンツバーグ教授が歩んだ50年間を知ることのできる一冊です。
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









