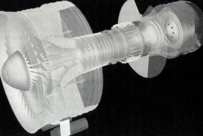-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
確実に1000ドルを手にするチャンスと、50%の確率で2500ドルを手にするチャンスのどちらかを選ぶよう言われたら、ほとんどの人が1000ドルのほうを選ぶ。後者の期待値(繰り返し実施した場合の平均値)は1250ドルになるにもかかわらず、である。また、コインの表が出たら100ドルをもらえ、裏がでたら100ドルを払うという賭けがあっても、参加を断る人が多い。損失のほうが利益よりもインパクトが大きいからだ。
トバスキーとカーネマンが開発し、1979年の論文で発表した「プロスペクト理論」(ノーベル経済学賞を受賞)によると、人は最も期待値の高いオプションを選ぶという、合理的な意思決定をしないという。なぜなら人はリスクを回避し、「損失は利益よりも大きく見える」からだ。
企業もこれと同様だという証拠がある。企業は段階的なイノベーションに投資をしすぎる。一方で、新たなサブカテゴリーを築くような「不可欠なもの」を創造するイノベーションには、投資が不足しているのである。真の成長を創造するイノベーションは、ほとんど例外なしに、後者のイノベーションだ。本稿ではこうした証拠については解説せず(興味がある方は拙著『カテゴリー・イノベーション―ブランド・レレバンスで戦わずして勝つ』〈邦訳2011年、日本経済新聞出版社〉を見て欲しい)、次の問題について考えていく――なぜ、最適ではない、臆病な投資ばかりが行われるのか。これには相互に関係する4つの理由がある。
1. 企業と主要な意思決定者は、単純にリスクを嫌う
ホームランを狙う代わりに、彼らは確実なシングルヒットを狙うのだ。確立されたカテゴリーにおける既存の製品での、段階的なイノベーションがその代表的なものだ。ブランドの成績を上げるうえでは、「よりよく、より安く、より速く」が合言葉となっている。企業とその経営幹部は、トバスキーとカーネマンの実験での被験者のように、損失を嫌い、利益を過小評価する傾向がある。売上げと利益の予想がつく、既存の事業でのイノベーションのほうを好む。もう一方の、より大きな利益基盤におけるチャンスとはなるが、投資資金を失う可能性も大きいイノベーション、その資金を別の案件に使えるかもしれないイノベーションは、相対的に好まれない。さらに、開発途中で期待外れなものとなったイノベーションは――市場でそうなるともっとひどいが――キャリアパスに影響する可能性がある。
2. 不慣れなものについて予測を行うのは難しい
大幅な、あるいは転換的なイノベーションについて予測を行う場合、市場の不確実な要素を基にすることになる。加えて、そうした予測は通常はデータでなく洞察をベースにする。とくに、慣れ親しんだものではなく、非常に新しいものについて顧客からフィードバックを得るのはかなり難しく、また間違いやすくもある。ヘンリー・フォード(「顧客は速い馬が欲しいはずだ」)やスティーブ・ジョブズ(「市場調査はしない」)といったイノベーターが明らかにしたのは、消費者は、馴染みのない分野に関しては当てにならないということだ。加えて、成功は技術などの進歩に依存する場合が多いが、その進み方も明らかではない。
これらの不確定要素と、イノベーションには成果が出ないものも多数あること、また楽観的な予測が実現しなければキャリアをリスクにさらすことなどにより、企業はイノベーションの利点とその実現可能性を過小評価してしまう。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)