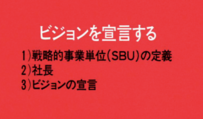-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
最近、企業の責任を問う声がますます高まっている。アウトドアメーカーのパタゴニアの長年にわたる取り組みについて記された著書『レスポンシブル・カンパニー』について、訳者の井口耕二氏が紹介する。
高くてもいいものを長く使う
最近、世の中には、安いモノがあふれています。お弁当などの食べ物から居酒屋・焼き肉・お寿司などの外食、そして家電製品、日用品なども、しばらく前から考えたらずいぶん安くなった感があります。これは一消費者としてはありがたい話ですし、私も、同じものなら安く買えたほうがいいと思ってしまいます。
でも、同時に、これで本当に大丈夫なのだろうかと心配になったりもします。
安く売るためには、その「工夫」がどこかでされているはずです。工夫としては、製造や流通を工夫して同じ品質のものを安く売る、あるいは、部分的に質を落として安く作るなどが考えられます。なにかを削らなければ安くならないのが道理ですから。その工夫は、いろいろな意味でまともな工夫なのだろうか、おかしな工夫はしていないのだろうかと気になるのです。
「いやいや、そういう工夫は当たり前だろう? 産業革命以来、我々は、機械化や大量生産、標準化などで生産効率を高め、それまでと同じものを安く作り、安く供給できるようにしてきたのだから」という意見もあるでしょう。それはそのとおりなのですが、食肉やお菓子の偽装に耐震偽装、あるいは、ユッケ食中毒などの事件を見ると、削ってはならない部分まで削ってしまう例がなくならないことがわかります。そこまで極端ではなくても、最近は壊れやすいモノが増えたようにも思います(私の気のせいでしょうか)。我が家では少し高めだけど書き味のいいボールペンをずっと使っていたのですが、何年か前、若干の価格低下と同時に品質がはっきりと低下してしまい、以来、そのボールペンを使わなくなったなどの経験もしています。
「人件費が安いなど、製造コストが抑えられる場所で作るなどの工夫なら問題ない」とも、必ずしもなりません。たしかに、最近は、生産技術の改善による効率向上に加え、グローバル化で安い労働力を調達することによって生産コストを抑えるといったこともよく行われています。この動きは、日本などの先進国にいる消費者は同じものが安く手に入るし、貧しくて労働力が安い国にとっては雇用が生まれ、多少なりとも国が豊かになると、見方によってはいいことばかりです。でも、もしかしたら、小さな子どもが安い賃金で働かされているのかもしれません。あるいは、環境規制が緩く、排水処理なしの垂れ流しができるところで作っているのかもしれません。だから、安く作れて安く売れているのかもしれません。
もちろん、「高い・安いにかかわらずきちんとした方法でまともなモノを作るのが企業の責任だ」というのが消費者側の言い分です。そして、そう言われたとき、「この値段では無理です。どうしても高くなります」と言う企業はまずありません。そんなことを言えば、売上が落ちて会社が立ちゆかなくなるからです。だから、少々の無理ならなんとかして対応します。そして、そこからまた少々の無理をしてコストダウンをして……とくり返していくうち、結局、やってはならない無理までしてしまったりするわけです。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)