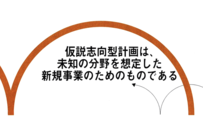-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
日本でも何かの危機に遭遇するたびにリーダーシップの重要性が叫ばれる。しかし、リーダーシップは日常的に必要とされるものだ。いまから未来のリーダーを長い目で育てていかなくてはならない。
リーダーシップ危機を叫ぶ声が、ふたたび高まっている。経済が低迷するたびに、人々はリーダーシップのあり方を考え直す。これは世の常である。
リーダーシップ危機の警鐘は今アメリカで大きく響いているが、インドでもやや小さいながらはっきりと鳴っている。何か特別な事態が起こっているのだろうか。もちろん、不況がもたらしているインパクトの大きさは近年に類を見ないものだ。しかしリーダーシップとは、危機に際してはじめてあみ出したり発見したりするものではない。継続的に育んでいくものだ。
私たちは近眼用のレンズから、遠くまで見える度数1.0のレンズに変える必要がある。そしてリーダーをどこから見出すかということについて、既存のマインドセットを捨てなければならない。
私たちは常に自社の人材に注目してきたはずではなかったか。『フォーチュン』誌シニア・エディターのジェフ・コルビンは人材に関するある協議会に出席した後、次のような核心を突く記事を書いている。「CEOはいつも『人を大事にしている』というが、内実がともなっていない。ほとんどの会社は人材の能力開発より、コピー機の維持管理のほうがまだうまくやっている。特に将来有望なリーダー人材を、何十年も放置している」
人材は今までも今後も最大の資産であり、私たちは見方を改めなくてはならない。
C・K・プラハラッドは著書『ネクスト・マーケット――「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジネス戦略』(邦訳2005年、英治出版)で、「価値共創」(co-creation)の概念を提唱し貧困層に対する私たちの見方を変えた。重要なのは、貧困層(bottom of the pyramid)というものに対する常識の鋳型が打ち壊されたことである。
リーダーシップについても、これと同様のことをしなければならない。ピラミッドの下層部分に着目するのだ。Cスイート(最高~責任者)の取り巻きではなく、社の看板を背負い顧客と接する前線にいる若手の男女こそ、未発見のリーダーなのだ。
警鐘を鳴らしている人たちに、私が問いたいことはシンプルだ。あなたたちは導きの火をかかげ前進する将来のリーダーを、正しいところから見つけようとしていますか? リーダーシップという資産はどこにあると思っていますか?
その資産は現場から、私たちをまじまじと見つめている。それを認識するために、我々は「幼虫を育てて蝶にする」(後任を教育してリーダーに仕立て上げる)という固定観念から脱却する必要がある。次世代の人たちはこうした独裁的なやり方には応えない。彼らは協働と価値共創の時代に生きている。
彼らは私たちと異なる見方や働き方をするが、そうしたやり方こそ今日の世の中では有効だ。階層を超越して協働し、データをうまく扱い、遠方とのコミュニケーションを得意とする。ジェネレーションY(1970年代後半~2000年代初頭生まれの世代)は「デジタル・ネイティブ」を構成する。彼らがシニア(熟年層・上司)よりもテクノロジーに親しみ、それを渇望し、強みとして活用しいていることには反論の余地がないだろう。
これらの若い世代は幼少の頃からマルチタスクに慣れ親しんでいる。音楽を聴き、宿題をやりながら、友だちとテキストメッセージのやり取りをし、ソーシャルネットワークを逐一チェックする――これらを同時に行うのが当たり前だ。四六時中誰かとつながっていたいと願い、複数の機器やアプリを平然と使いこなす。
ハイスピードの追い越し車線で変化とともに育った彼らは、ビジネスにおける革新にもごく自然に対応できる。オープンマインドで、意見の表明や判断の保留を慎重に行う。彼らの上司や過保護な両親よりも、彼ら自身のほうがよほど柔軟で成熟しているのではないだろうか。
したがって、現在の危機的状況に対処したいのなら、たとえ目の前が火事であっても、新たな考え方で明日を夢見る勇気が必要だ。未来のリーダーは今、下層や前線にいる。彼らを探しに出かけるのだ。多くの経営陣は彼らを直視し受け入れることに恐れを抱いている。それは大きなリスクをともなうと考えているかもしれない。しかしそのリスクを取らなければ、もっと大きなリスクを負うことになるだろう。
原文:Look for Leadership at the Bottom of the Pyramid January 9, 2009






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)