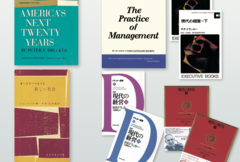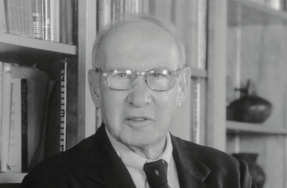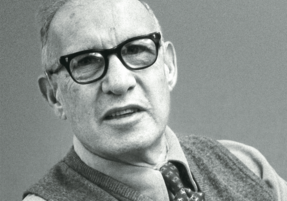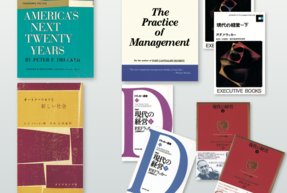-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
Managing for Business Effectiveness
経営者の真の仕事
経営者の責任とは何か
経営者の第一の務め、そして果てなく続く責任とは何だろうか。それは、現在使用している資源、あるいは保有している資源から、最善の経済的成果を引き出すために、日々邁進することである。
経営者の仕事と思われていることや経営者みずからが取り組みたいと思っていることは他にもあろうが、どれも向こう数年間の健全な業績と実り多い成果があればこそ成り立つものだ。
企業の社会的責任や文化活動といった高尚な経営上の使命でさえ、その例外ではない。金銭や地位という経営者自身の報酬もまたしかりである。
その結果、経営幹部たちは、持てる時間のすべてとまでは言わずとも、誰もがその大半を、短期的な業績に関わる諸問題に費やしている。彼らの関心は、コストやプライシング、スケジュール管理や営業活動、品質管理や顧客サービス、購買や教育研修などに向けられている。
さらに、現代の経営者に提供されているツールやテクニックの大部分は、今日明日の業績につながる目の前の事業を管理するためのものである。ビジネス書が100冊あれば、90冊はこれをテーマとしている。社内の報告書や調査にしても、100件のうち、控えめに見ても90件がそうである。
経営者に必要な概念
このように注目度が高いにもかかわらず、マネジメントにおけるみずからの仕事ぶりに大きな手応えを感じている者は稀である。そのような彼らが知りたいのは、次のようなことである。
マネジメントという職務をまっとうするにはどのような手はずを整えればよいのか、あるいは時間を浪費させるものと重要案件をいかに区別すべきなのか、また効果が期待できることと徒労にすぎないことはどのように線引きすべきか等々──。
経営者の周りには膨大なデータや報告書があふれているにもかかわらず、実際に得られるのは、つかみどころのない一般論ばかりである。だからこそ「私が勤める会社において、業績と成果を本質的に決定づけている要素は何か」という問いに、その答えとして「低コスト」「高い利益率」といった決まり文句が無造作に口にされる。
業績志向のマネジメントは、売り手市場という好況期の間でさえ、たえざる徒労感を生じさせる源となりがちである。また、好況期が去り、市場競争が再び激化すれば、業績志向のマネジメントは多大な混乱やプレッシャー、不安感を引き起こすため、企業の将来はもとより、短期的な成果についてですら正しい決定を下すことはまず無理だろう。
我々が求めているものは、数々のツールや優れたツールではない。すでに、一経営者は言うまでもなく、一企業として使いきれる数以上のツールが存在している。我々に必要なのは、単純明快な概念である。
・経営者の「職務」とは何か。
・経営者の職務における「主要な問題」は何か。
・この問題の本質を明らかにし、分析するための「原則」は何か。
すなわち、これら3つの問いに答えると同時に、職務を組織化することを容易にし、かつ大局的にして実際的な指針なのだ。