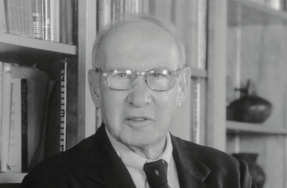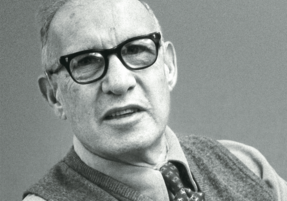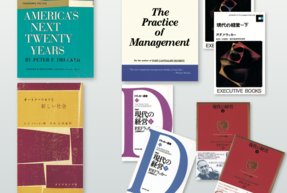-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
なぜそのルールが必要か本質を見極める
編集部(以下色文字):これまで国際連合の仕事において、命の危機と隣り合わせにある紛争の現場や、各国の利害が対立するひりついた軍縮の交渉など、常に瞬時の難しい意思決定と行動力を求められてきたと思います。そうした厳しい仕事と向き合う中で、日本語で「真摯さ」「誠実さ」と訳されることの多い「インテグリティ」について、中満さんはどのようなものと捉えていますか。これをピーター・ドラッカーは、組織を率いる者に不可欠な要素として挙げていました。

中満(以下略):「インテグリティ」とは、大きな意味で「原理原則に対して忠実である」、そして、「モラルコンパス(moral compass:行動や倫理の基準)に基づいて一点の曇りもなく守っていくべき姿勢」というふうに私は捉えています。
とはいえ、やみくもに守っていくという姿勢も違う、と思っています。特に日本で顕著かもしれませんが、形式やルールから外れたことをやってはいけない、という意識が非常に強い。法治国家として当たり前であり、よいことでもあるのですが、そちらに目が行きすぎているのではと思う場面もあります。そうなると、これは万国共通ですが、実際にそのルールが何を守ろうとしているのか、そのルールをなぜつくったのかということが、ややもすると見過ごされてしまう。思い至らないというか、それについて思考しなくなってしまう。これはまずいと思います。
もちろん人間社会にはルールが必要です。ただ、なぜそのルールが必要なのか、そのルールが何のために存在するのか、を考える必要があるといつも考えています。そのルールができた当時から時代を経て、実情や本質にそぐわなくなることもあります。たとえば「命や尊厳を大切にする」といった根本的に絶対に変えてはいけないコアの大原則はありますが、それ以外であれば社会や実情の変化に即して、この激動の世の中で何を守り何を変えていくのかを考えることが必要だと思っています。
時代や状況に即してルールを変えるべきだと感じられた事例があれば、教えてください。
私が紛争中のボスニアで国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の職員として働いていた頃のことです。国連職員は紛争地帯にあるチェックポイントをスムーズに通過するために、命と安全が保障されるIDカードを渡されるわけですが、私は一度その権利を濫用したことがあるんです。
命の危険にさらされた現地の女性2人を何とか安全な場所まで連れていかなければ、強制収容所に連れていかれるか殺されてしまうおそれすらあるという切迫した局面でした。そこで私は、彼女たちのために国連職員と身分を偽るIDカードを作成して持たせ、チェックポイントを通過しました。結局、処罰はされなかったのですが、これは明らかにルール違反ですから事後報告はしました。
私としては自分たちが活動することの本質的な意味を考えた時に、彼女たちの命が守られるならば、それを優先すべきだと判断しました。なぜそういう規則があって、何を守りたいのかという本質を考えることが、私にとっては重要です。この時の行動がよかったとは申しませんが、常にそうやって本質を見極めることが重要だと考えています。
若い時から自分の頭で考える練習をする
いまのお話のように為すべきことの本質を見極めようとする姿勢は、ドラッカーが「最も重要な5つの質問[注]」のうちの第1に掲げている「我々のミッションは何か」にも通じるところがあります。命の危険と隣り合わせの現場を経験されるなど、国連職員になった当初から癖づけられたものでしょうか。
この仕事の内容そのものが特殊なので、その影響もあるとは思います。ギリギリのところで私たちは何のために活動しているのかと常に考えるようにはなりますね。