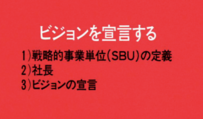-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
昭和の日本の大企業に根を下ろしていたさまざまな「構造」のうち、もっとも安定的に強力だったもののひとつに「終身雇用と年功序列」があった。これをもって「日本的経営」という人もいたぐらいだ。
もちろんそれが安定的な構造でありえたのには理由がある。論理の詳細は省略するが、高度成長期の日本の置かれていた状況を真剣に考えれば、「終身雇用と年功序列」という組み合わせは、ベリーベストの選択だったのではないか。日本だって、明治大正期、いや戦前の昭和初期までは、大企業であっても終身雇用や年功序列は普通のことではなかった。
終身雇用と年功序列というのは、戦後日本の成長を支えた構造上のイノベーションといってもよい。とくに年功(現実的には入社年次)という基準を、半ば論理を飛び越えてもってくるところなど、天才的だ。その正当性を問題にしさえしなければ、だれにとっても明確な基準であり、評価と運用のコストが極小化できる。ある意味で素晴らしく経営合理的な仕組みだといえる。
ところが、あらゆる構造の宿命として、「終身雇用と年功序列」という構造は徐々に時代と世の中の要請からズレてきた。1980年代になると、終身雇用と年功序列には悪い意味合いの方が強くなり、例によって「構造改革が必要だ!」というときの改革しなければならない対象として認識されるにいたった。
考えてみれば当たり前の話なのだが、終身雇用と年功序列は、「鰻と梅干」というか、食い合わせとしてよろしくない(いわゆる「合食禁」の例としては、「鰻と梅干」以外に「天ぷらと氷水」などがある。僕は子供のころあらゆる合食禁に挑戦してみようと思って、鰻重を食べるときは必ず梅干を食べ、天ぷらのときはできるだけ氷水を飲むようにしてみたが、とくに問題はなかった。余談終わり)。
普通の論理からすれば、終身雇用を保証して、同時に(建前としては)全員が年功で昇進していけば、人件費の拡大や管理職ポストの増殖、固定的間接費の増大に際限がなくなるので、経営は破たんする。終身雇用を原則とするのであれば、それだけ一人一人を細かく評価し、成果や能力や役割に見合った報酬の設計が必要になる。雇用は保証するけれども、報酬はあなたの貢献次第ですよ、という話で、この方がずっと食い合わせが良い。もちろん実際はケースバイケースなのだが、今後の日本の企業、特に製造業のような能力蓄積がものを言う分野では、原則的な終身雇用と能力や役割に応じた報酬体系がよい食い合わせになると思う。
逆に、これは現実にはちょっとアレだと思うが、いつでも解雇できますよという前提であれば、人間の能力評価はどんぶり勘定で構わない。年功序列でもまったく問題ない。問題があればその人を切ればいいだけの話である。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)