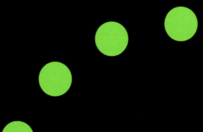-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ハーバード・ビジネス・レビューの最新号は、3月9日発売です。今号の特集は、「持続可能性」。かつて環境先進企業だけが取り組む課題が、いまではグローバル企業の先駆者になるための課題になりました。特集の企画から編集を通して感じたことは、もはや「攻め」の課題であるということでした。
ローマクラブが「成長の限界」を提唱したのが、1972年。以来、グローバル規模で環境保護への気運が高まりました。2000年以降は、消費者の意識も高まりNPOの活動も活発化しました。この情勢に一番遅れたのが企業かもしれません。しかし、今日の経済社会で企業にかかる期待が大きいことは言うまでもありません。ポーター教授もCSV(共有価値の創出)理論で、企業を社会ニーズを解決する担い手と位置付づけました。
今月号の特集「持続可能性」で意識したのは、このテーマが「企業の責務である」というメッセージを超えた意味を出すことでした。責務という言葉には「しなければいけないこと」という外部からの要請に「迫られたもの」と感じてしまいます。しかし、すでに先進的企業は持続可能性に対し、そのような動機づけを超えています。世界最大の小売業ウォルマートは、2005年から活動を本格化させ、いまでは競争優位の源泉となりつつあります。アウトドア衣料メーカーのパタゴニアは、愚直なまでの持続可能性への取り組みが、イノベイティブな製品開発に直結しています。今号では紹介できませんでしたが、ネスレも世界の水資源の問題にいち早く取り組んでいますが、それは自社の長期的な事業戦略の一環に位置付けており、それが問題解決をグローバルレベルで加速させています。このような事例は枚挙に暇がありません。
今号の論文の中で興味深かったのは、サンダーバード国際経営大学院のグレゴリー・アンルー教授らが書かれた「環境基準競争を制する」です。この論文に登場する企業には、公的機関が定めた基準に抵抗しようという発想は微塵もありません。どの基準が自社の属する業界にとって相応しいか。自社が基準づくりに貢献できるだけのケイパビリティがあれば、積極的に関与する。それが優位性だという戦略的な考えです。これは持続可能性が「企業の責務」と言った言葉をはるかに超え、事業活動の一環としての「攻める」分野という位置づけです。実にドライにこのテーマに対峙している様子は、まざまざと先進企業の視点の高さを感じました。
先日、読者との朝会でもこの話題になりました。「業界トップ企業だからこそ、持続可能性に取り組めるのではないか」「上場していないパタゴニアのような企業だからこそ実施できるのではないか」「業界中堅企業が果たしてどこまで積極的に対応できるか」などです。確かに、多くの企業にとって持続可能性を事業の戦略に位置づけていくには、克服すべき課題は多いです。しかしこれはこの課題がイノベイティブなテーマに代わってきた証しと言えます。
かつての環境問題が企業倫理やコンプライアンスの一環として議論されていた時代は、むしろ「ディフェンシブ」な課題でした。しかし、いまではいち早くモデルを開発させた企業が来優位性を構築する課題です。いわば、リーダーシップとイノベーションが求められるテーマとなりました。リーダーシップとイノベーションは、グローバル化経済への対応が迫られる日本企業の最大の問題でもあります。今号の持続可能性の特集とともに、日本企業の経営課題も併せて考えていただければ幸いです。(編集長・岩佐文夫)





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)