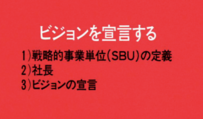-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
最新号の5月号は、『ワーク・シフト』のリンダ・グラットンさん、『スタンフォードの自分を変える教室』のケリー・マクゴニガルさん、『採用基準』の伊賀泰代さんと豪華な顔ぶれが揃った。インタビューも担当した編集長が読みどころを語る。
多くの企業が新しい年度を迎えるということで、最新号の特集は「キャリア」にしました。幸いにも今号では、ベストセラーになっている書籍の著者3人が揃いました。
おひとり目は、『ワーク・シフト』の著者リンダ・グラットンさんです。2月に来日された際にインタビューさせていただきました。『ワーク・シフト』を読んだ人の中には、「優秀な人だけが生き残る世界」と受けとめた方という印象をもった人もいるようですが、リンダさんにお話しを伺っていると、人のもつ可能性は無限かもしれないと思わされます。氏は、これから70歳、80歳になっても第一線で活躍できると断言されます。私が「でも仕事の能力は上がらないのでは?」と質問すると、すかさず「何でそう思うんですか?」と。リンダさんは人が興味を持ち続けて仕事をしていれば、80歳でも成長すると仰います。氏の明るくて包容力のある人柄と相まって、高齢者の労働力としての可能性について考え直すきっかけになりました。
2人目は、『スタンフォードの自分を変える教室』の著者、ケリー・マクゴニガルさんです。お写真で見られた方も多いでしょうが、とにかく美しい方で、女優さんにインタビューしているような心境にもなりました。ケリーさんのお話しでは、将来の自分を身近に感じることができるかという点が印象的です。別の言い方をすると、今の自分が、将来の自分に対して思いやりをもてるようになれば、体に悪いタバコは止めるでしょうと。この話しは非常に納得できました。将来のキャリアを考える上で、将来の自分をどれだけいまの自分と結びつけて考えられるか。若い人にこそ読んでもらいたい記事です。(それにしてもきれいな方でした)。
3人目は、『採用基準』の伊賀泰代さんです。マッキンゼーの採用マネジャーという経歴から生まれたのが『採用基準』だとすれば、今号で執筆いただいた原稿「キャリアの成功とは何か」は、伊賀さんの現在の本職であるキャリア形成コンサルタントとしての本領発揮と言えるものでしょう。氏の成功の定義は実にシンプルで、3つのステップで紹介されていますが、従来語られるキャリア論とは視座がまったく違います。そもそも仕事は自分にとってどういう意味をもつのかという本質的な問いかけをされているような読後感です。「基本的に、社会に強いニーズがあることは必ず職業化できる」という一文を目にしたとき、はっとしました。私自身、何度も読み返したくなる内容です。
キャリアの特集をつくって改めて感じたのは、この問題は大学卒業時にだけ考えるものではないということです。仕事をする限り自分のキャリアを自分で考えていく必要がある。そして、多くの人が自分のキャリアを自分で積極的にコントロールしようとすれば、社会も経済も活気に満ちたものになることは間違いないようでしょう。(編集長・岩佐文夫)





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)