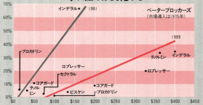-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
いよいよ「社会システム・デザイン」具体的な作業に入っていく。最初のステップは、悪循環を発見し、定義することである。私たちの身近に散見される悪循環を、どう捉え、読み解いていくのか。元マッキンゼー東京支社長であり、現在、東大エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(EMP)で次世代リーダーを育成している横山禎徳氏による特別レクチャー、第3回。
「社会システム・デザイン」の第1ステップは「悪循環」を発見し、それを定義する作業である。この作業の質が全体のデザインの質に大きく影響するので十分な時間をかける。このステップで行う繰り返し作業をしていると頭の片隅に次のステップのアイデアが浮かんでくることもよくある。しかし、「悪循環」の理解が進むとともにそのアイデアも次から次に変わっていく。どれかのアイデアにすぐに飛びつくのではなく、時間をかけて段々と「発酵」させていくこともこの「社会システム・デザイン」作業の知恵である。
手を動かし、脳内ニューロンが「発火」するまで考える
「悪循環」という表現はよく使われる。逆に言えば、そのくらい日常的にさまざまなところで起こっていることである。しかし、その表現をよく吟味してみると、ここでいう「悪循環」とは少し違う。メディアも含めて多くの場合、「悪循環」を現象として捉えている。しかし、「社会システム・デザイン」でいう「悪循環」を発見し、定義することは「中核課題」を捉えるための作業である。現象をいくらうまく説明してみたとしても、その背景にある「中核課題」を捉えていない限り、「社会システム・デザイン」という観点からは役に立たない。現象でしかない問題を裏返した対策をいくら打ってみても「良循環」の創造に結びつかないのである。
「デフレが長年続いているからインフレ・ターゲット…」、「GDPが成長しないから成長戦略…」、「OECD諸国で子育て予算が一番少ないから子供手当…」と問題の裏返し的施策が多いが、効果的な施策であるという証拠はほとんどない。それに比べると、「悪循環」は裏返すことはできない。実際に試してみるとすぐわかる。従って、「悪循環」を見つける作業からはそのような「問題の裏返し」施策は出てこない。これも「社会システム・デザイン」の自己規律の1つである。
「悪循環」を図の形でビジュアル化し、できたものを目で確かめながら自分が納得できるまで何度も描き直していく。目と手の連携を繰り返すことによって思考を練り上げるプロセスである。ビジュアル思考というやり方である。それを続けていると「あ、そうか」と「中核課題」が分かってくる瞬間がある。脳内のニューロンが同時発火するのであろう。ばらばらに発火しているニューロンが同時発火するのは確率でしかなく、自分の意志ではコントロールできないから、その確率を高めるためには何度も繰り返して同じ作業を続けるしかない。
「悪循環」の図は例示にあるようにできれば簡潔に美しく描くことが大事である。できるだけ一覧性を高めるようにする。少し眺めると誰でも「悪循環」の全体像がつかめるようにまとまりよく描くのである。循環図を描くための自分好みのフォーマットをあらかじめ決めておくのがよいだろう。フォーマットをいちいち考えることなく、ひたすら描き続けることができるのが望ましい。
簡潔に美しく描くことには意味がある。思考が明解になればなるほど循環図は無駄なく美しくなるはずである。また、途中経過においてもビジュアルの質はそれを眺める自分の思考に影響する。雑然と描いた中に創造的なものが隠れているということは実際にはあまりない。自分の創造性を信じたりせず、きちっと規律をもって何度も飽きることなく描き直し続けることが大事だ。エジソンも1%のインスピレーションと99%のパースピレーション(汗をかくこと)と言っている。
「中核課題」を捉えるということはどういうことだろうか。世の中の多くの現象をそのまま受け入れるのではなく、その背景にある本当の課題を見つける努力をするのである。地球温暖化、人口減少、少子化、高齢化、デフレ経済、就職浪人の増加、医療費の増大、年金の破たん、電力供給における原発の役割など数えきれないテーマがある。しかし、それらは現象的テーマでしかない。その背景にその現象が起こっている「中核課題」がある。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)