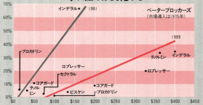-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「社会システム・デザイン」の第3ステップは、良循環を駆動させる「サブシステム」を見出すことである。急速に老朽化する新興住宅街をはじめ、ゆがんだ日本の住宅事情をどう良循環に変えるかを例にとる。元マッキンゼー東京支社長であり、現在、東大エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(EMP)で次世代リーダーを育成している横山禎徳氏の好評連載、第5回。
いろいろな試行錯誤と発見と工夫の結果、素晴らしい「良循環」を思いつき、デザインしたとする。当然、それは今、この世に存在していない。家や車やスマホとは違って「触れなくて目に見えない」ものではあるが、現実に循環する存在にする必要がある。それが循環の「駆動エンジン」としてのサブシステムの抽出である。1つの「良循環」を駆動するためには3つのサブシステムが適当である。2つでは「駆動力」に欠けるし、4つではお金がかかりすぎるからだ。
具体的なアクションが見えるように書く
この3つのサブシステムを抽出するコツは、「良循環」をよく眺めてみて、何かの「駆動エンジン」がないと自然には動かないところをまず見つけることだ。そのもっとも安直なものは法律で固めることである。政治家も官僚もすぐに法律を作ろうとするが、物事は法律で強制されたり、保護されたり、罰せられなくても動くのである。最初に法律ありきではなく、もっと多様な仕掛けを考え抜くことが必要だ。インセンティブ、ピアプレッシャー(同僚や仲間からの圧力)、競争やゲームの導入、功名心や達成感の組み込み、勲章など特別の表彰、メディアの活用による世論の喚起などいろいろ考えることができる。
このようなサブシステムを実際に関わる人たちに向けて、ちゃんと理解し実施してくれるよう、具体的なアクション・ステップの流れで書いていく。サブサブシステム、サブサブサブシステムのレベルに分解してより細かく具体的に書いていく。当然、玉虫色の表現はなく、解釈によってどのように運用されるかわからない法律よりもよほどアクションが明解である。これが「社会システム・デザイン」と法律の違いだといってもよい。
原子力規制委員会設置法を例にとって見よう。第7条、委員長及び委員の任命の項に「委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用の安全確保に関して専門的知識および経験並びに高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と書かれている。典型的な法律の表現であるが、任命プロセスが具体的に見えない。
「人格が高潔」「専門的知識」「経験並びに高い識見」を評価するクライテリア(基準)は何かを明確にし、候補者はだれがどうやって選ぶのか、どうやって絞り込むのか、両議院はどういう議論をして吟味するのかなどを具体的に示すのがサブシステムとして必要な記述である。そこには「てにをは」の解釈の違いはなく、誰がやっても同じにできることが目的である。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)