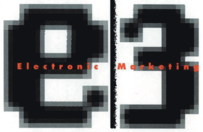-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
今月号の特集テーマは、「顧客を読むマーケティング」。このテーマを選んだ背景にあったのは、ビッグデータの可能性と限界である。その可能性はいまさら繰り返すまでもないが、一方で万能視するのは危険である。ビッグデータの「できること、できないこと」を正確に知ることが、いま問われている。
今年の2月号でビッグデータの特集をやりましたが、その反響の大きさに驚きます。刊行後も、さまざまな読者や企業から問い合わせを受けるようになりました。また本国HBRも、ビッグデータに関する論文が多数拝見されます。
この流れを汲んで、最新号ではマーケティング特集をするにあたり、ビッグデータをかなり意識することになりました。

新しいテクノロジーや技法が登場すると、あたかもそれらが万能薬かのように語られることがしばしばあります。古くはリエンジニアリングが登場した1990年代、この手法で既存の大企業のどこもが生まれかられるかのような喧伝がなされました。2000年代にはデル・コンピュータのダイレクトモデル(BTO)が一躍脚光を浴びましたが、IT端末の覇者となったスマートフォンでこのモデルはどこにも存在しません。
かように新しいモデルや技法は騒がれては消える、を繰り返してきました。さらに言えば、騒がれ過ぎたことで、そのモデルの本質や個別有意な点が見逃され、「使えるか、使えないか」のどちらかに整理されることになってしまいます。
これは悲しいことです。どんな技法も万能薬でもないし、その有効性がすべて否定されるものでもないはずです。一定の条件や状況で効果が発揮されるものまで、「期待外れだった」との烙印とともに人々の選択肢から消えていくことはもったいないです。
ビッグデータもその運命をたどることがないことを祈るばかりです。そこで今号の特集「顧客を読むマーケティング」ではビッグデータで、本当に顧客のことがわかるのかを問うことにしました。
ビッグデータによって顧客の購買データが詳細につかめる。さらに言えば、購買までの情報接触パターンまでもがつかめるようになりましたが、従来のマーケターが日々考えていた顧客インサイトが、ビッグデータから読み取れるようになったのでしょうか。マーケターは顧客が意識していない深層心理まで理解したいと、これまでエスノグラフィー調査や心脳マーケティングなどあらゆる手法を駆使して、顧客の本質に迫ろうとしてきました。これらの代わりをすべてビッグデータが担ってくれると思えません。であれば、ビッグデータに何を期待し、何を期待しないほうがいいか。これが今号の我々のテーマです。(編集長・岩佐文夫)





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)