-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
本誌2013年10月号(9月10日発売)の特集は「顧客を読むマーケティング」。HBR.ORGの関連記事の第8回は、ビッグデータ時代の顧客セグメンテーションについて。従来型の区分はもはや有効ではなく、「顧客が果たすべきタスク」に焦点を当てる必要があるという。
「実は、私はもうセグメンテーションを信じていません」と突然、クライアントの女性が口にした。それは、我々がこれからアドバイザーを務めることになる、新しいデジタル・マーケティング戦略に関する最初の打合せでのことだった。彼女は、周囲の音に紛れて聞き逃されることを願っているかのように、早口でそっとつぶやいた。しかし、我々はちゃんと聞き取り、こう応じた。「ええ、私たちもそうです」
我々にとってこのやりとりは、かねてより考えてきた問題が最も顕著に表れた瞬間だった。それは最初に、ビジネススクールでの授業やクライアント支援のなかで持ち上がった。一方ではセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングを人々に説きつつ、他方では、そうしたブランド側の行為よりも顧客のほうが強い影響力を持つようになっている現状を説く。双方のズレが広がっていることに、我々は気づいていた。
クライアントや学生は、次第に疑問を投げかけるようになった。我々はこれまで、「すべての顧客にすべてを提供するのは不可能である」という前提の下、市場をセグメントに分ける厳密な手法を推奨してきた。その一方で、「共創」という教義も広めてきた。たとえばレゴやスターバックスなどの企業が、顧客との対話に乗り出し、顧客に参加する機会を与え、リスクを顧客と共有し、透明化を推進している例である(共創についてはC・K・プラハラード、ベンカト・ラマスワミ著『コ・イノベーション経営』を参照)。
あるプレゼンテーションでは、ビッグデータやリトルデータについて熱心に語ったかと思えば、翌日は1960年代に生まれた迷信のような心理学のセオリーについて論じる。このような矛盾を解消するために、我々は学生とクライアントに「顧客が達成すべきタスク」に注目するよう提唱し始めた。このアプローチは、セオドア・レビットの有名な言葉、「消費者に売るべきなのは1/4インチ径の電気ドリルではなく、1/4インチの穴である」にも一致する。「製品を売る」という意識から離れ、顧客の「タスクを果たす」ことで彼らの問題を解決するのだ。クレイトン・クリステンセンの言葉を借りれば、顧客は特定のタスクを果たすために製品やソリューションを「雇う」のであり、特定のセグメントに属しているからそうするのではない。
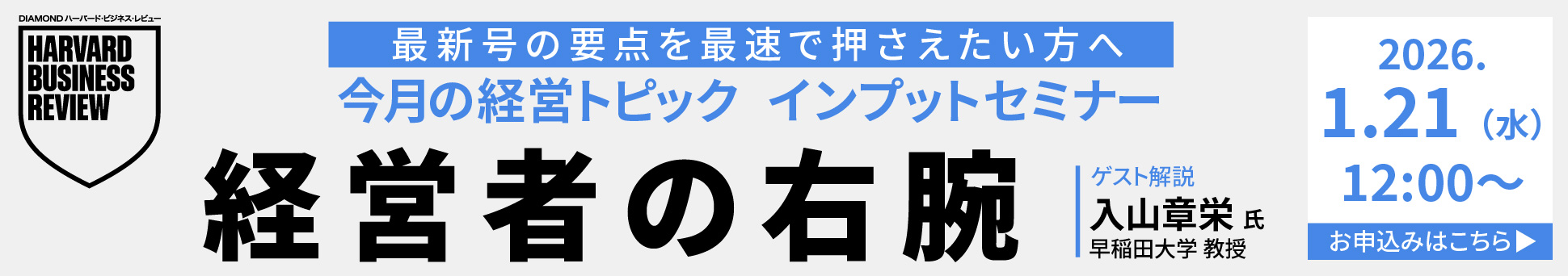





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









