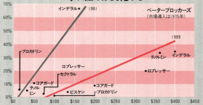-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
本誌2013年11月号(10月10日発売)の特集テーマ「競争優位は持続するか」に合わせ、MBA必読の古典『企業成長の理論[第3版]』の抜粋を紹介する連載。残る2回は、そもそも企業成長における企業の前提は何か。「理論における企業」を紹介する。
企業についての異なる見方
民間企業が中心の産業経済では、企業が生産組織の基本単位である。経済活動の大部分が企業を経由して行われる。生産だけでなく消費のパターンも含めた経済生活のパターンのほとんどは、企業という事業単位の活動を担うビジネスマンの多数の個々の意思決定によって形づくられている。経済の性質さえも、その経済を構成する企業の種類、規模、設立や成長の仕方、ビジネスの運営方法、およびこれらの相互関係によって、ある程度まで規定される。その結果、企業は、経済分析において常に特別な位置を占めてきた。企業は、経済生活や社会生活にさまざまな面で影響を与え、多数かつ多様な活動からなり、雑多で予測できない人間の気まぐれに影響を受けながらも、概してみれば人間の理性に方向づけられた多種多様の重要な決定を下す1つの複雑な制度である。
経済学の文献においては、「現実世界」の企業は、「純粋理論」の乾燥した高原と「実証-現実主義」の研究の鬱蒼とした森林との間の、居心地の悪い土地で長いこと暮らしてきた。2つの地域の住人の境界争いは日常的で、お互い熱心に忠誠を守ろうと対立する高貴な騎士たちが繰り広げた中世の馬上槍試合まがいの闘いが展開されてきた。これらの闘いは1つの際立った特徴をもっている。すなわち、不思議なことに誰にとっても、敵のありかを正確に見つけることすら難しいらしく、ある方向から途方もない数の攻撃が仕掛けられても、まったく違う方向から迎え撃たれ、太い刀と鋭い剣とが現実にはぶつかり合うことなく、力まかせに空を切っているようにみえる。思考の世界でこのような問題が生じると、人はその原因を言葉の意味に求めようとする。実際、「企業」に関わる現在の問題も同じである。「企業」は、決して輪郭のはっきりした存在ではない。それは他のものから物理的に分離して観察できる対象ではないし、それが何を行っているか、あるいはそのなかで何が行われているかに関連づける以外には、定義づけも難しい。このため企業を分析しようとする者は、それぞれの関心に応じて企業のどんな特徴を選ぼうと、それらの特徴に照らして企業を定義しようと、また、そのように定義したものを以後「企業」と呼ぶことにしようと自由なのである。ここにこそ、混乱、それも本書のまさに冒頭で取り上げざるをえない混乱の潜在的な原因がある。
企業は、その複雑性と多様性ゆえに、社会学、組織論、工学、経済学など多くの異なるタイプの分析手法を用いて、また、分析ごとに問題に適すると思われるさまざまな観点からアプローチすることができる。経済学自体のなかにも、企業の研究にはいくつかの異なるアプローチがある。その1つであるいわゆる「企業の理論」は、厳しい攻撃にさらされながら、その陣地を守り続けている。この理論は、あらゆるアプローチのなかで、その防御側からも攻撃側からも最も頻繁に誤解され、誤用されているものといえる。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)