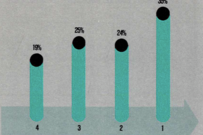「国」の枠にとらわれない組織の影響力も増加する。現在でも、とくに環境分野でのNGOの発言力の増大は目に見えるところである。今後もNGOなどの共通目的・価値観を持った組織が、国境を越えた活動を広げるであろう。また、移民の増加によって広がるグローバルなエスニック・コミュニティの影響力も、各国内で拡大することになる。「世界は1つ」というような単純に収斂していくようなグローバル化ではなく、多極化・多元化するなかで国境および国家という概念が相対的に希薄化していくというのが、これから起こるグローバル化の姿である。たとえば言語という軸で見ても、自国・母国語の文化で生活しながら、仕事は英語(または中国語)というようなスタイルがより一般化していくことになる。
逆に、「国家」という枠を早期に確立してきた西欧・先進諸国では、高齢化や低成長などの結果として、政治的、財政的、社会システム的プレッシャーが高まる。日本や西欧諸国で実際に見られるように、票欲しさの公約(大きな公的支出)は財政健全化とは相反することになりがちで、結果的に多くの先進国で短命政権化が進行し、強力なリーダーシップを発揮しにくくなる。税負担は増加せざるを得ないものの、企業は本社を他国に移転することも可能なため、そうした企業の海外移転を防ぐために法人税率はむしろ軽減の方向に向かう。
旧西側諸国の影響力の相対的な低下は、政治的に見ると民主主義の危機につながる可能性がある。一方、貿易や提携などのビジネス開拓の場においても、社会体制やルール、価値観が異なる国々(の企業)を相手に交渉することになる。たとえば、中国はどの資本主義国よりも資本主義的とも見えるが、政治的には共産党の指導部による集権主義であり、地方政治は悪い意味で官僚的な慣行が多く残っている。一方で中国系企業の経営者の多くは、海外で教育を受けたり生活をしてきた経験を持っており、もともと「国」の枠にとらわれない華僑・華人の伝統も持っていたりする。
今後20~30年という長期のスパンで考えてみると、世界は政治主導から経済主導に移っていくと見ることができる。政治面での欧米先進国のパワーは相対的に低下し、新興国の発言力がより増していくことになる。また、新興国内では、旧来的な政治勢力と民主化を求める勢力との摩擦がさまざまに起きる。しかし、その一方で、経済成長の持続による国民生活水準の向上が、結局は国内の社会問題の解決のための最善の方策であるということが明らかになっている。このため、短期的には何らかの揺り戻しや締めつけがあるとしても、多くの新興国は経済面での改革・開放を選択し、徐々に市場主義化が進んでいくことになる。企業の立場から見ると、さまざまな紆余曲折は予想できるものの、政治的な保護主義の力が次第に弱まり、より自由に企業活動が行えるようになっていくのである。
日本企業にとって、これまでのグローバル化とは、西欧社会(民主主義的な制度)と渡り合う術を身につけることであり、また、「国」(政府)同士によって定められた規制の枠組みを守ることであったため、比較的わかりやすかったと言える。しかし、今後新興国で事業を行い、新興国企業と交渉を行う際には、かつて学んだグローバル化の枠組みがかえって邪魔になる可能性もある。新たな時代のグローバル化においては、旧来の常識は通じないかもしれないという前提を持っておくべきであろう。
*第11回は2013年12月16日(月)公開です。
グローバルな経営コンサルティング会社として、世界のトップ企業及び諸機関に対し、経営レベルの課題を解決するコンサルティング・サービスを提供している。全世界57事務所に3,000人以上のスタッフを擁し、クライアント企業との実践的な取り組みを通じて、「本質的な競争優位」と「差別化された優れたケイパビリティ」の創出を支援することを使命とする。
【連載バックナンバー】
第1回「長期的ビジョンはなぜ必要なのか」
第2回「グローバル市場の変化を見通す」
第3回「グローバルな10のメガ・トレンド」
第4回「第1のメガ・トレンド 環境保護主義」
第5回「第2のメガ・トレンド 資源をめぐる戦い」
第6回「第3のメガ・トレンド 人口動態と富」
第7回「第4のメガ・トレンド 人口移動」
第8回「第5のメガ・トレンド 富の再配分」
第9回「第6のメガ・トレンド ビジネスのグローバル化」








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)