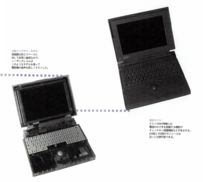言論の正当性はだれが決めるのか
――社会に影響力を与える方向性については、ユーザー主導であって企業側のコントロールが利きません。望ましくない方向に社会が動くツールとして使われうることに、ジレンマは感じませんか。
近藤:ソーシャルメディアの登場により、これまでは特定の人のみが持っていた発信力を一般の人々も得られるようになりました。この情報の民主化は基本的には望ましいものだと考えています。
しかし、そのことで、これまでは特定の人しか受けなかったような注目や批判を一般の人々が受ける可能性も増えています。このことについては2つの考えを持っています。
1つは、影響力の対称性についてです。発信力を持った人が、他の人の発信を遮断することは困難です。たとえば政治家や芸能人が「自分のメッセージは流してほしいが、質問と批判は受けたくない」と言うことは成り立ちにくい。オープンな言論空間に参加している限り、一定の議論や挑戦は避けられません。しかし、そこにはルールも必要です。プライバシー侵害、嫌がらせ、脅迫行為については厳正な対処が必要であり、Twitter上でも規約が存在します。もう1つは、表現の自由と検閲について。これは新聞における言論の自由、民主主義における表現の自由と通じる問題です。世界では多くの国々で表現の自由が制限されています。Twitterでは、世界の全ての人の表現の自由を推進したいと願っています。
もちろん、人間社会の縮図である以上、誤ったことを言う人もいます。間違った情報が流されることもある。例えば、東日本大震災でも間違った情報が拡散されることがありました。それらの間違った情報の動きを調べてみると、大部分が速やかに検証され、過ちであることが指摘され、正しい情報が拡散されました。東日本大震災に関する情報発信についてより包括的に俯瞰してみると、政府でも、専門家でも、メディアでも、地元の人でも、常に正しい発信主体はありませんでした。人々も、様々な発信主体の情報を入手し、新たな事実が明らかになれば誤った認識は改め、正確な事実認識に近づいていったのではないでしょうか。何が正しく、何が正しくないのかを誰がどう判断すべきかはとても難しいことです。
ただ、表現の自由と言っても、例外はありえます。例えば、児童ポルノについては、世界中で制限すべきとのコンセンサスが生まれつつあり、Twitterでも厳しく対処しています。しかし、こうした表現の自由の制限、情報の検閲は、あくまでも例外的なものであり、非常に慎重に取り組むことが大切だと考えています。
――ウィンストン・チャーチルの「民主主義よりましな仕組みは知らない」という言葉に通じるものがあります。民主主義の欠陥に直面しているところがありますよね。
近藤:そうですね。Twitter上では、多くの情報が発信されています。仮に今日、2億人がツイートしていたとして、その2億人のどの発信が正しくて、どれが正しくないのかを即時に判定する権限をだれかに与えることなどできるはずもありません。賢人にすべての真偽の判断を委ねたい衝動にはかられますが、では、適切な賢人など存在するのか。存在したとしても、チェック機能なしに権限を委ねることは危険ではないか。簡単な答えはないと思います。
ただ、人間は経験から学ぶことはできます。その上でビッグデータが今後果たす役割は大きなものとなるでしょう。例えば、東日本大震災については、Twitter、グーグル、NHK等とでデータを持ち寄り、震災時に人々がどのような情報をもとに、どのような行動したのかについて解析し、その結果、今後、震災が起きた際に被害を減らすためにとりうる重要な施策が数多く導かれました。
世界中の人々が自由に発信し、そのことが意見の多様性と議論の進展に寄与し、それらが集約され、ビッグデータとして解析されることで社会の学習が深まる。そうした開かれた言論空間を築くことが長期的には健全な社会を築く上で最も重要ではないでしょうか。(了)






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)