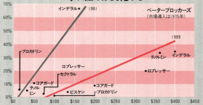-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
2013年7月に東京証券取引所は、MBO等にかかる株式価値算定書の開示を強化するよう上場規定の運用を見直した。これによって企業価値評価過程はどこまで検証可能になったのか。開示された情報から独自に計算してみた。
筆者は、2011年11月29日付けの本ウェブサイトの記事(エディターズ・チョイス「緊急提言・オリンパス事件からの教訓:M&A取引価格の根拠を開示する仕組みを確立せよ」)において、企業の合併・買収(M&A)取引において、第三者によって作成されている株式価値算定書の開示について、4つの提言を行った。記事執筆の契機となったのは、オリンパスがM&A取引を装って損失隠しを行った取引において作成された株式価値算定書であったが、通常のM&A取引においても、株式価値算定書が頻繁に当事者によって取得されているにもかかわらず、その内容の開示が不十分であることを指摘し、開示の充実を求めるものだった。
本稿は、昨年7月に東京証券取引所が、一部の取引(マネジメント・バイアウト(MBO)等、詳細は後述)について、算定書の内容について当事者により踏み込んだ適時開示を求めるよう上場規程の運用を見直したことを受けてのフォロー・アップ記事である。本稿では、特にディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)を用いた企業価値算定について、実際の企業価値算定のステップを確認しながら、今回の開示強化の意義と残された課題について論じることとしたい。
東京証券取引所による適時開示強化の概要
今般の東京証券取引所による見直しは、2013年7月8日付けの通知文によって行われた。その概要は、MBO等に関する意見表明、支配株主による組織再編を伴う場合における適時開示の見直しと、一定の場合に上場会社に提出を義務づけている算定機関が作成した算定書の実務上の取り扱いに関する明確化、の2点である。特にMBOと支配株主による株式公開買付(TOB)について、被買収企業が当該TOBについて意見表明を行う(「意見表明報告書」を提出)場合において、参照される株価算定書の内容について詳細な開示を求めている。具体的には、株価算定においてDCF法を用いている場合には、開示内容として、以下のような項目を掲げている。
1.算定の基準とした財務予測(各事業年度における売上高、営業利益、EBITDA(営業利益に減価償却費やのれんの償却を加えたもの)、およびフリー・キャッシュフロー)の具体的な数値(ただし、上場維持を前提とする場合を除く)
2.算定の前提とした財務予測の出所
3.算定の前提とした財務予測が当該M&A取引の実施を前提とするものか否か(筆者注:いわゆるシナジー込みの予測かどうか)
4.算定に用いられた割引率の具体的数値(レンジで示すことも可)
5.算定の前提とした財務予測で大幅な増減益を見込んでいるときは、当該増減益の要因
6.継続価値の算定手法および算定に用いたパラメータの具体的数値(レンジで示すことも可)
7.その他特殊な前提条件がある場合には、その内容






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)