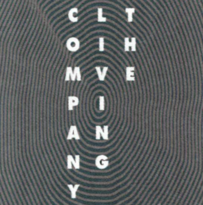市場地位毎に、違う戦略が必要
市場には、リーダー、チャレンジャー、ニッチャー、そして、フォロワーという位置づけがあるが、4つそれぞれ違う戦略定石が必要である。市場地位に応じた戦略定石を行わないと失敗する、というのが市場地位別の戦略のあらましである。
例えば、リーダー戦略の要諦は、フルライン、同質化、非価格対応、総需要拡大、周辺需要の拡大である。つまりリーダーは基本的にフルラインで商品提供し、新機軸で攻め込む競合がいたらすぐさま真似をして取り込むべきであり、シェア競争のあまり低価格勝負をしてはならず、市場需要の総量の拡大、とりわけ周辺需要の拡大を狙うべきだ、というのである。
なぜなら価格勝負になった時に一番打撃を受けるのはリーダーであり、市場が拡大した時に一番メリットがあるのもまたリーダーだからである。チャレンジャーはあらゆる方法で差別化を模索すべきであり、ニッチャーは限られた領域においてリーダー戦略をとるべきであり、フォロワーはなるべく開発コストや宣伝コストをかけずにリーダーの主要製品を模倣すべきである。
見事な市場リーダー戦略
さて、コトラーにはこれまで改訂を含めずに数えると、56の著書がある。その類型化を試みると、まずは、教科書の類。全部で7点あった。出版点数ではそれほど多くはなくとも、改訂の回数と売れている部数では圧倒的である。さらに、専門を深めるものは4点と少なく、新時代のマーケティングの啓蒙・評論は、14点と意外と多い。そして、共著でマーケティングを新しい分野に適用している類は、圧倒的に多く、31点だった。(分類は筆者)
日経の「私の履歴書」の連載に書いてあったが、コトラーは、当初はマーケティング意思決定モデルについての専門書を処女作とするつもりだったが、より幅広い読者を獲得出来る教科書『マーケティング・マネジメント』を処女作とした。
すなわち、はじめからこの分野を作ろうと志していたのである。
ナンバーワンの認知を得るためにも、総需要を拡大するためにも、教科書を重視する戦略は極めて正しい。また、さすがにその当時はそういう概念が無かったため本人は意識していなかったと思うが、デファクトスタンダードになってしまうと強いということが、まさにこの教科書の戦略の要諦だったのだ。
興味深いのは新しい分野へのマーケティングの適用の数々である。例えば非営利組織、プロフェッショナルサービス、学校、人(有名人)、医療機関、国家、地域への投資の誘致、観光、寄付、環境、・・・とあらゆる分野でマーケティングが有効であることを、次々と共著本を出すことで示してゆく。まさにリーダー戦略の定石の「周辺需要の拡大」を自ら行っているのだ。
共著者は各分野のエキスパートであり、コトラーとの共著ならば部数も出るし名声も上がり、コトラーは執筆することで短期間にその分野についての知識を体系的に獲得し、マーケティングの周辺需要の拡大をするのだ。
さらに、新時代のマーケティングの啓蒙本を書いて新しい考え方を紹介したり、新しい知見は必ず教科書の新版では新しい章として加えたりすることで、もう一つの定石である「同質化」を行っていると見ることが出来る。これがある限り「もうコトラーは古い!新しい○○論を聞け!」という主張が意味をなさなくなるのだ。
事程左様にコトラーの出版戦略を見てみると「マーケティング界のリーダーとしての戦略定石」を見事にやってのけていることが分かる。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)