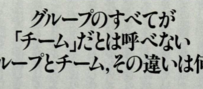-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
『世界はシステムで動く』の訳者・枝廣淳子さんと東京糸井重里事務所CFOの篠田真貴子さんによる対談の2回目。おふたりの対話を通して、システム思考がビジネスでどのように役立つかを探る。(構成:加藤年男、写真:引地信彦)
組織の構造を変えるには2通りのやり方がある
枝廣:子供は生まれながらにしてシステム思考家だという言い方があるんですよ。
篠田:ええ? そうなんですか。

枝廣 淳子氏
枝廣:大人になる過程でリニアな考え方を優先するようなしつけや教育を受けることで忘れていくという仮説です。生まれたときはいろいろな物事はつながっていることを直感的に感じていても、結果を出すために直線的な考え方に子供の頃から慣れ親しんでしまうのですね。
でも自然は循環していますから、循環するという考え方のほうが本来自然だと思います。そのなかの一部を取り出しているから直線に見えるだけで、大人のほうが近視眼的なのかもしれません。
篠田:たしかに赤ちゃんでも性質の違いがあって、すごく安定していてあまりグズらない赤ちゃんと、ずっと泣いている赤ちゃんがいます。赤ちゃんが泣き続けるのは不快感があるからで、それで十分ミルクが飲めなくて、そうするとおなか一杯になれなくて、眠れなくて、よけいに体調が悪くなってずっと泣くことになる。すると親もだんだん精神的に参ってくるから、それを感じて赤ちゃんはさらにまたご機嫌が悪くなっていく。これもループですね。
枝廣:そのときに赤ちゃんを怒ってもしようがないから、構造自体を変える働きかけをしないといけません。

篠田 真貴子氏
篠田:私は物事を考えたり進めたりするときに、要素に分解することと、それを統合することをセットにするというイメージを持っています。それはリニアに考えるときもそうなんです。要素に分解して、そのつながりをリニアにとらえていたとしても、最後は「商品が売れる」など何か統合的な結果が出る。でもシステム思考によって循環していると考えたほうが、要素のつながりがすでに統合しているというイメージをもちやすいと思いました。
枝廣:組織の場合、難しいのは部署が分かれていることです。それぞれの部署が個別最適化をやってしまう。たとえば製造部門の人に全社的なつながりを考えなさいといってもすごく難しいんですね。だけど本当は組織のシステムは部門で分かれているわけではありません。人間が人為的に部門に色つけをしているだけなんです。
そこで構造を変えるには2通りやり方があって、一つは経営者なり部門の上に立つ人が全体をつながりとして見ること。もう一つは各部門が話し合って改善することです。そのために私たちは、製造や営業などいろいろな部門の人たちに集まってもらい、会社全体のシステムを考えるワークショップを開くことでお手伝いしています。最初は製造からはこう見えている、開発からはこう見えていると自分たちから見えていることしか話ができないのですが、ワークショップをやっているうちに、自分たちがよかれと思ってやっていることが、実は他の部門にとってマイナスの循環をつくることになっていることに気づいてきます。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)