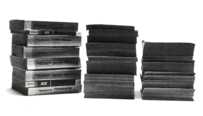-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
GEはなぜ優秀な人材を輩出できるのか。リード・ホフマンらの著書『ALLIANCEアライアンス』の刊行を機に、GEの事例から新しい働き方・雇い方を考える。今回は、GEキャピタル社長の安渕聖司さんと同書の監訳者で「ほぼ日」の篠田真貴子さんに対談していただく。
ジャック・ウェルチは、人材育成に投資を惜しまなかった
篠田:リンクトインの創業者、リード・ホフマンは『ALLIANCEアライアンス』という本の中で、企業と人の長期的な信頼をベースにしたフラットな雇用関係を提唱しています。本書をお読みいただいた感想からお聞かせいただけますか。

(やすぶち・せいじ)
日本GE株式会社代表取締役。GEキャピタル社長兼CEO。
早稲田大学政治経済学部卒後、三菱商事に入社。90年、ハーバード・ビジネススクールMBA修了。99年米投資ファンド、リップルウッドの日本法人立ち上げに参画。2001年、UBS証券会社入行。06年、GEコマーシャル・ファイナンスにアジア地域事業開発担当副社長として入社。07年、GEコマーシャル・ファイナンス・ジャパン社長兼CEOに就任。09年より現職。著書に『GE世界基準の仕事術』がある。
安渕:ひとつは、GEは必ずしもこの本に書いてある通りの形ではないにしても、従業員が卒業したあとのネットワークの考え方はあるし、終身雇用はできなくても終身雇用に値する能力を持った人材に育てるという考えはジャック・ウェルチのころからずっと言っています。だから「そうだよね」という納得感が正直な印象です。
もうひとつは、自分のキャリア振り返ったときに、会社の資産を使って自分の能力を高め、それをまた会社に返すというこの本『ALLIANCE アライアンス』の内容を実際にやっていたことを改めて思い出しましたね。
篠田:本書にはGEの事例が何度か出てきますが、1960年代にはGEも終身雇用を目指していると明言していたことに興味を持ちました。でも、現在はそうではありません。この50年あまりの間に、どのような変遷があったのでしょうか。
安渕:本書では「maximizing employee security」と書いてあります。会社が成功し成長することが、従業員の「ジョブセキュリティ」をより高めるという話です。そのためにも、GEは1956年に「クロトンビル」という企業内ビジネススクールをオープンし、マネジャーに対するトレーニングを始めています。その一方で、1981年にCEOに就任したジャック・ウェルチは「ニュートロン・ジャック」との異名を取るほど、徹底的に事業を整理しています。当時の42事業部門から、有名な3つのサークル(中核製造業、技術、サービス)を使って、コアビジネスを絞り込み、それ以外の事業は「直すか、売るか、閉鎖するか」しています。

(しのだ・まきこ)
東京糸井重里事務所取締役CFO。
慶應義塾大学経済学部卒、1991年日本長期信用銀行に入行。1999年、米ペンシルべニア大ウォートン校でMBAを、ジョンズ・ホプキンス大で国際関係論修士を取得。マッキンゼー、ノバルティス・ファーマ、ネスレを経て、2008年10月、ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を運営する糸井事務所に入社、2009年1月より現職。2012年、糸井事務所がポーター賞(一橋大学)を受賞する原動力となった。この度、『ALLIANCEアライアンス』を監訳)
篠田:「信用」という概念が『ALLIANCE アライアンス』に流れる通奏低音だと思いますが、経営側からすればそんなこと言っていられないという状況だったのでしょう。それにしても、長きにわたって暗黙の信頼関係を作ってきた従業員が目の前にいたわけですよね。事業整理と従業員との信頼関係、この間のジレンマをどのように乗り越えたのでしょうか。
安渕:1970年代までは、アメリカである程度成功した会社には暗黙の契約のようなものがありました。毎日会社に来て、ちゃんと仕事をして、生産性も上げていけば、会社に忠誠心を誓っていることになる。それに対し、会社もちゃんと報いる。だからクビにすることはありません。ジャック(・ウェルチ)も言っていますが、その時代の人事考課は非常に生ぬるかったといいます。能力が低くても、昇格にも値するいい人ですと書いてしまう。社員もそれに甘えていました。それをジャックは「本当の親切ではない」と大きく舵を切ったのです。
それでも、一方では従業員のトレーニングに力を入れ、クロトンビルを拡充してリーダーシップのトレーニングコースを充実させます。そこから育った人間が、今のGEのシニアマネジメントにいっぱいいる。現在のCEOジェフ・イメルトもそのひとりです。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)