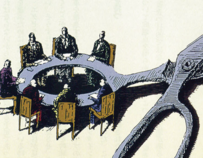-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
上司から規則の逸脱を求められた部下は、保身と良心の間で悩む。非倫理的な相手に抵抗しながら被害を最小限にするための、8段階の方法論を紹介。
私たちは何かの折に、職務上の規則を破るよう求められることがある。
それは、帳簿で端数の上げ下げをしてほしいというような、些細なことかもしれない。あるいは、その行為を見て見ぬふりをしてほしいという、些細な「非行動」の要求かもしれない。
要求が1度きりの場合もある。筆者らの1人が、かつて勤務していた病院で患者の記録の改ざんを求められた時のように。あるいは慣例化していることもある。その同じ病院では、不在の看護スタッフの出勤記録を他の者が代理でつけることが奨励されていた。
それはたいしたことではないかもしれない。そう、「規則は破るためにある」のだから。あるいは、たいしたことかもしれない。フォルクスワーゲンやエンロン、ワールドコムの例がそうであったように。
仕事で規則を破るよう求められると、ほとんどの人は葛藤を覚える。特に、次のような場合には難しい選択に直面することになる。その職に就いたばかりの新人である時。組織階層で低い職位にある時。現在の職や立場に大きく依存している時。そして、相手に好印象を与えたい時である。
うまくやっていくために従うか、それとも抵抗するか。出方によっては、組織にも自分自身にも重大な影響が及びかねない。
コンフリクト管理(意見や感情の衝突への対処)における通常のアドバイスは、「できる限りウィン・ウィンの解決策を見出すよう努める」ことだ。しかし、倫理や道徳、あるいは法に関わる問題に直面した場合には、そのやり方はまったく功を奏しない。たとえば、あなたの上司が以下のような行動を取っているケースである。
●詐欺行為や不正行為を働いている
●あなたや他の人にハラスメントをしている
●従業員や消費者の負傷を招きかねない状況をつくっている
●正当な抗議の声を挙げるための、あらゆる機会を阻止している
●違法あるいは非道徳的な活動を促している
●不正行為を隠している、あるいは隠すよう求めてくる
倫理観が強く、同時にいまの仕事を大いに必要としている従業員は、このような問題にどう対処すべきだろうか。
ここでお勧めしたいのは、我々が「道義に基づく抵抗(principled rebellion)」と呼ぶ、積極的かつ計画的なアプローチである。自身の倫理観を貫きながら被害を最小限に抑えるために、段階を追って戦略的に抵抗していくやり方だ。当事者への姿勢を少しずつ強めていき、順を追って連続的に拒否の意を伝えていくのである。
以下に、政治運動に関する文献から集めた知見に基づく戦術を、いくつかご紹介しよう。拒否の姿勢が穏やかなものから強硬なものへと、順に挙げている。




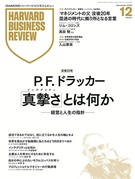
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)